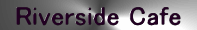 …「Natto」の話 …「Natto」の話 |

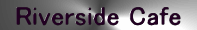 …「Natto」の話 …「Natto」の話 |

小生の好物に「納豆」があります。以前にドイツで暮らしていたとき、一番困ったのが納豆が高かったこと。日本では100円もしないやつが、現地のアジア食材店では一箱5マルクもしました。 当時の邦貨換算では350円、しかも冷凍です。そのまえ米国にもしばらくおりましたが、ここではさすがに日本人が多いためか、現地生産納豆などもあって、値段もそこそこで不自由しませんでした。
米国生産の「日の出納豆」⇒
 海外向け納豆。米国以外は冷凍輸出になる。たれに入っているみりんが酒類にあたるとか言って、EU税関がいちゃもんをつけて「たれ付き」がしばらく手に入らなかった時期もありました。 海外向け納豆。米国以外は冷凍輸出になる。たれに入っているみりんが酒類にあたるとか言って、EU税関がいちゃもんをつけて「たれ付き」がしばらく手に入らなかった時期もありました。ところが欧州はやっぱり日本からは遠い。 そんなわけで、年に何度か日本に出張する際は、帰りのスーツケースは殆ど日本食だったわけですが、なかでも納豆は極めて大きなスペースを占めていたものです。 当然そんなに一度に食べれるわけではなく、家に戻ったらみな冷凍してしまうのですが、それでも現地の食材店で長期間冷凍していた納豆よりは、ずっと美味でしたね。 そんなことも忘れてしまった今日この頃、小生がひそかに尊敬する町田忍さんの本「納豆大全」(小学館)を図書館で見つけ、何やらこの摩訶不思議な食べ物のエッセイを書いてみたくなりました。 納豆というと「嫌だ〜」「気持ち悪い〜」という人は多いですが、都道府県別の傾向をみるとやっぱり東高西低。(下記表) たしかに関西では、糸引き納豆はポピュラーではないようです。これは寺納豆(後述)の歴史的な影響もあるのかも知れません。 ドイツの駐在員時代に日本出張した際、最後が関空から帰独という時があったのですが、前夜宿泊した大阪で、ホテルの近辺のコンビニにいったところ、店員さんから「なっとう? ああ、あの卵かけて食べる奴ね〜。そんなもんおいてあらへんよ。」 がび〜ん、となりました。 梅田近辺のコンビニを十軒以上回ってようやく三十パックほど確保した記憶があります。「俺はこんなところで何をやっているんだ??」と自問自答しながら、深夜の梅田界隈をフラフラ徘徊していた駐在員。今となっては面白い思い出です。 血を奇麗にしたり、血圧を下げたり、はたまたO157などの抗菌作用を始めとして、納豆の数多ある栄養価を知らない人はいないでしょうが、ビタミンKについては余り知らないでしょう。これは骨をつくるビタミンで、納豆には大量に含まれております。 都道府県別納豆消費量
 野菜類の十倍近く含まれていて、納豆の消費の多い茨城県では、大腿骨骨折が日本一少なく、もっとも消費量の少ない和歌山県では、逆にもっとも多くなっております。 ドイツでは日照量が少ないことから、幼児期にビタミンKの投与が義務付けられておりますが、そういう意味でも現地で納豆を漁っていたという姿は、そうおかしなものではなかったのでしょう。 米国では「Steamed-Soy-Beans」とか「Fermented-Soy-Beans」とかいって現地生産もしておりますが、ヨーロッパでは気候の関係からか現地では作れず、全て日本からの輸入に頼っております。もっとも海外での需要はせいぜい日本人駐在員や留学生などで、現地人にはほとんど人気がない感じです。  「おかめ納豆」で有名な、業界最大手の「タカノフーズ」でも輸出比率は1%にも満たないそうで、同じ原料の「豆腐:Tofu」が、海外で健康食品として人気を得ているのと対照的に、「Natto」の国際認知度はいまひとつのようです。 「おかめ納豆」で有名な、業界最大手の「タカノフーズ」でも輸出比率は1%にも満たないそうで、同じ原料の「豆腐:Tofu」が、海外で健康食品として人気を得ているのと対照的に、「Natto」の国際認知度はいまひとつのようです。いまやコンビニでの定番「おかめ納豆」、現在は「三つ」入りが主流。味はバランスが取れている。さすが業界トップの実力。 近々、水戸方面へ行く用事が出来たので、本場の天狗納豆を入手しようと思っております。(数ある納豆のなかでもこれが一番好き)  本場水戸の「天狗納豆」。同名のブランドがもう一つあり、どちらも美味い。
ただ個人的にはこっちが、駐在時代に世話になったのでリコメンドしたい。あまり首都圏では売ってないが安くて美味い! JR水戸駅に各種取り揃えてあるとの事なので、いろいろ買ってじっくり食べ比べてみたいものである。 PS:ゴルゴ13が渋い表情で、天狗納豆を食べる様は想像するだけで愉快。 注:寺納豆は遠く平安の昔から古文書に記述がのこっています。浜名湖の大福寺や京都の大徳寺などが有名。別名塩辛納豆とも呼ばれますが、乾燥していて塩辛いのが特徴。もちろん糸は引きません。「僧坊の台所(納所)で作られた豆」ということで「納豆」と呼ばれるようになったらしい(諸説はある)。 いま主流となっている糸引き納豆は、歴史はずっと浅く、明治になって水戸にまで鉄道が開通された際に、水戸の名産として全国に広まったものです。 |