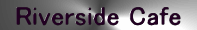 …ドイツのカーニバル …ドイツのカーニバル |

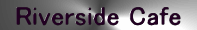 …ドイツのカーニバル …ドイツのカーニバル |

|
松葉杖騒ぎで忘れてしまいましたが、そういえば先週あたりがドイツのカーニバルだったことを思いだしました。 二月の中旬が、一年のうちもっとも冷え込む時期で、これは北半球のいずれの国も同じ傾向だと思います。 ドイツでも、この時期は氷点下が普通で、たまに2〜3℃にもなると「今日は暖かいなあ」とか感じてしまいます。 そしてこの厳寒のときにカーニバルが始まります。復活祭のまえ四旬節(40日)のあいだ、身を清めるため肉食を禁じるキリスト教の教えで、その直前に最後の馬鹿騒ぎをしましょうという趣旨で始まりました。 ラテン語の「肉よ(Carne)、さらば(Vale)」が、カーニバルの語源らしいですが、この風習は大なり小なり、ドイツ各地で行なわれます。現地では「カルナヴァル:Karneval」とか「ファスナハト:Fastnacht」と呼ばれます。 ファスナハトは、四旬節に入る直前の「バラの月曜日:ローゼンモンターク」でピークを迎えます。特に有名なのはケルンやデュッセルドルフ、マインツなどの西の地域で、街の人たちはみな化粧をしたり仮面をかぶって一日騒ぎます。 
こわいのはローゼンモンターク前の木曜日で「ヴァイバーファスナハト:Weiberfastnacht」と呼ばれる日で、この日は「女達のカーニバル」という意味で、この日は女性は何をしても良い。街ではそこかしこでハサミを持った女性達がうろつき、ネクタイを締めた男性を見るや、抑えつけて、結び目の下からチョッキン! これは旅行者でも関係無く、一度イギリス人と日本人出張者を連れて、その日とは知らずデュッセルドルフに出張しましたが、みな襲われてしまい、あわれ帰りには、スーツ姿に結び目のしたからキレイに無くなっているネクタイ、という出で立ちに相成ってしまいました。 空港に行ったらそんなビジネスマンが一杯。同行したイギリス人は「外国からのお客様にはそんなこといたしません」とか受付嬢に言われて、ホッと油断したところを電光石火に襲われてスパッ!「俺は金輪際ドイツの女は信用しない」とか本気で怒っていました。 まあ現実にはいろいろな人がおりますが、良い意味でドイツ人は悪ふざけも"真面目に"徹底しますので、かえって付き合うには安心できる部分はありますね。 さてローゼンモンターク(特に盛んな西部以外はその直前の週末)には、山場のパレードがあります。氷点下という厳寒のなか、いつものグリューワイン(お燗した香料入りワイン)やブラートブルスト(焼きソーセージ)で暖をとりながら、ほとんどの市民は広場や目抜き通りにでて、パレードの花車や騎馬隊を見物します。お目当ては花車の上にいる仮装した美女や美男?や妖精(子供たち)から大量にばらまかれるお菓子。 それこそ半端な数ではなく、雨あられと降り注ぎます。「万歳!:ヘロウ!」とか互いに呼応して、これを拾ったりカサを逆に広げたりして集めるわけですが、花車の列は延々と続き、終わることにはポケットや袋の中は一杯。聞いたところではケルンでは有名なコロン「4711」の小瓶までばら撒かれるとか… これを過ぎると長い冬からやがて春に向かいます。
 |