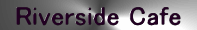 …龍とドラゴンの話 …龍とドラゴンの話 |

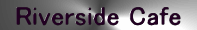 …龍とドラゴンの話 …龍とドラゴンの話 |

ちょっと乱暴ですが「竜は東洋、ドラゴンは西洋」という図式も、概ねあたってはいるのですが、それぞれの地方で独特の竜あるいはドラゴン像というものがあり、一言で定義付けはとうてい出来ないことが分かってきました。 そもそも竜類もドラゴン類も数多いて、二つはあくまで「総称」という概念と考えた方がいいのかも知れません。 さて「総称としての竜」の話をするには、そのなかの個別種「龍:ロン」の話から始めなければなりません。龍は東洋の竜の元締め的な存在でもあり、西洋のドラゴンと比較する際は、龍の文化的背景からみることが、竜&ドラゴンの全体像を理解するうえで正しいかも知れません。 
四川省、山東省から新彊ウイグル地区では今なお恐竜の骨が、それも浅い地層でしばしば発見されますが、おそらく大地震や崖崩れによって当時の人目に触れた可能性もあるでしょう。 驚くべき巨大な骨、その中にはチラノザウルスもいたでしょうし、翼竜プテラノドンの骨もあったでしょう。当時の人々は恐れおののき、そしてそこから畏れの対象として「龍」を連想させていったのかもしれません 現代から確認できる、当時の人々の龍に関するエビデンスのうち、最も古いのは新石器時代です。六千年前に作られたC字スタイルの石器「龍の玉」がその最も古いものとされております。場所は内モンゴル〜河北地域でした。 さらに下り親石器時代後期にさかえた紅山(ホンシャン)文化では、龍を描いた壺などが出土されたりしてます。 四千年前の龍山文化は黄河の中流域〜下流域、山東、河南、山西地方で栄えました。黒陶文化とも言い、黒褐色の薄い陶器が有名ですが、この中にも見事な龍の絵が描かれております。 このようにして龍の形は次第に作り上げられていき、三千年前の殷の時代には、ほぼ今の形の龍ができあがっておりました。 漢の時代に龍のイメージは完成。約2200年前には、漢の高祖の「劉邦」が卑しい自分の家系を高めるために、龍神の生まれ変わりのようなプロパガンダを行ったという記述は有名な話です。このアイデアは秦の始皇帝からパクった話ですが、このようなことから中国では皇帝と龍のイメージを同位置におくような執政がとられてまいりました。 
龍ののどの下には49枚の逆向きの鱗があり、これに触れると龍は激しい痛みを感じて怒り狂い、触った者を食い殺してしまうそうです。そんなことからこれを「逆鱗」というようです。  日照りは農民にとっては死活問題で、中国の人々は龍の機嫌を損ねないように、雨乞いをしたりしました。 水を司る龍は、魚やヘビなどの鱗を持つ生き物すべての祖先で、彼らの暮らしている水の中を統治している王とされておりました。龍の口からのあの炎も湿気を持つとなお激しく燃えさかり、かえって乾燥した場所ではあっさりと消えてしまうという特徴がありますが、これも龍が水の王たる所以かもしれません。 龍の神通力の源は、手に持っていたり、あるいは首の下に隠されている「如意宝珠」という宝の玉によるものです。この玉の霊力によって、天まで昇ったり地の底まで一瞬に潜ったり、あるいは身体の大きさや形を思いのまま変えることができるので、中国では多くの人々が何とかして手に入れようと競ったそうです。  さらに龍は成長期に蛟(ミヅチ)という幼年時代を池や川の中で500年間過ごして、その一部がようやく龍となります。したがって人々の目に触れる竜は、ほとんど蛟といって差し支えないのかも知れません。だいたい3m前後の体長で、角もあまり生えていません。 蛟は、湖や淵、池や川などの淡水で暮らす生き物すべての王で、魚の群が2600匹を越えると、どこからともなく蛟がやってきて、そこの王となります。蛟の霊力は龍ほど強くなく、雨雲を呼び寄せたり、住処の水が枯れることをさせないといった程度の力だそうですが、農民にとっては干ばつを防ぐために、この蛟をとても有り難がったそうです。
竜神さまの棲む水場は神聖で、石を投げ込んだり、鉄製品を水につけたり、汚れた足を洗ったりすることは厳禁とされており、やぶった場合はたたりがあるとされております。人々は竜神さまに供物などをあたえて祀りました。 このように龍(ロン)を代表とする東洋の竜たちは、いずれも民から畏怖の対象としてだけではなく、瑞祥として、それぞれの生活環境のなかに取り込まれて親しまれてまいりました。ここが東洋の竜の特徴です。 東洋から西洋に話を移す前に、ちょうど中間にあるインドに立ち寄りましょう。インドでは竜として伝わる存在は「ナーガ」です。サンスクリット語源で「ヘビ」の怪物です。インドやタイを中心に今も残っており、ヘビのような長い身体とコブラのような大きな頭が特徴です。 ナーガはインドの神話に出てくる地下に住む怪物で、その情欲の熱で川や湖を煮えたぎらせ、植物は枯らしてしまいます。やがて正義の神クリシュナとの戦いで敗れ征服されてしまいますが。このルーツは、当時ガンジス〜メコン〜揚子江中流域に広く生息していたクロコダイルの一種「グンビーラ」だったのではと言われております。現在このワニはインド〜ネパール地域の保護区でしか見られませんが、鼻先が大きく丸くなっている事からもナーガの特徴と酷似しているためです。 脱線しますが、グンビーラはシッタータ族のトーテムとして扱われていて、日本にはいってナマって「コンピラ→金比羅」と呼ばれるようになりました。これはご存じの通り四国の琴平町などにありますが、航海安全の神様として奉られております。 インドのナーガは細長い胴体と巨大な頭をもち、形態的には中国や日本の竜と、西洋のドラゴンの中間的な要素をもっておりますが、その位置付けは王様という偉い存在ではあるものの、あくまで悪役で、やがて正義の王によって倒されてしまうというもの。これも東洋の畏怖観と西洋の悪魔観とが折衷されていて、インドの文化的な位置付けを図らずも示していると言えるでしょう。
荒っぽく言えばユダヤ人のための書である旧約聖書と、イエスキリストによって成された救済を説く新約聖書とは、主旨はまったく違いますが、ともに「ドラゴン」は倒すべき敵として描かれております。 旧約聖書ではドラゴンとは言わず「タンニーン」と呼ばれて、長大な怪物という意味があります。海を割って水の中にいるタンニーンの頭を、我がユダヤの王はうち砕くという記述があります。 また新約聖書では、ヨハネ黙示録のなかでドラゴン=サタンと位置づけて、大天使ミヒャエルによって、ドラゴンは殺されてしまいます。  東洋の竜のような霊性や畏怖感はなく、単に凶暴な怪獣という位置づけは西洋人の一般的なドラゴン観のようです。
 |