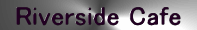 …川舟の話 …川舟の話 |

さて船というと、誰しも海に浮かぶ船を思い浮かべてしまいますが、この日本には多くの河川があり、そこには古くから川舟が使われてまいりました。このあまり日の当たらない船のジャンルである「川舟」について、少々話をしてみましょう。 さて「船」とか「舟」とかいう呼び方がありますが、慣例的には大型船を「船」、小型船を「舟」と呼ぶようです。ですから今日はもっぱら「舟」の話になります。(ちなみに法規上は、大小関わりなく「船舶」と称するようです) 歴史を振り返りますと、ヒトの暮らしと河川は緊密な関係を保っていて、これは古代文明を引き合いに出すまでもなく、日本の歴史ある内陸都市で河川に近接しているものが極めて多いことが分かります。人が集まれば、商業の発達とともに物資の移動が必要になり、そこに水運が生まれます。 海の上の島嶼はともかく、舟の起源はすべて内陸河川からであり、これを研究することが「舟」から「船」への歴史を勉強するうえで重要なのではないでしょうか?また河川を媒体として民俗文化が系統的に広がっていったわけで、河川交通史は、実は「河川民俗文化史」という側面も併せもっているというわけです。 ハードウェアとして川舟を見た場合、海の船以上に名称もまちまちで、形状も実に多岐にわたっております。この理由は各地でそれぞれ独創的に作られたという点と、後生になって形式や製法などの交流が行われても、各地の河川の状況に応じて、それぞれ独自の工夫や分化が行われてきたためだと思われます。例えば、利根川水系で使われてい川舟の分析結果では、なんと40数種もあり、それらの分類も、発展史的には極めて複雑であるということからも分かります。
さて河川交通を考えた場合、昔の主要物資はコメ、シオ、木材でしたが、これらを馬や馬車で運ぶことは極めて非効率ですので、川舟が活躍したというわけです。駄馬1駄で40貫といいますので、米俵二俵といったものを運ぶのに対して、舟は300俵から500俵積むことが出来ますので、その効率は言うまでもありません。
丸木舟:原始的な舟の代名詞にもなっている、造船は一般的には海岸部で行われるという感が強いのですが、意外にも川を遡った山中、材木の豊富なところで作られておりました。下北の川内川の奥地にある「畑」という部落や、新潟奥の荒川水源に近い「三面」などでは、狩猟や薪作り、木の伐採などと並んで舟造りは重要な生業だったようです。 丸木舟は土地によっては、単に「フネ」とよんだり「エグリ舟」などとも呼ばれておりました。クニマスで有名だった田沢湖では、四間〜四間半のエグリという舟があって、肥料用の刈草や薪などを運んでいたそうです。 上にある川内川の畑部落で作られた舟は、後年それを素材にして河口にある川内町で手を加えられて、漁民に売却するようになりましたが、この例からもフネの発祥の地としての「川」の役割と、舟造りの発達の過程を示していて、けっこう興味深いことです。 高瀬舟:森鴎外の小説の題名にもなっているこの舟の呼称は、いまや川舟の代名詞的な扱いを受けているようですが、実際のところ思い浮かべるような具体的な舟のイメージはあまりなく、まあこれは河川交通がいまや遠い昔の歴史の一コマになってしまっている、ひとつの証左でしょう。 この舟の名は、京都の高瀬川を上下する川舟として有名になったわけですが、古書の記述では元慶八年(884)にもあるようですので、そうとうの歴史をもっている舟です。後世になっては輸送船としての役割が殆どでしたが、初期は貴族の舟遊び用として使われていたようです。作歌、作詞あるいは管弦楽などで乗る舟を分けて、それぞれ楽しんでいたそうですので、やはり氏素姓は立派な舟だったようですね。 浅い喫水、平らな船底、そして細長い船型とそり上がった舳先、というのが共通スタイルですが、年貢米や物資の輸送に活躍しました。後期には帆をもって大型化し、利根川で動いていた大型船は長さ27m、幅5mという規模。これで米1200俵も運ぶことが出来ます。これを舟子4人で動かします。 ヒラタ舟:高瀬舟は全国の河川にあまねく伝播いたしましたが、これと同じ様な川舟に「ヒラタ舟」があります。「ひらた」とか「平田」などとも言われて、主に石や石炭、砂利の運搬に使われていたようですが、川漁や米運搬にも使われておりました。形状は高瀬舟と酷似しておりますが、舳先が角形であり、世事(せいじ:舟の厨房)が後部に位置していて、タナイタのところも頑丈に補強されているいるところが特色です。大きさはいろいろあって、三人乗り二百俵積みから、大型では21〜25mほどの長さをもっていたようです。 その他の川舟:40を超える川舟をすべて紹介することは出来ませんが、なかでも面白い用途の川舟をここで取り上げてみましょう。
湯舟:これは名のとおり、銭湯の川舟です。利根川筋などを巡回していて、やってきた合図にホラ貝吹きますと、船頭や河岸の住民がやってきてひとっ風呂浴びるというわけです。これもなかなか風情があっていいものですね。 茶舟:大阪や江戸には廻船といって、海上輸送の大型船が寄港いたしますが、沖に停泊した大きな船の積み荷を運ぶために、廻船と河岸を結ぶための舟を茶舟と呼びます。 水舟:水を売る舟です、湿地帯を埋め立てた江戸下町では、井戸を掘っても海水が混ざり、良質の水を得ることが困難でした。このために玉川上水の水が行き届かない下町の運河筋には、この舟によって運ばれた水が重宝がられたそうです。なお関西でも淀川筋に水舟があったそうです。 猪牙舟:「ちょきぶね」と呼びます。まあ、これは江戸時代のタクシーといったところでしょうか。スマートでスピードが出るので人気がありました。これで吉原に通う、というのが当時の伊達男のスタイルだったそうです。ただし櫓漕ぎなので乗り心地はけっこう悪かった様です。
川蒸気:日本で初めて蒸気船が就航したのは明治十年。利根川航路の「第一通運丸」という名前で、両舷につけられた水車で動く、いわゆる外輪船です。これは「川蒸気」とも呼ばれて人気も高く、淀川など大河川では川蒸気の就航が盛んになりました。川蒸気の登場でも、高瀬舟の輸送力はあまり衰えず、明治20年中頃には、利根川航路だけでも高瀬舟とヒラタ舟などは年間3万8千隻もの盛況を呈しておりました。 明治30年以降、河川事業は治水を目的に高い連続堤防を築きはじめ、河岸から河岸への舟運には妨げとなってまいりました。廃止されたり、さびれたりする河岸が増えて、川には橋が増えていわゆる「渡し」も減り、鉄道の発達とともに輸送の主役は代わり、人々の意識も次第に川から離れていってしまうことになりました。 |

