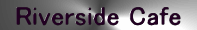 …マークトェイン …マークトェイン |

先日、柄にもなくディズニーランドに家族を連れて行きました。例によって掲題の蒸気船に乗って、解説を聞いていたら「マークトェイン」とは深度二尋のこととか、ペンネームの由来を知らなかった小生が無知でしたが、これで興味をもって「川蒸気」の話を調べてみることに致しました。 川蒸気については「川舟の話」にも少しばかり乗せましたが、そのルーツは、やはりフルトンやリヴィングストンの蒸気船の話にまで遡ります。 それまで人力で櫓をこいだり、帆を張って風力で進む帆船がメインでしたが、蒸気機関の発明によって、これを推進機関に応用する考えが出てまいりました。だれでも初めに考えることは、大きな水車を回して、その力で前進するということ。これが「外輪船」の始まりです。外輪はパドルホイールと呼ばれ、それを回して進む外輪船は、パドルホイーラーと呼ばれました。 アメリカ人のフルトンは、もともとは肖像画家でした。英国に渡って、画家の弟子として働いておりましたが、なにしろ当時のイギリスは産業革命華やかなりし頃。とたんにヤマっ気がでたのか、絵をすてて渡仏。
ナポレオン戦争中だったフランスに、手動潜水船の売り込みを計ったり、イギリス侵攻用として平底船を曳航する蒸気船を試作したりしましたが、どれも相手にされず腐っていたところ、在仏アメリカ公使リヴィングストンの目にとまり、運が開けてまいりました。 リヴィングストンの後援で、フルトンは1803年に全長31m、船幅2.4mで、両舷に直径3.5mの外輪を付けた試作船は、セーヌ川を流れに逆らい時速2.9マイルで走らせたそうです。ところがこれでもフランスでは相手にされず、フルトンは1806年に帰米。
アメリカの地を踏んだフルトンはリヴィングストンの地元、ハドソン川で蒸気船ビジネスを興します。ハドソン川の一流造船業者であるチャールズ・ブラウンに船体製造を、主機関をワット社に特注して、乾坤一擲の思いで作り上げられたのが、全長42.8m、船幅4.3m、喫水は1.2mという80トンの細長い船。これに松の薪で動く20馬力の蒸気機関による片舷2輪×2の外輪をドッキングさせのが、アメリカでの川蒸気一号が「ノースリバー・スティームボート・オブ・クラーモント号」です。
 ノースリバーはハドソン川の俗称、クラーモントはリヴィングストンの所有地をあらわしております。この船は通称「クラーモント号」とよばれ、1807年8月、ニューヨークの岸壁を離れた同船は、途中クラーモントに寄港し、150マイル上流のオルバニーまで32時間かかって汽走致しました。平均時速は4.7マイル。
帆船は、もしも強い順風が吹き、速ければ16時間でニューヨークからオルバニーまで行ってしまいますので、大したことはない記録のようですが、自然の風が相手の帆船では、速度のバラツキが大きく、平均では4日間もかかってしまうので、時間が読める川蒸気のメリットは大きく、営業運行を開始してみると大当たり。このようなことからフルトンは蒸気船ビジネスの開拓者だったといえるようです。
アメリカでは「スチームボート」と呼ばれ川蒸気が有名ですが、その登場はずっとあと。初めのうちは日本などと同様に、人力で船で動かしておりました。 ミシシッピ川は、カナダに近いミネソタ州に水源をもち、東のアパラチア山脈、西のロッキー山脈からの水を集めて流れる広大な川です。 その流域は31州、合衆国の1/3を網羅し、開拓時代の米国にとっては、まさに内陸の交通路の大動脈だったわけです。 ところで「当時の西部」というのは、いまのそれとはエリアが違い、アパラチア山脈の西側がすべて「西部」として扱われました。オハイオやイリノイ、インディアナ、ウィスコンシン、ミシガンなどもこの範疇にはいりました。 蒸気船の導入前から、ミシシッピ川には多くの川舟が航行しておりました。一つには「筏舟=ラフト」です。筏の上にログハウスを載せた筏は、2〜3家族が同居しながら、ゆっくりとミシシッピ川を下り、貿易港ニューオーリンズで西部の品々をさばき、残った筏やキャビンはそこで木材として売却するという、「一方通行」の川舟です。 一方通行の舟には「平底船=フラットボート」というのもあり、6〜30mほどの、幅の広いちゃちな舟ですが、これに牛馬を乗せてニューオーリンズに下ったそうで、河口で船材は廃材として処理されたそうです。若かりし19歳のリンカーンが雇われて、ミシシッピ川を下ったのもこの平底船です。 また「竜骨船=キールボート」という、日本の川舟のようなものがあります。これは舟の背骨にあたる竜骨を舳先から船尾まで通して強度を維持。舟幅も狭く細長い竜骨船は、喫水も60cmしかなく、南部の浅い河川もすいすい走れたそうです。8人乗りで船長と舵取り、それと両舷に4人ずつが「川船頭:リバーマン」が居て、棹をさして進むそうで、川下り2ヶ月、川上り4ヶ月で往復したそうです。 さて、東海岸のハドソン川で川蒸気ビジネスに進出したフルトンは、この広大な南西部マーケットに着目して、リヴィングストンの後援を得てニューオーリンズを中心とした、内陸水運に進出するために「ニューオーリンズ号」をペンシルバニア州ピッツバーグで建造致しました。
船舶の完成後にモノンガヒラ川から、オハイオ川の濁流を下り、ニューオーリンズまでの2000マイルの航行をしました。ところが東部スペックの川蒸気では、喫水線が深すぎるため、沈木などが多く、河床が浅いミシシッピ川では航行に支障が出てしまい。結局のところは川を下っただけで、あとは下流域の川の深いところしか航行することが出来ませんでした。フルトンは南部の河川と川舟の研究を怠ったため、ここではビジネスは上手くいきませんでした。
やがて本格的なミシシッピ型川蒸気は、1816年に「ヘンリー・シュリーヴ」によって作られた「ワシントン号」全長45m/403トンです。やがてシュリーヴは改良型「ジョージ・ワシントン号」400トンを続けて出し、やがてこれがミシシッピの川蒸気の原型となりました。
喫水を浅くするために船幅は広くとり、ボイラーとエンジンは、ハドソン型の船底から甲板に持ち上げられ、貨物は船倉に積み込まれました。エンジンは復水器のない高圧機関を採用して軽量化。ボイラーには薪を使用しました。 そのまた外側に外輪を付けるわけですので、速度も速くはなく、格好もあまり良くありません。  船体の構造は、機関とボイラーを置く「メインデッキ」。その上に柱で支えた「ハリケーンデッキ」これは機関を雨水から守る役目からこの名が付いたようです。客室もこのデッキにあります。客室の上(屋根)にあたる部分が「テキサスデッキ」と呼ばれます。これはアメリカ人お得意のシャレで、テキサスデッキはメインデッキからもっとも離れており、メインデッキを「メーン州」に例えて、そこから最も遠い州であるテキサスをもじったデッキ名です。操舵室や船員居住区があり、居住区を「テキサス」とか呼んだそうです。
外観上の特徴は、とにかくチャチ。けばけばしく塗りたくったパドルボックス(外輪の上部を隠すカバー)や細長い二本の煙突が目立ちます。船材も生乾きの木材を使って、デッキを支える柱も細くて頼りなげ。 実際、西部の水路には沈木や、河床の泥から突きだしている朽ち木などがあちこちにあり、船底を開けてしまったり、座礁したり、しまいにはボイラーの爆発や火災なども多く、だいたい4〜5年の寿命だったようです。 火災が多いのは、積み荷が綿花であることなども一因だったようです。綿花以外では豚・毛皮・穀物なども積まれて、一路ニューオーリンズに向かいました。  さてミシシッピ型川蒸気の喫水はだいたい9フィート(2.7m)という感じが普通で、安全航行できる川の深さの限度が12フィート(3.6m)だったようです。12フィートは2尋(ひろ)であり、これを船員は「マーク.トウェイン」と呼びます。
マークトウェインはサミュエル=ラングーン=クレメンズのペンネームですが、川面にこだまする、「危険水域に入るぞ〜」という意味の「マ〜ク・トウェイン〜」という大声が、おそらくミシシッピ川のあちこちで聞かれたのでしょう。 川蒸気の場合、船長がその権威を誇示できるのは、入出港の時だけであり、一旦岸から離れると「水先人=パイロット」が、航行の全権を握ります。航行中は、停船や減速、回頭などの判断も船長は一切出来ません。 セントルイスからニューオーリンズまで、平底船は4ヶ月かかり、川蒸気は4日で着いてしまいます。このようなことから、1846年には2792隻も運行していた平底船も、南北戦争のまえ(1860年頃)にはわずか500隻にまで減ってしまいました。 1810〜1850年までの40年間で、985隻の川蒸気が水難事故に遭い、そのうち209隻がボイラーの爆発などで壊れてしまいました。火災になって犠牲になった人は数千人にものぼったそうですから、昔の川旅はちょっと命がけだったようですね。
川蒸気というと外輪を縦に回して推進する、というのが一般的ですが、これだと幅をとるため水門を渡るときに難儀したり、場合によっては水車を外して水門を曳航される場合もあったようです。 アメリカ海軍士官の「ウィリアム.ハンター」は、この縦の水車を横にして、船底脇に取り付ける「水平車船」を試作しました。これだと機関や推進器が水面下に隠されたため、両舷の砲門列を一杯とれるというメリットや、水門運河も楽に通過できるうえ、その場で回頭するという離れ業も出来るため、軍艦として極めてポテンシャルが高いものとして、初めのうちは評価されました。 1841年にハドソン川からエリー湖/オンタリオ湖を、静かに走り抜けるデモ航行時には、外輪船の大騒音に慣れていた群衆からは、大きな喝采をあびたそうです。 ところが世は大型船舶時代に移りつつあり、水車を回すだけの水平車船では、下膨れの逆鐘型の断面のため、大型化にともなってスピードが出なくなる。新たに出てきたスクリュー船の速度に、あっという間にスターの座を奪われてしまいました。出てきた時期が遅すぎたと云うことでしょう。 |

 |