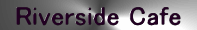 …鶴見川と杉山神社の謎 …鶴見川と杉山神社の謎 |

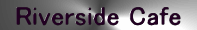 …鶴見川と杉山神社の謎 …鶴見川と杉山神社の謎 |

まえにHPで「サバ神社と境川」の話を取り上げたことがありましたが、鶴見川にも似たような話がありました。それは「杉山神社」です。
鶴見川本流。支流、恩田川、早渕川にとどまらず、それに連なる枝川にいたるまで、網の目のように分布している「杉山神社」または「杉山社」は、「武蔵風土記稿」によりますと、なんと72社にもおよんでいるそうです。なぜこのように「杉山」という名の神社が鶴見川流域に集中しているのでしょう。今回はこの謎を考えてみたいと思います。 さてこの話を遡っていくと、遠く神話の時代までいかないと駄目なようです。ちょっとばかり小難しい話になってしまいますが、ご容赦願います。 杉山神社の話をする前に、まず「忌部氏:いみべ氏」の話をしなくてはなりません。日本書紀によれば天照大神の岩屋戸隠れによって、天下は闇になってしまいました。八百万の神々が集まり次善策を協議するわけですが、そのなかに中臣氏の遠祖である「天兒屋命:アメノコヤネノミコト」とともに、忌部氏の遠祖である「太玉命:フトダマノミコト」がおりました。ともに祭事をとり仕切る神で、この流れをくむ「忌部氏本家」は奈良の橿原曽我川流域に強大な勢力をもっておりました。 忌部一族は各地にネットワークを張っておりますが、なかでも阿波の国にいた天日鷲命(アメノヒワシノミコト)を始祖とする「阿波忌部氏」が、杉山神社と深い関わりをもちました。 神事の場で、榊に掛ける祭具の木綿(ユウ)というのがあります。これは布の幣(ぬさ)を指しますが、原料に麻も使われております。また神官が着る衣にも麻が使われるなど、麻布は祭事に欠かせせないものでした。 それを作るのは、専ら阿波忌部氏でした。かれらは麻作りのプロ集団であり、いわゆる専門家集団を示す「部曲:かきべ」として阿波忌部氏は栄えたのでした。吉野川中流にある麻殖(おえ)郡、忌部郷を拠点として栄え、いまでも忌部神社が祀られ、往年の反映をうかがわせております。  古文書「古語拾遺」によりますと、太玉命の孫にあたる「天富命:アメノトミノミコト」の命により、忌部氏の全国戦略に基づき、阿波忌部氏の一派は東国に進出いたしました。時期的には神武年間のころだそうですので、まさにヤマトの国の始まり頃の話。阿波から移ったエリアに「安房の国」をたて、安房神社(画像)を建立いたしました。 古文書「古語拾遺」によりますと、太玉命の孫にあたる「天富命:アメノトミノミコト」の命により、忌部氏の全国戦略に基づき、阿波忌部氏の一派は東国に進出いたしました。時期的には神武年間のころだそうですので、まさにヤマトの国の始まり頃の話。阿波から移ったエリアに「安房の国」をたて、安房神社(画像)を建立いたしました。安房神社の祭神は太玉命であり、洲宮神社や洲崎神社など付近にある神社には、太玉命の后神である天日理乃咩命(アメノヒリノヒメミコト)が祀られました。この一帯はまさに忌部氏の東国進出の橋頭堡となったわけです。 小生は学生時代の夏場、洲崎や平砂浦で早朝釣りをしたあと、よく安房神社の境内(涼しい)でのんびり寝ころんでおりましたが、まさかそのような由緒がある神社とは思いませんでした。 朝廷祭官としての忌部氏本家の勢力範囲は広く、傍系の安房忌部氏も権勢強く、安房郡麻原郷(おはらごう)に拠点を構えて、麻(=総)を実らせる国、上総・下総を治めたと云うことでしょう。その痕跡として霞ヶ浦湖岸の行方郡麻生町や、利根川河畔にある下総の国印旛郡栄町安食(かっては麻生村)あたりにも地名が残っておりますので、千葉県一帯から茨城南部あたりまで勢力を広げていたようですから凄いものです。 さて時代はすぎ、12世紀のころ石橋山合戦に敗れた源頼朝は、海路を真鶴から房総半島へ逃走。いまでも南房総のあちこちに頼朝ゆかりの地が残されておりますが、そのときに上陸したのが洲崎だったそうです。頼朝は故事にも長けているうえ信心深く、おそらくはここの神社で亡命成功の感謝と再起への加護を願ったのでしょう。 鎌倉時代の杉山神社は幕府の加護をかなり受けていたようですが、忌部氏と源氏とのつながりが、このあたりから始まったのかも知れません。
ところで忌部氏が如何にして鶴見川流域に進出したのか?残念ながら日本書紀や古語拾遺には記述がありません。そのとっかかりは都筑郡茅ヶ崎です。いまでは市営地下鉄線「センター南駅」そばの都筑中央公園の一部となっている、鶴見川支流の早渕川を見下ろす小高い丘の上にひっそりとたたずんでおります。どんなところかと訪ねてみましたが、台地の東端に位置していて、まさに武蔵進出の第一歩としては絶好の地という感じです。
 白鴎三年(674)頃に建立されたという茅ヶ崎杉山神社の祭神には、忌部氏の大本である高皇産霊神(タカムスビノカミ:高木神ともいう、太玉命はその孫にあたるといいます)にならんで、阿波忌部氏の始祖「天日鷲命」とその子「阿波別彦命:アワワケヒコノミコト」の三神が祀られました。初代の斉主は忌部義麻呂とされております。
白鴎三年(674)頃に建立されたという茅ヶ崎杉山神社の祭神には、忌部氏の大本である高皇産霊神(タカムスビノカミ:高木神ともいう、太玉命はその孫にあたるといいます)にならんで、阿波忌部氏の始祖「天日鷲命」とその子「阿波別彦命:アワワケヒコノミコト」の三神が祀られました。初代の斉主は忌部義麻呂とされております。
さて何故「杉山」という名の神社だったのでしょう?いまでも面影がありますが、その昔はこの付近は杉の大木が林立するような丘で、そこに社を構えたことから「杉山神社」という名が付けられたのでしょう。当時では日本には自然信仰がまだまだ色濃く残っており、杉山にある種の神聖をだぶらせて、開拓の神として崇められたのかも知れません。 何故、忌部氏がその勢力範囲を武蔵に広げたのでしょう?どうやら当時の鶴見川流域は、安房忌部氏の生業「麻作り」という面で、じつに良い土地であったようです。 谷本川支流には「麻生川」があって、「上麻生」「下麻生」という地名がありますので、ここで麻が栽培されていたのが分かります。古い朝廷への麻の寄進記録によれば「常陸国」や「下総国」とならんで「武蔵国」が並んでおります。 さて、鶴見川流域には杉山神社や杉山社などと呼ばれた神社が、またたくまに広がりましたが、環境的には必ずしも「杉山」にあたらないようなエリアにも建立されました。これは別に杉山があろうとなかろうと、官弊社式内社である茅ヶ崎杉山神社の霊験にあやかりたいとか、忌部氏の威風になびくとかいうような理由で「杉山」の名をもって広がっていった事を示しているようです。一部の例外はあるものの72社もの杉山神社群はこのようにして出来上がったようです。 当時の武蔵における忌部氏の権勢を物語るエピソードがひとつあります。都筑郡のとなりにあたる橘樹郡(有馬、末長、新城、小杉、小倉、太尾、菊名、岸根、菅田、片倉、六角橋、下星川、など)は「稲毛庄」と重なっております。ここは町田方面の領主「小山田氏」の三男重成が興した庄ですが、稲毛重成の妻は頼朝夫人の北条政子の妹。当然として頼朝の幕府に重用されました。 ところが重成の妻は病死、この後妻として茅ヶ崎杉山神社の神主の娘が入籍いたしました(1198)。北条一門に続くような家格を安房忌部氏がもっていたことを、この政略結婚は如実に表しているようです。 そして、この婚礼を機に、稲毛氏や本家の小山田氏の勢力範囲である鶴見川流域へ忌部氏=杉山神社が進出していったことも想像されます。 この風土記からは、一部を除きそれぞれの神社の祭神は明らかになっておりません。おそらく当時としては、祭神というより、前述のとおり「式内社杉山神社」という霊験そのもので意味があったのでしょう。く
ところが人の世の栄枯盛衰をうけて、やがて杉山神社群も大きく傾いていきます。神社は国政と強く結びついているため、政治の流れの影響を被ってしまいます。中央の忌部氏は神事を取り仕切る役割を中臣氏(=藤原氏)に奪われていき、その朝廷内でのポジションを落としていきます。これが、時間差はあるものの、地方の傍流にあたる安房忌部氏の権勢に影響したことは間違いありません。郷や村の支柱であった社もその影響を受けてしまい、次第に忌部氏の威光が反映されなくなってまいります。
そしてだめ押しが「足利尊氏から受ける手痛い打撃」です。14世紀の半ば、北条時行を破り鎌倉を治めた足利尊氏は、朝廷と手を組んで足利の実権を握ろうとする足利直冬の挙兵に対して京へ進軍するさいに、鎌倉の奥座敷にあたる当地の名社である茅ヶ崎杉山神社へ戦勝祈願を出向いたところ、なんと杉山神社側がこれを拒否。おそらくは朝廷にとっての逆臣足利尊氏にたいする、名家たる忌部氏の面目や意地の問題だったのかも知れません。 が、このことは杉山神社に「凶」とでてしまいました。足利家の怒りをかって神領はことごとく没収。その権威は見る間に地に落ちてしまいました。 これに準じて、他の杉山神社も変節を余儀なくされます。たとえば旧都筑郡は、中山、鴨居、上星川、新羽、吉田、茅ヶ崎、市が尾、谷本など、いまの港北区・緑区・都筑区・青葉区にあたりますが、ここにある杉山神社・杉山社22社の祭神には忌部氏の名残をしめすものは全くありません。神社の祭神が変わることはままあるようですが、ことごとく忌部氏の由来が消え、五十猛命や日本武尊(ヤマトタケルノミコト)などに変わってしまいました。 日本武尊は東国征討の神ということで一般的に受け入れやすいのですが、「五十猛命:イタケルノミコト」には説明が要るでしょう。この神は紀伊和歌山の神であり、紀伊の国を木の国として栄えさせたという「森作りの神」です。素戔嗚尊(スサノオノミコト)の第二子とされ、出雲系の相当に由緒がある神です。そのうえ「杉山」という環境にも融合しやすいので五十猛命になったのでしょうか?もしかしたら武蔵風土記上でただ一社、南多摩郡成瀬村の杉山神社が五十猛命を祀っていたことから、それに準じて他の祭神を取り決めたのかも知れません。  祭神がこうなった時期は明確ではありませんが、だいたい明治初年の神仏分離の頃の話だったようです。流域に広がった杉山神社群はともかく、かってはエリア一帯のご本社的存在だったはずの、茅ヶ崎杉山神社の忌部氏の神までもが、なぜか五十猛命に切り替わってしまいました。
祭神がこうなった時期は明確ではありませんが、だいたい明治初年の神仏分離の頃の話だったようです。流域に広がった杉山神社群はともかく、かってはエリア一帯のご本社的存在だったはずの、茅ヶ崎杉山神社の忌部氏の神までもが、なぜか五十猛命に切り替わってしまいました。そこで何が起こったのかは、今となってはふかい闇の中です。 小生が訪れたとき、本社にあたる茅ヶ崎杉山神社の質素な今のたたずまいからは、かって式内社(延喜式にも取り上げられている社格の高い神社)であったという名残は想像できませんでした。とはいえ1300年余りの風雪をくぐった社からは、その時間の重みが醸し出すような清浄な空気が感じ取られました。 杉山神社はおそらく鶴見川流域をめぐる様々な人々の生き様を見続けてきたのでしょう。 |