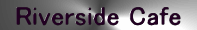 …稲荷民俗譚 …稲荷民俗譚 |

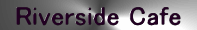 …稲荷民俗譚 …稲荷民俗譚 |

最近よく行く多摩川の河原にお稲荷さんがあります。宿河原堰のそばにあるので川の守り神として祀っているのかもしれません。こうしてみると、身の回りには実に多くのお稲荷さんがあることに気がつきました。

そういえば勤め先のそばにもあって、ときどき自己嫌悪するときに行ってみたりもするのですが、かなり歴史があって由緒がある社だと人から聞いたことがあります。
また、家のそばにもちょっとしたのが二社ぐらいあって、節分祭や七五三のときには賑わいをみせております。どれも結構生活の中にとけ込んで存在しているという感じです。 キツネと関係があることは分かっているつもりでしたが、そもそも「お稲荷さん」とはいったい何じゃろうということで、しろうとなりに調べてみることにしました。考えてみれば学校でお稲荷さんの意味をきちんと教えてくれる教師はいませんでした。当時はいまほど日教組も強くはなかったにも拘わらず、教えてもらわなかったということから、おそらく教科書にも書いていなかったのでしょう。 たしかに戦中の教科書は良くはありませんでしたが、だからといって日本古来の民俗史にあたるような供述まで法度とするのはいかがなものでしょうか? だいたい外国の文句を気にするあまり、自国の教科書を書き換える国はおそらく世界中探しても見あたりません。どうも日本という国は中庸ということを理解せずに、フラフラと極端に走るきらいがあります。まあ、これも民度が低いといってしまえばそれまでですが。 さて脱線してしまいましたが「お稲荷さん」の総元締めともいわれる「伏見稲荷大社」のことから入っていきたいと思います。 伏見稲荷の縁起については諸説はあるものの、そのなかから代表的なものをあげてみましょう。その昔、秦氏という帰化系の名族が富に奢ってしまいました。食べ物である餅を的として弓を射るという酔狂をおこなったところ、餅は白い鳥に化して飛び去り山の峰に留まった。 そしてそこには、たいそう稲が実ったという。ここにその行いの非を詫びて社を祀り、そこを「イナリ」と呼んだという話。 どうも餅が変化した白い鳥は「稲魂:いなだま」を意味しており、ここの神霊はすなわち「穀霊」であるということを示しているそうです。「稲荷」は「稲成り」という説ですので、五穀豊穣をつかさどる神さまとして位置づけられているようです。 伏見稲荷は、古くは稲荷山の三峰に三社(上社・中社・下社)祀られていて、古い文献には祭神については本社となる中社が穀神ウカノミタマで、上社が地主神サルダヒコ、下社は水神オオミヤノメとなっております。まさに地と水とそして穀物ということを表しているわけです。(その後二摂社が加わり五社になった) やがて稲荷信仰は仏教的な伝承を加えたり、山神信仰とも合体し密教化していったりして理屈っぽくなっていくわけですが、根っこは上にあげたように原始的・民俗的な穀物信仰だといえるようです。 ところが世間では、穀神というよりも「稲荷=キツネの神様」という理解(=誤解)のほうが一般的です。たとえば、お稲荷さんの元締めにあたる伏見稲荷大社にも、玉をくわえたキツネの像がたくさんありますので、そう感じてしまうのは仕方のないことでしょう。 
さて、このようなキツネ信仰の原点はどのようなところにあるのでしょうか?
どうやらキツネとお稲荷さんの合体は、もう少しあとにおこなわれたようです。というのは、伏見稲荷が出てくる古い文献には「キツネ」の記述は全くなく、ようやく平安時代からポツポツとキツネの記述がでてくることからも伺い知れます。 実はキツネと稲作を結びつける要素はずいぶん古くからありました。ネコのいなかった時代には、田畑を荒らすネズミやモグラのたぐいを仕留めるのは専らキツネでした。キツネは肉食獣なので田畑を荒らさない上、害中となる小動物をやっつける。ときどきは鶏などがやられてしまうものの、一般的に農業をやる人にとっては、まさに益獣だったわけです。 キツネの棲息域は村落と接していて、その住処となる「狐塚」「狐穴」などが村はずれに散在しておりました。村の外周は田畑で、その先にはうっそうとした森があり、なかには古墳などがあったといいます。キツネにとって古墳は格好の隠れ家、ここにも狐穴をあけて出入りしていたことが想像されます。人と森の境界に棲み、先人の霊魂が宿る古墳にも出入りをしているキツネの姿を見て、村人がある種の霊性を感じたとしても不思議ではないでしょう。 キツネの古語は「ケツネ」というようです。これは「ケ(食)ツ(の)ネ(根元)」という語源を有していて、ケツネには食物霊として位置づけがあるようです。 食物とは木の実、根の実(イモ類)はおろか魚鳥獣肉まで指しているそうで、いうなれば全ての食物に当てはまります。そしてこの民俗信仰は、いうなれば原始宗教的な色彩もあって、初めに紹介をした「稲成り」を稲荷とする穀物霊起源説よりずっと古くからあったとされております。 たとえばある山里では、師走の時分に山の方からキツネの鳴き声が聞こえてくるときは、翌年は縁起がいいとか、近畿中国地方の村では寒中の野山の狐塚などに、小豆飯や油揚げ(キツネは肉食なので、これも不可思議な話)を置いて稲の豊穣を祈るという俗信があるようです。 また、東北の漁村の中には狐の鳴き方で漁の多い少ないを占うという伝承が残っております。「コンゴ」となくと大漁、「グワング」となくと不漁、「カインカイン」では不思議なことが起こり、「コンコン」となくと慶事があると伝えられているようです。古来よりキツネは人と自然をむすびつける役割を果たしていたようです。
このように、今のお稲荷さんの要素である「イナリ」と「キツネ」には、どうも異なるルーツがあったようです。それでは、これらが合体するようになった背景は何だったのでしょう?
これもいろいろと説があるようで、網羅するときりがないので、その中からもっとも現実的な一つをご紹介しますと、伏見稲荷の本社の祭神ウカノミタマに仕えていた斉女が神格化し、下社の女神である水の神オオミヤノメとなったとされておりますが、どうもその社の付近に野狐が棲息していたのではなかったのかと想像されます。当時キツネは人里にもっとも近いエリアに棲息しておりましたので、稲荷山の社まわりなどは格好の住処だったのではなかったのでしょうか。 このように、正式にはキツネが神様そのものではなく、神の使者としての役割を果たしていたとされておりますが、いずれも根元は「それぞれの土地の精霊としてのお稲荷さま」と「精霊の使いとしてのキツネ」というようなところに、結局は行き着くのではないかと思います。 
冒頭にご紹介いたしました多摩川宿河原堰のそばのお稲荷さんについても同じことが言えるのかも知れません。歴史をひもとくと、この付近は大昔から水害で悩まされ続けてきたところです。人々はときとして大暴れする川の神への畏怖心から、多摩川とそしてその土地の鎮守として、社を祀ったことが始まりなのでしょう。
最後に、いくつかの土地とお稲荷さんの関係を示す、興味深い話をご紹介させていただき、この章を閉めさせていただきます。皆様も、どこかの釣り場でお稲荷さんの小祠を見つけるようなことがあるかも知れません。そっと手を合わせてくだされば、もしかしたらキツネの精霊が、油揚げならぬお魚を差し出してくれるかも知れません。 |