小生の場合、海外旅行にいくと、やっぱり「魚や釣りに関連した行動」をとりたくなります。行った場所で、そこそこの釣りが出来そうならば「パックロッド」は必ず持参したいと思いますし、たくさん魚が見られればスノーケリング道具も持って行きます。ところが、シンガポールの場合、インターネットや本で調べてみると、オフショアならまだしも、陸からの釣りではせいぜいキスやイシモチの類しか釣れないそうです。船で沖に行くほど時間が取れるわけではないので、タックルの持参は止めてしまいました。さらにスノーケルは話になりません(沖合はタンカーや貨物船銀座、ビーチには重油ボールが流れてくるようなところですから…)。
でも「魚や釣りに関連する行動」というのは、それらだけではありません。シンガポールには釣具店があるので、そこで珍しいものを探してみようという気持ちはありました。釣具店はアラブ人街にあるという話を聞いていたので、二日目に早速出かけてみました。多民族国家であるシンガポールではマレー系の人がイスラムであり、アラブ人街にはイスラム教モスクやサリーなどの布地、そして絨毯などの店が立ち並んでおります。どれも価格は安く、しかも交渉次第でディスカウントが可能です。家族がそちらを見ているあいだに、釣具屋を発見。せまいエリアには、なんと三軒もの店がありました。
狙っていたペンのスピニングリールは、価格は日本より安いものの、お目当ての小型モデルがなく断念。そのかわりに、今は絶版品となっている大森製作所のダイヤモンドリールを発見しました。もっともトラディショナルなインスプールモデルではありませんでしたが、思わず購入してしまいました。おそらく何年間も棚に眠っていたものなのでしょう。
ターボミニSSとかいうチタン製ということなので、最後期のモデルでしょう。スピナーフィッシングには最適です。今もっているアブ44Xが調子悪い(スプールが外れない)のと、スピナー釣にはややデカイということで代替機を探していたわけです。92S$を値切って80s$にしてもらい購入しましたが、物好きな小生が買わないと、あと数年間はまた棚で埃をかぶっていたはずです。
その他ではアブのクローズドフェイススピニングやカーディナルの見たこともないリアドラグモデルが置いてあって、食指はけっこう動いたのですが、衝動を抑えて、ここで買うのは控えました。アンバサダーのクラシックモデルはもう一台欲しいと考えていたのですが、値段が320s$でしたので、日本で買ってもあんまり差がないような感じでした。ただ一つの店では1600CIARが260s$でした(値切り前)ので、これはお買い得だったかも知れません。
2004年夏
SARSや何やかやで伸びてしまい、二年ぶりの訪問となったシンガポール。会議が終わって少し時間が出来たので、アラブ人街に出かけて釣具屋を覗いてみました。今回の先ずお目当ては、前回買わなかったABU1044。ところが「数ヶ月前に日本人のバイヤーがやってきて根こそぎ買っていったよ」ということでソルドアウト。いや〜残念なことをしました。
他にもミッチェルやアブガルシアの面白そうな中小型スピニングリール、そして今は無き大森製作所の遺品リールなどがありましたが、最近、ウナギのブッコミ釣りなどストロングスタイルの釣りが増えているので、今回は少し大きめの奴ということで、ペンの4500SSを購入。無骨ですが、構造がシンプル且つ頑丈なのでヒラスズキの磯ルアー釣りによく使われているリールです。米国ではもっと安いのですが、値切って159S$でしたので、まあ国内よりはお得でした。今まではルアー用を工面してましたが、これでブッコミのタックルは揃いました。
ハワイに限らずアメリカでは「釣り具屋」というのはあんまり見かけません。だいたい、スーパーやスポーツショップの一角にコーナーを抱えております。ハワイ島ではKマートのなかに釣り具コーナーがありました。日本製が席巻してますが、やぱり地元だけあってペンリールの品揃えは立派です。笑えるのは仰々しく箱に入っているのではなく、コンビニオニギリのようなプラのちゃちいケースに入っております。ペンリールの内外価格差が分からなかったので、初めてのハワイ行では買わずに終りました。
帰国してからJ屋やS水でペンリールの価格を見てみたらビックリ。日本との価格差が、けっこう激しくありました。ハワイでの価格は日本の6割ぐらいでした。がっくしでした。ペンリールを買わなかったことを、そのあと多いに後悔しました。
そんなわけで、二回目のハワイ行(オアフ)では「ペンリールの調達」というのが、大きな命題となりました。オアフはドライブで田舎のビーチばかり行っておりましたので、なかなかショッピングエリアに行くようなチャンスはなかったのですが、有名な「ワードウェアハウス」のそばに、たまたまあったスポーツ用品スーパー(スポーツ・オーソリティ)に、小型スピニングリールの「SS4300」が置いてあったので買ってしまいました。67ドルですから、けっこうお買得ではないでしょうか?
さらに見てみると、中型ベイトリールの「ビーチマスター」が41ドルでした。当面は使うようなシチュエーションにはありませんが、将来ストロングスタイルのコイ釣りをするときに使えそうな予感がしましたので、これも思わず手が出てしまいました(どっちもディスプレイ品で、ストックもありませんでしたので、マネージャーと交渉して一割値切りました…)。「ビーチマスター」というのは、今は日本の釣具屋の店頭では、ほとんど見かけないような普及型のベイトリールです。これには想い出があって、小生がまだ中学生のころ、釣友がこれを買ったのをうらやましく思っていたやつです。
「どうしてペンリールがいいんだ?」と聞かれても、明快に答えられるものでもないのですが、云えるのは「頑丈なこと」と「モデルチェンジをしないこと」の二つです。ビーチマスターなどは30年以上続いているモデルです。この二点は「ツール」としては大切な要素だと小生は信じております。昨今は適度な品質で、本質的でないモデルチェンジを頻発させるような、これとは全く逆行するような行為が当り前になっております。
ひとかどの経営者とされている人が、「程々の品質で目新しいものを安く作る、これが企業の力なり」などと吹聴するような空気に、ニッポンのモノづくりの将来を危惧せざるを得ません。たかがリールと言う人もあるかも知れませんが「変わらないことに価値がある」とするペンリールの姿勢には多いに共感されます。(でも、むやみに高価格化を志向する日本代理店の姿勢には賛同しかねますが…)
いまや市場がグローバル化しつつあるということで、「内外価格差」というものが無くなってしまったと勘違いしている人も多いようですが、実態は効率の悪い国内商流の結果、まだまだ多くのもので、大きな内外価格差があるようです。釣り具にもそれが云えます。これらが払拭しない限り、ニッポン人の海外買物熱は冷めることはないでしょう。そして小生も、またいつか釣り具あさりに出かけるような気がします(笑)。
このページは過去の旅行記からテーマを選んで再編集したものです。
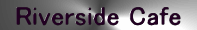 …海外釣具ショップ行脚
…海外釣具ショップ行脚
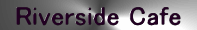 …海外釣具ショップ行脚
…海外釣具ショップ行脚