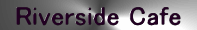 …沖縄行脚備忘録 …沖縄行脚備忘録 |

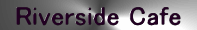 …沖縄行脚備忘録 …沖縄行脚備忘録 |

いつからか忘れてしまいましたが、小生のなかで「島旅」への憧憬が、年々日増しに強まってきました。ここでいう「島」というのは、どうも単純な地理的な意味合いだけでなく、もっと観念的な位置づけをもっているようです。
辞書には地理的な意味合いの「海中の小さな陸地」とだけしか記載されていませんが、文化論的には多様な意味合いがあります。「島」とは「シマ」であり、ある縄張りを意味し、そのことは、様々の局面での外界との分断が前提になっているようです。 個人的には「結界」という言葉が好きで良く使ったりしています。つまり、島というのはある種の結界を意味していて、一つの異世界を形成していると捉えています。旅人はこの結界の中に身をおくことで、その外側からの様々な干渉を逃れ、自分の日々のありようをリセットしようとしているのではないのでしょうか。 結界のなかにも、社会が形成されて人々の営みが日々行なわれているわけですが、それが結界外からの侵入者に対して攻撃的、あるいは排他的であったりすると、その「シマ」は旅人にとっては決して居心地の良いものではありません。 実際、二度と行きたくないような島もありますが、不思議と沖縄の島々には、こう云った空気は少ないような気がします。これは沖縄の人たちの、あまり細かいことにこだわらない気質が大いに影響しているのではないかと思っています。 まだまだ沖縄フリークというには行脚数は少ないのですが、島それぞれ、微妙な違いがあって非常に興味をそそられます。これから先も機会があれば、また沖縄離島行脚を組んでいくつもりですが、そうこうしていくうちに始めのほうを忘れてしまいそうなので、ここにエッセンスを備忘録的に纏めてみようと立ち上げました。まあ、はたから見ると既にご存知の内容かもしれませんが、宜しくお願い申し上げます。
沖縄を語るときに、小生としては、何はさておき、ここ西表島を始めに取り上げるべきでしょう。それは、初めて出掛けたのが西表島ということ以上に、この島のもつ雰囲気が、沖縄諸島の中でもとりわけ特異だからです。
沖縄諸島には大きく、険しい山のあるギザギザ島(大陸棚の隆起)と、丸くて平らな島々(隆起サンゴ礁)に分けることが出来ますが、西表島はまさしく前者の代表格です。 険しい山と、奥深いジャングル、そして忘れてはならないのは沖縄でも指折りの河川と、その河口に広がるマングローブ林。このワイルドさは、やはり西表島がピカイチです。火山島という違いはありますが、ハワイ諸島のカウアイ島に近い存在かも知れません。 周囲130キロもある西表島は、じつは沖縄本島に続いて琉球諸島のなかで大きな島なのですが、その地形と過酷な自然環境から、多くの土地は未開のままで今日に至っております。そのような豊かな自然に囲まれているため、イリオモテヤマネコをはじめ、貴重な生物たちの宝庫にもなっています。 泥炭層を含む大陸棚の隆起によって発生した島ですので、石炭層が島のあちこちの地表に点在していたます。そのため19世紀終わりから20世紀初頭(1940年頃)まで、多くの炭鉱労働者によって炭鉱が営まれておりました。一時期は労働者数千人にもなって、繁華街や学校などがあったそうです。 そのイメージは長崎の軍艦島(端島)のようなものを想像しましたが、実態はもっと更に過酷で厳しいものであったそうです。水の多い西表島はマラリア蚊の巣窟でもあり、炭鉱労働者から戦時中の強制移住者に至るまで、大勢の人間がマラリア病禍に倒れてまいりました。このように、西表島には暗い側面が近年まで色濃く残っていたのです。 今では表面的なエコツアーばかりの西表島ですが、なかには炭鉱ツアーなどもありますので、硬派の旅人はこれに参加することをお勧めします。 さて、小生的には、豊かな魚類相で、マングローブや原生林のなかのリバーフィッシングを志向していたのですが、初回は家族旅行、二回目は五十肩痛で、いずれも満足に出来ずにおります。ここの河川は魚影は濃く、浦内川などは、上流の遊覧ボート発着所(かなり渓流的な様相)でも、尺上のチヌがあまた泳いでおります。バイオワーム、ワームベイト、スピナー、プラグなどなど駆使しましたが見向きもせずBOZでした。このような潮汐の激しい河川の場合、時合さえピッタリ合えば喰いが立つはずですので、粘れば良かったのですが、残念ながら20〜30分程度で撤収の憂き目にあってしまいました。 東側の仲間川には、二回目の行脚で行きました。雨後ということで濁ってはおりましたが、河口域には魚影もたくさん確認され、いまにも釣れそうな感じでしたが、残念ながらここもBOZに終わってしまいました。また、西表島温泉の脇を流れている、細い渓流にも尺級の魚がたくさん確認できました。こう云った感じですが、腰をすえて攻めれば、西表のリバーフィッシングはかなり期待できそうです。近い将来、またチャンスがあれば、先ずは浦内川を攻めてみたいと思います(ライトタックル・ルアーのツアーもある)。 初回の行脚では、例によってカヌーと山登り(ピナイサーラ滝上)ツアーに家族ともども出掛けました。滝つぼにいるという巨大オオウナギの確認をしようと、潜ったりもしましたが、やはりというか、その姿は確認することが出来ませんでした。とにかく水はきれいで冷たく、潜っていると、はるか南の島にいることを忘れてしまうほどでした。(あとになって、霊感の強い人から 「あそこは聖地だから、むやみに立ち入ったりすることは止めるべきだ」と云われましたが後の祭り。旅から帰って、しばらくは面倒ごとばかりでした。) 西表島に限らず、沖縄ではこういった場所が点在しておりますので要注意です。
石垣島は八重山の中心なので、いつも通りがかりだったのですが、たまにはきちんと巡ってみようと、一日がかりで島内をドライブしてみました(五十肩だったので殆ど片手運転!超危険!)。西表ほどではないのですが、山があるので、そこそこの河川もあります。河口部にはちょっとしたマングローブもあって、スピナーやエサ釣りをやってみましたが、ここでも時合が悪く、スカスカのBOZ。そんわけで、石垣島の魚釣りには全く良い印象はありません
とはいえ石垣島の離島桟橋周辺の雰囲気は大好きです。周辺にたくさんある離島に宿泊するのも手ですが、どこの島にも色があります。自分が気に入る島を早く見つけ出すために、始めは石垣島をベースにして、あちこちの島々を日帰りで行脚するという方法をお勧めいたします。そのうちにお気に入りの島を見つけると思います。
先ず始めに感じたのは、沖縄本島、石垣島とは宮古島は「何か違う」という印象でした。地理的には本島→宮古→石垣という関係ですから、本島の影響が石垣島以上に強いはずなのですが、個人的には本島−石垣間の違いよりも、本島−宮古間の違いのほうがより大きいという印象です。
石垣市内はリトル那覇という感じですが、宮古島の市街、平良のイメージは異質です。よく言うと、より都会的、悪く言うと、沖縄らしさが薄いという感じがしました。もちろん、こういった印象は個人的なものなので、「それは間違っている」とか云われてもどうしようもありません。 こう書くと「お前は宮古島は嫌いなのか」と思われるかも知れませんが、そうではありません。宮古島にも非常に惹かれるものがあります。要は、石垣島の魅力と宮古島の魅力は、けっこう違うということです。サンゴ礁は石垣島が素晴らしいですが、宮古島の砂浜の美しさには息を呑むばかりです。リバー系では、宮古島にも小川程度の小河川があるのですが、あちこちチェックした限りでは、もとより水量も少ないうえ、石灰岩ということで水がどんどん浸み込んでしまい、河口付近では殆ど干上がってしまっていたりします。マングローブ林も一部にありますが、雑っ魚釣りではあまり期待できそうもないようです。 宮古島の最大の魅力は、島内のあちこちにある聖地です。御嶽とか石庭とか巨木とか、いろいろな場所で、地から湧き出るパワーを感じました。これほど力を感じる島は初めてです。人によって癒し方はいろいろありますが、多少なりとも感性の強い方なら、この島への訪問を強くお勧めします。何といっても北米のインディアンがわざわざ大海を越えて、訪ねて来るほどの島です。
ここは石垣からの日帰りツアーで出掛けた場所です。小さい島なのですが、高低差がかなりあって(とはいえ百m)、島内のチャリンコ移動は結構難儀します。海岸線も入り組んでいて、マングローブ林から岩場、そして静かな砂浜とバラエティに富んだ島ですので、滞在してもそれなりに楽しめるでしょう。大きなリゾートも建っていますので、ひなびた離島ということにはなりませんが、メチャ俗されてもおりません。個人的にはけっこう気に入っている島です。
今回の小浜行脚で失敗したのはガサガサ道具を持っていかなかったこと。小浜島には水田もあるのですが、その周囲に小さな細流があって、なにやら小魚がたくさんおります。おそらくはグッピーの類でしょうが、これをぜひ確認したかったのです。そんなわけで、足腰がまだ丈夫な間にもう一度出掛けてガサ入れをしたいと思っています。 また、この島には沖縄固有の赤土畑がたくさん見られたことです。じつは、この琉球赤土、拙宅のリビング壁に塗りたくっているのです。ゼイゼイと坂道を登ったところで、赤土の広がる畑が視界に広がっていました。疲れを忘れて、思わず感動をおぼえたものでした。畑や田んぼに囲まれると、なぜか妙に心が落ち着くのは、やはり小生のDNAのなかに、それを感じる何かがあるのでしょう。
石垣島からの日帰り行脚で、もっとも期待と現実のギャップが大きかったのが黒島です。人からは「あそこに行っても牛しかいないよ」と言われましたが、厩舎に入っていたのか、溢れるような牛の歓迎を受けたという感じもありません。そこそこに居ましたが、どこを見ても牛、牛、牛という感じではなかったです。要は驚くほどの牛は見なかったということになります。
日本の道百選にも選ばれた通りも、つまらない田舎の舗装道路になっていましたし、いくつかの観光施設もほとんど感じるものは無し。たまたま出掛けた日が強風だったため、あまり居心地が良くなかったのかも知れませんが、名物の牛が期待外れだったので、結果的にがっかりの島でした。(泊まらなくて本当に良かった)
竹富島は、正直言って、石垣から船で10分の観光名所だったので、行くことにはあまり魅力を感じておりませんでしたが、ここはいい意味で外れました。予想外に気に入ったからです。
町並みがきれいということだけでなく、小生が驚いたのは御嶽のパワーです。この島には意外と多くの御嶽があるのですが、なかでもパワーを強く感じたのが世持御嶽です。ここは竹富で有名な種子取祭を行なう広場に近い御嶽で、鳥居もあるし、立派な石碑もあり、情趣的にはマイルドな感じなのですが、そこの場所から何かを感じたので、鳥居の前に立ってみると、風の無い日にも関わらず、ビュンとつむじ風が舞い、祠の中からかなりの力を感じました。 しばらく(20分ほど)鳥居の前にボケッと立っておりましたが、何かに包まれているようで、非常に心地よいひと時でした。この島には、他にもいくつかの御嶽やパワースポットがありましたが、小生自身が感じたのはここだけです。 石垣島からさほど遠くないので、石垣行脚の折にはまた訪ねてみようかと思います。
久高島は、観光目的の他の島と区別して考えねばなりません。ここはまさしく聖地だからです。宮古の大神島と同じく、「カミ」がおわす領域なので、本来は用もないのにノコノコ出掛けていくような場所ではありません。
初めての沖縄行脚でしたので、そんなことつゆ知らずに久高島をあちこち巡り回ってしまいましたが、さすがに狭い島内にあまた有る御嶽には、なみなみならぬ何かを感じてしまい、畏れを感じて奥には入り込みませんでした。(それでも帰京後にひどい目に遭いました) 島の裏側では、本島のツアーか何かで山盛りのマリンレジャー客がクルーザーで来て、賑やかに楽しんでおりましたが、神聖なる島を汚して、彼等も決してロクな事態になっていないはずです。
世間一般には、沖縄本島についての情報量は、離島のそれを遥かに上回るものですが、翻って小生自身の知見は、沖縄本島については、ほんの端っこしか舐めていない状況です。そんなわけで、小生のコメントはどうしようもなく瑣末なものですので、ここで多くを取り上げることは意味がありません。
せいぜい国際通り周辺だけと首里城近辺しか巡っておりませんので、余計なコメントは控えますが、一つ驚いたことがあります。たまたま県立博物館目当てで行った新都心周辺には、本当にビックリしました。街並にまったく沖縄色が見られなかったからです。目隠しされてここで降ろされても、おそらく東京郊外の千葉か多摩のニュータウンかどこかと勘違いするはずです。 普段と同じ店に入って、普段と同じ食事をして、そして普段と同じ買い物をするという場合にはピッタリのエリアですが、個人的には何もわざわざ沖縄まで出掛けて、そんなことはしたくはありません。この一帯はツーリスト相手ではないでしょうが、実につまらない空間が出来たものです。 本島で関心があるのは、やはり北部の山原(やんばる)地方です。釣竿とタモ網を手に、いつかは巡ってみようと思いますので、そのときは面白いレポートができるかも知れません。 いまのところはこんな感じです。沖縄にはこれから幾度も行きそうな予感がしますので、その都度追記していきたいと思います。 This page is edited by Zaurus。 |

 |