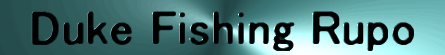 |

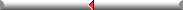
| 2005-12-31(土) | 二ヶ領用水・多摩川野池 | |
| 10:30〜12:00 | 晴れ | コウライモロコ、モツゴ |
|
カーボン硬調2.9m、ライン1.0号、ハリス0.3号、 玉ウキ、タナゴ新半月、グルテン、 | ||
|
大晦日、本当は魚釣りどころではないのだろうが、カラッとした冬晴れにさそわれ、正月用品の買物がてら、小継竿を持参して近所の二ヶ領用水へ。外に出るとやはりかなり寒いが、風を避ければ楽しめるはずと、いつもジモティが集まっているポイントに行く。中河原取水堰からすぐ、三沢川を潜る手前の淵である。
いつも4〜5人いるのだが、今日はさすがに釣り人はゼロ。川筋は風の通り道になるのか意外と風が強い。グルテン餌を付けて(というより針先に引っかけて)。藻穴に仕掛けを流しこむが、一ヶ月前にあれほどあったアタリが全くない。ここは駄目だとすぐに釣り場移動。冬の雑っ魚釣りは一ヶ所にこだわると撃沈す羽目になる。さっさと見切りをつけて次のポイントに移動すべきである。 多摩川河原に行くと、犬の散歩している人、薪ストーブの薪あつめをしているオジサンなどは居るが、さすがに大晦日なのだろう、いつも見かけるボケッと川を見ている人は見あたらない。まあそれが正常なところだろう。少しばかり安心した。ちなみに釣り人は常連風の幾人かが静かに糸を垂れている。 小生の方は川筋ではなく野池にいく。寒い時期の雑っ魚は、本流筋テトラ穴か野池が一番だが、テトラ穴はあいにく対岸なのでパス。野池は案の定、雑っ魚の活性は悪くない。一投目からほぼ入れ掛かりでモツゴ、モロコがあがってくる。…が、なぜかタモロコではなくコウライモロコ。そういえば冬場の野池はコウライモロコが多い。冷水に強い種なのかも知れない。この時期なら酒の肴として唐揚げにしてもかなりいけるが、さすがに暮れに仕事は増やしたくないので、すべてリリースした(一部間違えて、水辺に張った氷のうえに放り投げてしまい、サギのエサになってしまった)。 何はともあれ、今年一年が終わった。めぼしいものは何もなかったが、まあこんな年もあるだろう。 |
||
| 2005-11-13(日) | 二ヶ領用水 | |
| 08:00〜09:00 | 晴れ | オイカワ、モロコ、モツゴ |
|
カーボン硬調2.9m、ライン1.0号、ハリス0.3号、 玉ウキ、タナゴ新半月、グルテン、 | ||
|
時間が少々あったので雑っ魚狙いで再び二ヶ領用水に出向く。気になったので前に行けなかった学校そばの合流点に行ってみる。今日は先行者は無し。用水の中ほどにある石の回りが洗掘されていて、そこからのカケアガリがポイント。ここには小生が放流したウナ君も数匹いるはず?の二ヶ領切っての好ポイント。
今日もグルテン餌。仕掛けを流しこむとオイカワがポツポツあがる。サイズはどうも前回の場所のほうがよさそうだ。あと、ここのポイントの弱点は鯉がやたらに多いこと。近寄ってくるたびに雑っ魚釣りは中断となる。鯉払いに気を取られていたら、手元のグルテン玉が滑り落ちてボチャン。急いで引き上げるがブニャブニャでもう使えなくなっていた(T_T)。 気を取り直して再度グルテンを作っていると、どこからかオヤヂ登場。づかづか小生の隣に入り釣りを始めた。雑っ魚釣りなのでまあ目くじら立てる話ではないが、このオヤヂ、風上に陣取り、咥えタバコで釣りをしているからこちらはたまらない。折角の朝の澄んだ空気が台無しである。何故か魚のほうも、モツゴ主体になってきてしまったので、そそくさと撤収。 |
||
| 2005-11-12(土) | 二ヶ領用水 | |
| 14:00〜15:00 | 晴れ | 小ベラ、オイカワ、モロコ |
|
カーボン硬調2.9m、ライン1.0号、ハリス0.3号、 玉ウキ、タナゴ新半月→ハエスレ2.5号、グルテン、 | ||
|
久々の本家雑っ魚釣りということで、ポイントも渋く『二ヶ領用水』にする。秋も深まったので深場とのカケアガリがポイントとなろうが、困ったことにこの用水路、深場もトロ場も非常に少ない。多少深くとも、タマウキがビュンビュンと流れていくようなポイントばかりで、辛気臭い雑っ魚の浮木釣りを楽しむポイントが限られている。 一つは学校そばの合流点だが、あいにく先行のオヤヂが入っていた。二人は入れなくもないが面倒だ。仕方がないので浄水機場のトロ場に行くことにした。ここもオヤヂたちのサロンと化しているので、あまり気が進まないところだが、端のほうに釣り座があったので、そちらに入れさせてもらう。ここは藻が繁茂していて、その切れ目や、ところどころに置いてある飾り岩の周辺が狙い場。 グルテン餌をつけて、放り込むと一発目からモロコが入れ掛り、しかもすべてコウライモロコである。しばらくは楽しんだが、さすがに飽きてきたのでハエ針にチェンジ。モロコが掛ることはなくなったが、餌取りが増えて釣れなくなった。「新半月に戻そうか」と思案していると、アタリもなくなった。どうやらコイが廻ってきているようだ。 仕掛けをしばらくあげてコイの去るの待ってから再度投入。ウキがピョンと跳ねる、瞬時に竿を立てるといい感じの引き。両型オイカワ君の登場である。グルテン餌なので最初のピクリが勝負、これを逃すとエサが消えている。オイカワに混ざり小ベラもかかってポツポツ。小一時間の釣行にしては効率的だった。 |
||
| 2005-08-18(木) | 西表島 | |
| 18〜19:30 | 晴れ | BOZ |
| テンオーシャン7.6ft+ゼブコ520、ライン16LBS、バイオベイト、 | ||
|
二年越しになるのか、ようやく離島での夏休みを取ることが出来た。場所は沖縄本島からさらに南西に四百キロのところにある日本最南端の八重山群島。ゲートウェイは石垣島だが小生が選んだのは西表島。亜熱帯原生林とマングローブ、そして珊瑚礁に囲まれた豊かな自然の島である。 とはいえ家族旅行がメインであるので、タックルはごくごくライト。いつものパックロッドを一本トランクに放り込んだだけである。6ftシングルのほうが軽量だが、大物がくるとヤバイのでシーバス用の並継四本継のロッドと、壊れてもよさげなゼブコリールの組合せ。これでブッコミ、ミノーイング、スピナー、浮木フカセ、サビキすべてを想定して対応するといういい加減なアプローチである。 ネックの生エサは、以前ハワイで効果があった「バイオベイト」を持参。チューインガムのようなエサだが、いざとなると使える。J屋に行くといままでの白に加えて、赤色バージョンがあったので、これも確保した。 到着初日の夕方、昼は半日、山奥の滝見学トレッキングに出ていたので、宿に戻ったときには若干ばて気味だったが、まだまだ日が高い。さすがに南西諸島で日没もおそく7時過ぎ頃。宿でゴロゴロするのも勿体無いので、近所の砂浜で竿を出す。砂浜はリーフの内側にあり遠浅なので、浜の脇の岩場混じりのポイントから竿をだす。海草天秤とバイオベイトの組合せである。浜には今までお目に掛かったことのない異様な深海魚の死骸が打ち上げられていた。やはり南海だ。 あまりラインは巻いていないので、遠投せずに20mほど先の岩の間に仕掛けを放り込んだ一投目。置き竿で油断をしていた一瞬、竿が飛んでいく。それも2〜3mぐらい吹っ飛んだ。慌てて海に走って入って竿尻をつかんで立ててみたが、時すでに遅し。10lbのハリスが見事に切られていた。 気を取り直して、ハリスを14lbにアップ、再度攻めるがアタリはない。三十分ほど粘ってから、赤色ベイトにチェンジすると、またもや竿先が絞り込まれる。今度はがっちり対応できたが、途中までいなしながら寄せてくると波打ち際で急反転。これもいともあっさりライン(ハリス)ブレイク。残念ながら魚の姿を確認することは出来なかった。 このあとフックアウトが一回あったが、日没コールド。軽く釣れると踏んでいた思惑は外れ、西表島初日は無念のBOZスタートとなった。(T_T) |
||
| 2005-08-19(金) | 西表島 | |
| 10〜11:00、18〜19:00 | 晴れ・スコール | ベラ類多数 |
| テンオーシャン7.6ft+ゼブコ520、ライン16LBS、バイオベイト、 | ||
|
さすがに亜熱帯だけあって天気の変化がすごい。夜になってドピーカンからスコール。それも強風を伴い半端ではない。いったいどうなるのかとヒヤヒヤものだったが、朝にはカラッと晴れていた。これで予定通り二日目AMはスノーケリング中心のプランで、星の砂ビーチへ行くことが出来た。 ここは島北部にあるリーフに囲まれている珊瑚浜で、西表のなかでも最も人が集まるところ。うまく歩けば半ズボンでも沖合100mぐらいまで出て行ける。途中いくつか珊瑚礁に囲まれた水深1〜2mのタイドプール的なところが点在していて、これらがスノーケリングに適している。 小生自身はまずはリーフのサイトフィッシング。こういうエリアだとブッコミは自爆行為なので、飛ばし浮木釣りが一番手頃。タイドプールに放り込むと色とりどりな魚が寄ってきて、浮木がパコパコ。走ったり、沈んだりした頃合に竿を立てると、魚がついてくる。…が、釣れてくるのはベラばかり。どうもタイドプール内での優占種になっているのかも知れない。パン餌フカセも頭をよぎったが、持参しているのは名産サーターアンダギー(沖縄風ドーナッツ)なので魚にくれるには勿体ないので止め。 バイオベイト一本に絞りやってみたが、ここも赤色がいいようだ。ただし竿をあげるタイミングを失すると珊瑚の穴に入ってしまい、簡単にラインブレイク。それにしても、ここ石垣のサンゴ礁のエッジは鋭い。ベラ攻撃は相変わらずで、そのうち口から糸をだしたベラ君が釣れだした(切られた奴)ので、これは駄目だと魚釣りは中止。雨もパラパラ降りだしたので、スノーケリングに専念することにした。 スノーケリングの印象では、想像以上に好印象。ハワイ諸島のタイドプールに比べると、水は明らかに澄んでいる。珊瑚の種類も豊富(たまたまかも知れない)。サンゴ礁の状態も悪くない、泳いでいる魚の種類も多い。敢えて云えば魚がやや小振りである。ダイナミックさには多少欠けるが、可憐な箱庭的な美しさとでも云える。 この日も夕方から、リベンジをはたすべく昨日行った砂浜へ。…が、どうも潮が変わったようで、アタリすら無く、ぐりぐりBOZに終わった。海は難しい。 |
||
| 2005-08-20(土) | 西表島 | |
| 17〜19:00 | 晴れ | コトヒキ |
| テンオーシャン7.6ft+ゼブコ520、ライン16LBS、バイオベイト、 | ||
|
西表三日目はカヌー&トレッキングでかなり疲弊していたが、またもや夕方から浜にでる。日が長いというのは非常にいい。こちらで時間とは無縁の生活をしているが、思ったのは、もしサマータイムを実施したら、日本のGNPは間違いなく上がるだろうということ。人は本来昼行性のはずである。 今回は子供の希望もあって、反対側にある砂浜に行ってみた。ここも大して宿から遠くない。口コミで何も分からぬまま予約した民宿だったが、複数の浜へのアクセスも悪くなく、非常に良いロケーションだった。今日行った浜は河口部に近く、いわゆる星砂はないが非常に粒子の細やかな美しい砂浜、そんなわけで浜遊びにはいい。…が、釣りにはイマサン、 波打ち際をバイオベイトで探ってみても、何の生体反応もない。 根掛かりも魚もないという状況。これは駄目だと魚釣りは中止、こどもと砂遊びすることに。しゃくなので、浜と反対側にあるちょっとしたクリークに仕掛けを放り込み、しばし遊んでいると、竿がなにやら動いている。慌てて戻って竿をあげてみると、ちっこいコトヒキが釣れていた。こちらでの呼び名は「クヮーガナー」。いちおう汽水魚だが、むしろ海水側の魚だ。このクリークは100%淡水と思うが、亜熱帯では海水魚も浸透圧調整が活発になるとかいう話もあった。そんんなわけで、まあこんなところにも旺盛に巣喰っているのだろう。 。 散発的だがコトヒキを何匹か釣ったところで、お腹も空いてきてので納竿。ここ西表では、小物釣りも海よりも川の方が面白そうだ。 |
||
| 2005-08-21(日) | 西表島 | |
| 10〜11:30 | 小雨・曇り | イーブー・コトヒキ |
| テンオーシャン7.6ft+ゼブコ520、ライン16LBS、バイオベイト、スピナ−(Pマーチン・セルタ他) | ||
|
西表のまったりした時間はあっと云う間におしまい。今日は午後から那覇に移動することになってしまった。名残惜しいところだが、外は小雨。家族は「みんさー織(八重山織)」手織工芸体験とかに出掛けてしまったので、小生は竿をもってまた浜へ。…ということはなく、浜の後背地にある原生林のなかのクリークへ行く。昨日の感触でちっぽけな川でも魚が意外と多い気がしたからだ。そう云えばカヌーイングの途中でもかなりの魚を見ている。亜熱帯では本土以上に川が豊かな生態系を維持しているのか。 藪こぎしながらクリークに着いて、今日は先ず浮木釣り。昨日は海草天秤での釣りだったので、釣趣はイマイチだった。少しは繊細に攻めてみよう。…が、やたらに立木やツルやら、川の中には倒木(台風でやられた?)などがあり、なかなか難しい。ようやく、ここぞと思うところに仕掛けを放り込むと、浮木がピュンと沈む。竿を立てるとビンビン震わせて、またもやコトヒキ。やはり西表では淡水魚登録している感じ。 しばらく釣っていると、やはり彼等も学習しているらしくバイオベイトでは反応が無くなる。南の島でもリスク管理はきちんとしているようだ。そこでこちらもメソッドチェンジ、スピナーを出す。マルタ用のパンサーマーチンだ。やや深みになっているところをゆっくり通すと、一発でがつんと来た!これはコトヒキのアタリとは違い重量感がある。慎重に寄せてくると、なんとイーブー※だ。小生としては始めて釣った魚だ。上がってきたときにはハゼのお化けかと一瞬思った。 ※ハゼ科カワアナゴ亜科のタメトモハゼ・ジャノメハゼ・ホシマダラハゼ等の混称 ここからイーブーのまさに連打。2〜3匹釣れると反応がなくなるが、スピナーを変えるとまた何発か釣れると云った具合。感じからするとツ抜けはしたと思うが、途中からカウントし忘れたので数は不明。レストランで待ち合わせた昼飯時間が近づいたので納竿としたが、まだまだ遡行すれば数は出る感じ。次に西表に来る機会があれば、もっと川釣りに照準をあわせて道具立てをしてみたい。 |
||
| 2005-08-23(火) | 沖縄本島・久高島 | |
| 13〜14:00 | 晴れ | BOZ |
| テンオーシャン7.6ft+ゼブコ520、ライン16LBS、バイオベイト | ||
|
沖縄本島では那覇ベースなので観光&買い物モードになってしまった。そのため一日ぐらいは離れ小島に行こうというと、那覇の反対側、知念半島の沖合にある久高島に、路線バスと連絡船を乗り継いで行った(片道一時間半)。ちなみに、この久高島は琉球の国造りの神様が降臨してきたとされている島。いまなお神秘的な祭祀スタイルを踏襲している島である。貸チャリでふらふら回ったが、島のなかあちこちに聖地(御嶽・拝所)が散在していた(男子&俗人禁制)。 海は西表ほどではないが、やはり美しく、そして穏やか。水をみるとソワソワしてしまい、竿を出す。とはいえ珊瑚礁の隆起島なので、岩場はギンギンに尖っている。やわいビーサンなら大怪我をするほどである。根掛かりもハンパじゃなさそうで、日和って飛ばし浮木仕掛けで攻めてみる。…が、残念ながらなにもアタリがない。よくよく考えてみると、それもありなん。ジェットスキーが沖合をバンバン走るは、隣の浜ではマリンレジャー倶楽部の団体がウワッと遊んでいるはと、なかなか賑やかだ。 サンゴ礁の狭間には魚が見え隠れしているが、さすがに沖縄本島の小島、魚の方もスレているのか、小生が持参したバイオベイトには、赤も白も全く反応なし。残念ながら、今年の沖縄・先島行脚はBOZで締めくくることになってしまった。本島には釣り餌屋がたくさんあるので、次回は横着しないで生エサを持参しよう。 |
||

 |