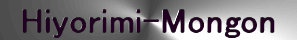 |

|
★本物タックル考 ダイワ精工(40億円)、シマノ(140億円)、リョービ(40億円)これは99年3月期(シマノは決算期が違うため98/11月)の釣具大手各社の業績(経常利益)です。 アジア全国区で不況風が吹き荒れているなかでは健闘しているとは思います。おそらく個人的には実感がわかないのですが、ここ数年は空前の釣りブームだそうで、その恩恵をこうむっていることが、この数字に現れているのでしょう。 ただ会社四季報のコメントにもありましたが、関東のルアーブームは一段落し、今後は成長は鈍化ということですので、そういつまでも拡大基調は見込めないのでしょう。 ただ、いまの釣り具を見ていると機能満載の反面、なにかが足りないような気がしております。それは恐らく、あまりにハードに傾いた設計思想でしょうか。 日本のクルマが欧州で受ける評価と同じですが、出来たモノとしては比類無いバランスなのでしょうが、何故このモノができたのかというスピリットが感じられません。 もちろん、中にはそういう製品もあるのでしょうが、極々わずかなケースなのでしょう。そのためには作る側の確固たる自信と信念がなくてはとうてい無理な話です。 一つのブランドの精神を確固とさせるためには、揺るぎ無いコンテンツの統一性と、マシンとしての熟成期間が、少なくても七〜八年必要と思います。 ところで今のタックルで八年前と同一ブランドのものがどれだけ残り、そのうち、どれだけのものが一貫性あるコンテンツを有しているでしょうか? 浅薄なマーケットの我侭にも動じない設計者の一貫性のあるコンテンツと、膨大なフィールドからのデータのフィードバックを受けて、改良してきたものだけが持つ信頼感。これが本物というものでしょう。 話は違いますが、ドイツ駐在中に日本への土産として良く購入したのがタオル。ドイツ製でファイラー(Feiler)と呼びますが、シュニール織というとても奇麗な織り柄のタオルです。 日本では3000円もするのが、現地では20マルク(1600円)弱で買えるので結構喜ばれました。長年使っても色落ちせず固くもならず、やがて日本でもこのブランドは次第に人気をつけてきて、三越他の百貨店から大量の引合いが出たそうです。 これに対してメーカーは増産せずに、今の設備と熟練者の数から出来得る枚数しか生産をしなかったという話を、又聞きですが知りました。 これと似た話を、スイスの時計会社のケースでも聞きましたが、妙な増産設備投資をしなかったため、当時は相当文句を言われたそうですが、いまでもアジア不況の影響をそれほど受けていないということでした。 おそらく日本の企業の場合、需要が二倍三倍となったときは、大半が工場を新たに建てたり、新鋭の工作機械などを投資して最大限のアウトプットを計るであろう事は容易に想像がつきます。 ところが欧州の伝統的企業は目先の引合いには一喜一憂しません。本物を作っているという自負があるからこそ、自らのスタンスをこちょこちょ変えない強さを持っているようです。 これは400年の資本主義の歴史のなかで培われた,本能的なものなのでしょうか? 景気には必ずサイクルがありますし、消費者の気まぐれは今に始まったものではありません。 只今の時代はメッキがはがされています。本物だけが残っていける時代といわれております。 個人的には釣り具の世界は、まだまだバブル状態であるという感じを持っております。本物というのは贅沢な素材と装飾に飾られるものではなく、しっかりした思想と価格を凌駕する品質に裏打ちされたものであると思っておりますが、それに値するものが少ないことを感じるのは小生だけでしょうか?? |

 |