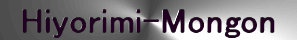 |

|
★多摩川サーモン考 二月ころ多摩川河口でシーバス(セイゴ)の大群が来たという情報がありましたが、これはおそらく上流のサケの稚魚放流と関連していると見ております。 約一万尾と新聞に出ていましたが、これは毎年の恒例行事だそうで、それを狙ってきたのではと思います。聞くところでは隅田川でも似たようなイベントをしているそうですが、リターンという意味合いではかなり期待が薄いのではと思ってしまいます。 まずサケの生態系の南限は外房総の栗山川で、これは寒流(親潮)の影響下の南限という意味があります。たとえ多摩川が奇麗でも回帰する個体はかなり確率は少ないと推察されます。つまりサケの回帰行動で重要なのは河口水温で、河川の汚濁云々は二義的な要素という事です。 すなわち河川環境の改善を趣旨とした場合、サケの放流は東京湾内では、パラメータとしては意味が薄いということが言えます。そういうことで行田市で同様に実施している利根川へのサケ放流運動は生態系に則っていると思います。 多摩川や隅田川に放たれた幾多の稚魚は、よしんば東京湾口にたどりついても、北洋を目差すためには暖流(黒潮)をクロスせねばならず、殆どはここまでで死んでしまうと思われます。イベントの関係者にもこのことを知っている人はいるのでしょうが、それでもなおやり続けるには、きっと何か別の理由があるのでしょう。精神的な啓蒙でしたら、もう少し別の知恵があると思いますが‥ 。要は東京湾の場合、サケ遡上確率と河川汚濁度云々とはほとんど相関が無いという事です。 それでも時々遡上魚が発見される事がありますが、これは河川回帰本能の標準偏差から離れて行動する、特異な固体行動と思っております。これは悠久の地球の歴史のなかで培われた、自らの種の保存に対する、一種の保険的行動で、大規模な気象変化や地殻変動のなかで種を絶やさぬための本能的行為と理解されております。どうやらこれは全ての種のDNA内に埋め込まれているそうです。 そういうことで、ごく特異な固体を除いて、サケが東京湾に標準的に回帰することを期待するのは、ばかげていると言わざるを得ません。まあ東京湾シーバスのベイトを放流しているという事で、小生としては間接的に恩恵を受ける?立場ですので、敢えてこの多摩川の放流イベントに強く異をとなえる気はないのですが‥。 どうせなら、50年代まで多摩川に自然遡上が確認されていましたサクラマスの放流のほうが、本質的な河川浄化啓蒙のためにははるかに意味深いと思います。ただこれはスモルト化(降海型固体化)までケアせざるを得ないため、時間とコストがかかってしまいますが‥ |

 |