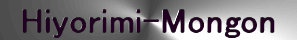 |

|
★タケとロッド考 同じ島国のイギリスが日本と並んで、趣味としての釣りを発展させたことは巷でも知られておりますが、大正時代にハーディ社が出した六角竿の素材が日本の竹であったことは存知でしょうか? 英語で竿はロッド(Rod)といいますが、ロッドとは本来「木の枝」という意味です。つまり木製の棒を始めは釣竿として使い始めた訳です。なぜなら欧米では竹はありませんでしたから。 やがて竹のもつ軽さと柔軟さ、さらには強靭さが釣竿に適していることを欧州の釣り師も発見したわけでありますが、それまでの木材(柔軟性のある奴を工夫していた)を接着して使用していた事にくらべますと、竹素材の導入は彼らにとってかなりのエポックだったのではないでしょうか? 竹をみてバンブー(Bamboo)と呼ぶ外国人は、あまり学のない人で英語でも竹は(Take)、笹は(Sasa)と呼びます。バンブーというのは、広義では竹の仲間ですが、繊維質も大きく異なり、釣竿としては使いものにはなりません。 竹と笹の区別は。成長後に皮が落ちるのをタケ類と呼んで、成長しても皮がついているのをササ類といいます。だから釣竿に使用される竹類(ヤダケ、メダケ、コウヤダケ)は、実はササ類という事になってしまいます。 軽さと強靭さ,弾力性を兼ね揃えた竹竿(選び抜かれた素材を入念に仕上げたもの)は、釣竿の素材としては完璧で、更に竹のもつ強い伝導性と反応性を超える素材は近年のカーボン素材まで出ませんでした。あらためて先人の知恵と自然がうむ素材の芸術性を感じてしまいます。 |

 |