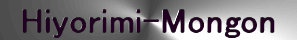 |

|
★高圧線と魚 魚に色彩感覚があるのかどうか、という話は過去も色々なところで論じられてきたものの、誰も自分の目として見たわけではなく正直なところ分かりません。魚によって違うそうですが、赤が反応良いという人もいれば、赤に忌避反応を示すという実験結果もあるようです。 ただ色彩というのはあくまでスペクトル(波長)であって、たまたま人間にとっては、赤より長い波長(赤外線)や、紫より短い波長(紫外線)は見えないわけですが、見えないもの即、色が無いとも言えません。あるスペクトルには特異な反応を示すことが実験では知られてはおりますが、その情報が魚の「目」を通じてだけ入っていると思い込むのは危険でしょう。 メインページの無益風聞雑感エッセイ「シーバスは目利き?」でも一度とりあげましたが、魚の場合、もともと見通しの良くない水中にいるわけで、周囲の状況については複数の器官を通じて、認識を行っているのだと思います。魚の目や耳の働きをする器官として側線がありますが、それとは別にもう一つの感覚器官があるのをご存知でしょうか? 上生体という頭頂にある器官で、波長の短い電磁波を受信する事が出来るようです(無益風聞雑感に画像あり)。側線の感じる水中波動はせいぜい75hzということです。この上生体のアンテナが関与していると思われる例を上げてみましょう。 釣り場に行きますと、運河や河川を高圧線が横切っている光景を見かけると思います。不思議と好ポイントといわれる場所は高圧線の下が多いようです。ご存知の通り高圧線は大量の電磁波を放射しております。人間はこれを認識することができませんが、魚の上生体では何か感じているのでしょう。 平面的でストラクチャも無いような釣り場でも、高圧線の下では何らかの理由で魚が集まるようです。最近読みましたバス釣りの雑誌にも、似た様な記事が出ておりました。ただカーボンロッドを持ち長時間そこに居ることは、優秀な避雷針をもちながら、雷の鳴る荒野を歩くようなものですので、健康面ではマイナスです。滞在時間はほどほどに。 |

 |