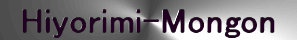 |

|
★水温のウンチク 水温は魚の活性にとり、かなりのウェイトを占めていることを否定する釣り師はいないでしょう。 重要な環境ファクターであります酸素(容存酸素量)も、水温の影響を受けます。冬になって水温が低下すると溶存酸素は最大になります。ただ低水温下の魚は動作もにぶく、摂餌行動もあまり活発ではないので、この水温域では酸素をそれほど必要としないのでしょう。 一方、夏になって水温があがると、摂餌も活発になって、必要酸素の量も増加しますが、溶存酸素量は最低になって、深い湖や池などでは底に無酸素層さえできてしまいます。しかも魚の構造は、水温が高いと血液中に酸素を取込みにくいかたちとなっているので、魚にとっての高水温はかなりの負荷となります。 全ての魚は自身の適水温域をもっておりますが、高水温側のほうが魚には負荷が強いようです。高水温下ではある限界点までは、魚は活発に摂餌しますが、それを超えますと極端に活性は劣り、さらに高くなると死亡してしまいます。 低い温度側では、水温低下とともに次第に食欲は減退しますが、フナの例では4度位まで摂餌いたします。4度は溶存酸素が最大となり水の比重が最大となる温度で、一般の湖沼の底部ではこれよりは温度は下がりません。 スズキの適水温域は15〜18度ですが、23度以上では食餌行動は大きく減退します。ただし下方には比較的適応力があるようで、小生の経験では10度弱でもルアーを追います。福井県水産試験場の低温テストのレポートによると5度以上の水温であれば餌を良く食べるそうです。更に東北大学の臨海実習所の越冬試験では2.5度の最低水温でも大部分が生き延びたそうです。 ちなみにコイの場合は適水温は23〜28度と高めですが、5〜6度でも釣れます。小生の経験では6度でもTOPのフライにかなりの大物がアタックしてきました。ただし固体差はあるようですが‥。シーバスでもコイでも、一発大物は、やはり低水温側のレンジのほうが出るのかもしれません。これから次第に高水温になっていってしまいます。大物狙いはなるべく早目にどうぞ。 |

 |