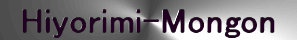 |

|
★多摩川の塩水くさび 朝日新聞神奈川版で連載された、俳優中本賢さんのエッセイ「多摩川ノート」におもしろい記事が出てましたので、ご紹介いたします。 中本氏は趣味高じて、多摩川の汽水域の移動状況を確認するために、わざわざ塩分計を手にカヌーをだして、塩水くさびの干満による移動状況を調査したそうです。 それによると、氏が確認できた多摩川のくさびの先端は、大潮満潮時には多摩川大橋〜ガス橋間まで延び、干潮時はJR東海道線の上流500m付近といういうことだったそうです。 この結果は「満潮時に塩水くさびが丸子堰に突き刺さっている」とした小生の見解とは異なりますが、拙HPでもご紹介のとおり、くさびのベロの先は少しずつ伸びていくという点と、くさびそのものの境界が目視出来るものではなく、ファジーに伸びている点を配慮すれば、もっと先端は上流という気も致します。 とはいえ自ら実地調査した結果という点では、称賛に値するものでしょう。それと干潮時には全ての塩水が下流部に戻らず、川底の凹部に溜まって、そこに海水系の魚がステイするということを実証した氏の見解は重要な示唆を含んでおります。、 干潮時に中流の凹部に溜まることでポイントが絞れるということですので、中流域を狙うシーバスアングラーは、干潮時の水位の低いときでもチャンスがある、ということを忘れないで下さい。 この凹部の開拓が重要ですが、川底のヒントは河川の湾曲や流れを注意深く研究すれば必ず見つかるとおもいます。またドピーカンの日中、干潮時に橋や土手の高いところからの観察でもみつかるかも知れません。 それから干潮時の塩水くさびがJR東海道線近辺という点からもいろいろ分かります。干潮時に次ぎの上げ潮を待って、この近辺にシーバスが待機する可能性が高いということです。干潮ソコリ時やアゲッパナで、鉄橋下流の浅場で大型が来るという情報からも、この近辺での、特に干潮前後での探りは意味あることです。 小生自身は多摩川では振られつづけておりますが、これらの情報を生かして成果を出していきたいと思っております。 |

 |