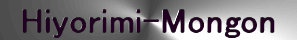 |

|
★日本では生みっぱなし: こういうフレーズではチョット分からないでしょうが、魚の世界の話です。いまや日本の淡水域は密放流や生簀からの流出によって、帰化種と呼ばれる外来魚によってほぼ制覇されつつあるような感じです。 環境破壊や流域開発にともなって河川環境が変わっていると同時に、帰化種の増大によって、生物相そのものも大きく変わってきております。自然の中に定着した外来淡水魚は25種以上おり、純淡水域に生息する淡水魚の六種に一種は既に外来魚です。 これらの帰化種が増えてきている理由は、彼等が日本の在来種に比べて優位種であるためですが、実はその大きなポイントは「子育て」にあります。たとえば「害魚」とされて、環境問題にもなっておりますサンフィッシュ科のブルーギルとブラックバス。 彼等は春から初夏にかけて産卵しますが、その際オスが岸辺に産卵床を作って、メスを迎えいれて産卵したのち、卵や稚魚をほぼ絶食状態で保護しつづけます。この期間はブルーギルで2〜3週間ほどブラックバスで約一ヶ月間にもなります。 日本の湖沼には魚食性の在来種は少なく。卵や稚魚達が食べられる危険性は少ないのですが、彼等は産卵期になると必死で卵に水を送り、稚魚の群れに少しでも近づく多種をおいはらうわけです。 地元の北米では、サンフィッシュ科がカワカマスやウォールアイ等含め四種は居て、どれが強者というわけではなく彼等は日々食うか食われるかという緊張感をもって生活したわけですから、この日本の淡水系はまさにヘブンというわけです。 また食用として日本に持ち込まれたテラピア類のうちナイルテラピアとモザンビークテラピア(カワスズメ)も、メスが卵や孵化した仔魚を口にくわえて保育します。 この習性はマウスブルーダ-といわれておりますが、とても効率がよく、親の口から出て自由に泳ぎ出す頃には8ミリほどにもなって、すぐにも動物プランクトンや藻類などを食することが出来ます。 それから最近は河川改修による産卵場所の減少で激減しておりますが、ライギョ類(カムルチーやタイワンドジョウ)も卵や稚魚を保護する繁殖方法を持っております。 湖沼や河川の岸の水面に水草が茂っているような場所に、雌雄がもんどりうって丸いプールのようなスペースを作って、そこで産卵致します。 孵化まではたった2〜3日で、稚魚の成長も速く、プランクトンを食べつづけて、あっというまに3センチを越えます。その間、雌雄は稚魚の群れの真下に陣取って、稚魚に近づく全てのものを排除する行動を行ないます。 このように外来魚はもともとタフな環境下で生きてきたため、子育てに対してとても手厚い気遣いをいたします。 この結果、生みっぱなしでなにもしない在来種よりも、仔魚や卵の生存率(歩留り)が高くなり、生物相的には優位種となってしまうというわけです。 同じような例では、グッピーやカダヤシは卵胎生であり稚魚を産仔しますし、チョウセンブナは気泡で水面に巣を作って子育てします。 流下卵という寒天質に包まれた大きな卵を生むソウギョやハクレンなどの事例も、子育ての保護行動のひとつかもしれません。 いままでは日本の淡水環境はクローズされていて、天敵も少なく生みっぱなしでも、穏当なコミュニティ(環境)のなかで温もっていれば、それなりに問題はなかったわけですが、魚の世界でも、合法的とはいえないグローバル化の荒波を受けて、在来魚種は駆逐されはじめました。 一方、ヒトの世界に目を向けますと、日本では小学校での「学級崩壊」など、いろいろと子供達に問題が出てきております。紙面では教師の指導力不足云々とか言ってますが、個人的には90%家庭の問題だと確信しております。 「子育て」をキチンとやらないと、種は衰退し滅ぶという冷徹なロジックを肝に念じて、家庭での教育に対して、もっともっと真剣に考えなくてはいけないのかも知れません。 |

 |