
[Back]
| ■2006年6月30日 (金) BKK行脚Ⅲ |
分かっていたとはいえ、やはり体温以上の気温は辛いものがあります(笑)。 でも良かれ悪しかれ、この気候がタイ人のメンタリティを作っていることは間違いがありません。 さて、タイと言えば農業国、しかも世界一のコメ輸出国家です。タイのコメというと、あのタイ米を想像するでしょうが、実はちゃんと日本米も作っているのです。日本からの農業指導や、現地農業関係者の努力の所産です。ところが駐在員の人は「タイで作る日本米はマズイ」とは吐き捨てるように言います。現地で小生の食べた限りでは、コストフォーバリュー(約500円/5kg)は充分あると思います。(そもそも東南アジアの駐在員は贅沢すぎます。日本食にもめったに出会えない欧州辺境に居た身としては、どうしても辛目の採点をしてしまいます。) 殆どの人は忘却のかなたにありますが、かって日本が不作で平成の米騒動が起きたとき、タイ国政府はタイ米の支援を申し出でました。にもかかわらずニッポンは「こんなの食えない」と名目的な輸入の後、なんと廃棄処分をしてしまったのです。繰り返します。タイは我が国とおんなじ稲作の国です。コメはタイ人の誇り、このときのタイ人の悲しみの深さは想像に難くありません。やはりニッポン人は飽食さや他国への無頓着さを自省しなくてはなりません。
|
| ■2006年6月29日 (木) BKK行脚Ⅱ |
バンコクに着きました。暑いですが日本も蒸し暑かったので、インパクトはさほどではありません。 さて今回、道中のトラブルは二件ありました。一つは不覚にもアルコールの飲み過ぎで酩酊してしまったこと。これは体力的に大きくロスです。どうも国際線フライトでは、この手の失敗を過去幾度かしていることを、機内トイレでうなっているとき思い出しました。高々度にいると予想以上にアルコールが回ります。W杯のTV観戦で睡眠不足がたまっていたので、それも一因なのでしょう。基本的にはやはり節制をして、インフライトではアルコール断ちをすべきでした。後悔先に立たず。 もう一つは、怖れていたことですが、メモリーカードエラーが肝心なところで再発してしまったことです。どうもAir-Edge通信カードを使用してからシグマリを一旦リセットしないと、メモリーカードのエラー「ディレクトリが不正です」が出てしまうようです。もちろん、こうなるとメモリーカードは使えなくなってしまいます。自宅の母艦パソコンにはバックアップがあるので大事には至らないのですが、出張中はやはり不便になります。これがシグマリの問題なのかメモリーカードの呼称なのかは分からないのですが、帰国したらカードを替えてみて原因をチェックをしようと思います。 そんなこんなで、旅には何かしらのトラブル、ハプニングがつきものですが、まあこれも「非日常」的な体験の一つなのかも知れません。 |
| ■2006年6月28日 (水) BKK行脚Ⅰ |
本日からまたバンコク行です。 さて我がNRTも化粧がえというか、第一ターミナル南ウィングが今月よりリニューアルオープンしました。W杯で眠くて重い体を引きずってでも、これは早めにチェックを入れておかない手はありません。予定より早いリムジンバス(最近は列車を使わずにこればかり)で空港に着いて探検しました。 第一ターミナルにスターアライアンス系が集結することになりましたので、小生は全日空を使う使わないに限らず、これからの海外行脚の8割方は第一ターミナルになります。そうなると、出発前に使うことの多い土産物屋と銀行/郵便局をちゃんと探さねばなりませんが、行ってみて分かったのは北ウイングと共通のショッピングモールなので、とくに目新しいことはありませんでした。ただ全日空系の土産屋「ANA FESTA」が出国審査前エリアから無くなったのには困りました。いつもそこで決まった土産を調達していたからです。 南ウィングは新しいと思いきや、カウンターだけで大きな変化はありませんでした。でも中央のモールはベンチも多く、マックやローソンなどもあってお手軽に出発前のひとときを過ごせますので、総合点は第二ターミナルより高いでしょう。 |
| ■2006年6月27日 (火) ラジオ文化 |
ついでにもう一話。 最近になってようやく、2011年でTVのアナログ放送が終了する情報が広く認知されるようになってまいりましたが、それと平行してあらたな試みがされ始めています。 アナログTV放送はVHF帯域を使用していますが、アナログTV終了後にこの帯域を他の放送手段に振り向けていこうという動きです。一つはもう有名になっている携帯電話を中心とした1セグ(TV)放送ですが、小生的に関心をもっているのが「デジタルラジオ放送」です。正しくは「地上デジタル音声放送」ですが、このVHF帯域を使っての放送を狙っています。2011年以降放送開始ということになっておりましたが、携帯向け1セグに続いて早めの放送開始が望ましいという意見が多く、早ければ今年中に本放送が始まるようです(現時点でも試験放送中ですが受信機はまだ出ていません)。音質は素晴らしく良いという話なので、これには非常に興味をもっております。 余談ですが、アナログラジオ放送(FM、AM、短波)はテレビとは違い、2011年以降もそのまま残ることになっています。これは災害時などのラジオの有効性が広く認識されているためです。何かをやりながらでも聴ける、お茶の間にズカズカ入り込まない、目も疲れない、もっとラジオに目を向けましょう。 |
| ■2006年6月26日 (月) NHK-FM存続 |
歳とともにTVがうざいと感じるようになってきました。どこかでラジオシフトしようということを考えていたら、どうにもケシカラン記事が目に入りました。 竹中大臣を中心とした政府与党で作る懇談会で、チャンネル削減などNHK改革策を審議していたそうですが、そのなかで何とNHK-FMラジオ削減についても議題に上がっていたそうです。これは辛くも逃れたようですが、ろくすっぽFMラジオなど聞かない政治家がチャンネル削減を考えること事態が異常のような気がしました。 曰く「FMラジオ放送は民間のFM放送や音楽配信サービスが普及し公共放送としての役割はすでに終えた」ということだそうですが、本当にバカです。民謡好きな年寄り、あるいはクラッシクファンが民間放送を聞いたり音楽ダウンロードをするでしょうか? NHKでしか出来ないFM音楽番組は間違いなくあります。衆愚とは云いませんが視聴率に迎合した民間放送が上質な番組をほとんど作っていないことは、彼等はまったく分かっていません。 こうなると意地でも、かってのFMファン復活をせねば気が治まりそうにありません。 |
| ■2006年6月24日 (土) 多段引出し |
まだ人生を振り返るような歳にはなっていないと思っていますが、目先だけしか見ずに生きてきた若い頃とはちがって、これからの軌道を確認するようなことは増えてきました。 生き方としては、一芸に秀でると云うことも良いのですが、一度切りの人生ですので小生的には多芸多才の方が好きです。誰しもそうですが「よりよく生きていきたい」というのが、それぞれの本音でしょう。 そして、豊かな人生を送るためには、いくつもマジになれる世界、つまり「引き出し」は多い方がいいと思います。柱のようなものは必要ですが、それが一本だけで「自分にはこれだけしかない」と突き詰めてしまうと、何かあったときに立ち直れません。 そんなわけで、小生は多段引出し志向とも云えるでしょう。現状で云うと、フィールド行脚(魚釣り・ガサガサ)、温泉銭湯行脚、フロンタ-レ日和見サポーター、そして拙サイトマスターと云うのが四本柱。これにチャリ坊主やカメラ小僧、島旅オヤヂなどの、これから強化していこうとしている引出しを加えると、まあやることばかりで時間がなくなってしまいます。 今のところは使える時間は限りがありますが、やがてそのうちに年相応にヒマヒマになるはずですので、それまで更に引出しを増やしていきたいと思っています(^o^)。 |
| ■2006年6月23日 (金) 少食⇒免疫力 |
先日、久々の人間ドックを受けました。相変わらず耳鳴りは続いていて、困っているのですが、自覚する体調とはうらはらに、検査の結果、数字的なデータは異常がないと言うことで、あっさりと終了。こうしてみると西洋医学の底の浅さを感じずにはいられません。言葉を変えて言うと、医者の話にだけ一喜一憂するのも考え物です。 自覚する、しないに限らず、異質物に対して自分の身体が反応するのが病気だとすると、本質的には第一波を跳ね返す力、つまり「免疫力」というのが重要になるのでしょう。突破されて、懐に攻め入れられてから対策を講じるような、いわゆる対処療法では効果を出すためには、相当のエネルギーもかかってしまいます。 言い古されていることですが、防衛力=免疫力を如何につけていくかということが、健康の要であることは間違いありません。近年、成人の病気で問題になっているのは、いわゆる生活習慣病の類で、これを予防するためには衛生や栄養と言うよりも、日頃の生き方を是正しなくてはいけません。 タバコも吸わない、酒も大して飲まない小生ですが、非常に気をつけねばいけないな、と思っているのが「食習慣」。生来の食い意地のわるさで、ついつい食べ過ぎてしまいます。飽食を戒める言葉は、太古の昔からあって、かのエジプトのピラミッドには「人は食べる量の4分の1で生きている。残りの4分の3は医者が食べている」という碑文が彫られているそうです。日本でも似たようなのがあって「腹八分に病無し、腹十二分に医者足らず」というのがそれです。 免疫力回復のために、辛いのですが少食をしばらく続けてみようと考えています。併せ、ウエスト回りも最近妙に気になってきたので、こっちの効果も期待してやってみます(笑)。 |
| ■2006年6月22日 (木) 雨水Ⅱ |
よく「日本には資源はない」という言われ方をされてしまいますが、この「雨」というのも、本当は資源と言っても良いのでしょう。海の水の淡水化はコストが掛かるものですが、自然の働きは優秀で、蒸発した海の水は、真水となって空に水蒸気の粒として一旦蓄えられます。それが一杯になると雨粒となって地上に供給されるわけです。 つまり日本は、空に馬鹿でかいダムや貯水池を背負っているようなものです。たしかに梅雨はうっとおしいですが、雨水をハザードとしてしか捉えかねない今の考え方は、あまり正しいと云えません。表土はすべてコンクリで覆って、川は極力まっすぐにして、とにかく雨水を出来るだけ速く海に棄ててしまう、というような近年の土木行政には、ややギモンを抱かずにはいられません。 里山や雑木林で保水された雨水は、天然のフィルターを通じて清冽な水がわき出る谷戸を作り、そこには小さいながらも貴重な生態系が出来ます。水田に溜まった雨水は川の水位を安定させ、川の生態系の維持に非常に大きな助けとなります。単なる排水溝となってしまった川には多くの生き物は住めません。雨水はもっともっと大切に扱うべきものです。遙か山の上のダムの水位がありさえすれば、それで良いという話ではありません。もっと私たちは考えなくてはいけません。 そういえば、引越し先のコーポラティブハウスで「廃材の樽を使って雨水利用タンクを作り、それを菜園の水に使おう」とかいう話が出ているのですが、これがなかなか面白いです。とかくイニシャルコストが掛かるエコ施設の中でも、この雨水利用は上手く活用すると、安上がり且つ非常に有効だと感じています。どのお宅でも出来る話ですので、是非一考してもらいたいものです。 |
| ■2006年6月21日 (水) 雨水Ⅰ |
今日は関西から配信します。 PJが片づき少しは暇になると思いきや、目論見通りはなかなか行かず、相変わらずあちこちに行脚しています。梅雨に入ってからは、ヘタをすると梅雨前線と一緒に移動しているときもあって、帰宅すると身も心もじっとり湿ってしまったりしています。 この時期は、年間雨量の二割から三割の雨が降りますが、梅雨があるからこそ、日本の稲作文化も成り立っているのでしょう。この時期の雨が稲の成長とどんぴしゃりだからです。そして遡上魚にとってもトリガーとなるのが梅雨の出水です。これも、この時期だからこそ産卵や稚魚の成長に梅雨は大きく機能しているのです。 片田舎の田園地帯に行くと、水田の周囲の水路には川から引いた一杯の水が勢い良く流れ込んでいます。最近は農薬を減らしているためか、小さな生き物にけっこう出会えます。水田をじっと見ていると、ゲンゴロウやメダカ、更にはこの時期にしか出現しないホウネンエビやカブトエビも見つけることが出来ます。 梅雨の合間、田んぼのなかでボケッと水の流れを見ていると、やはり日本はコメと雨水に支えられているのだな〜と感じてしまいます。 |
| ■2006年6月20日 (火) 八丈島おこし |
二月に行った羽田→八丈島の航空運賃は割安(往復\21200)でしたが、これは全日空と島の間で取り付けた「プラス一万人」のプロジェクトの一環でした。八丈島のメリットは何と云っても空路アクセスのし易さにありますので、ここでの運賃割引は島の観光にとっては大きなメリットです。一時期黄信号がともりましたが、三月下旬にとうとうプラス一万人を達成できました。島への観光客が年々一万人近く減っている中での、半年間で対前年同期プラス一万人というのはもの凄い話です。 このプロジェクトを立ち上げたのはボランティアの「八丈島おこし実行委員会」。いろいろなイベントを起こし、絶海の孤島である八丈島の活性化を図ってきましたが、とくに有効だったのが、以前ここでも取り上げた「ブロードバンド化」です。熱心な誘致がソフトバンクの宋さんを動かして、開設にこぎ着けたものです。これによって情報過疎を穴埋めする一方、島からも大量の情報を世界中に流し始めました。「八丈島総合ポータルサイト」がそれです。沖縄・先島のポータルに比べると、情報の深さという点では、まだまだ弱体の感はしますが、それでも立派なものです。 来島者の便宜を図るために、携帯電話基地局の整備も並行して推進しており、現地でのモバイル情報提供も始めました。こういった島民たちの地道な努力が、プラス一万人への力になったのでしょう。 羽田から40~50分で亜熱帯八丈島についてしまいます。広大な海は勿論、焼酎も島寿司も旨いですし、そしてなにより素晴らしい温泉があります。ぜひ八丈島を覗いてみて欲しいものです。 |
| ■2006年6月19日 (月) ストライカー育成計画 |
名古屋から配信します。 危惧していましたが、クロアチア戦はスコアレスドローに終わってしまいました。どこでも書いていると思いますが、日本の課題が明らかになってきました。四年後は云うにおよばず、将来の日本サッカーの一層のボトムアップを図るためには、どこをおいてもFW層の育成が急務です。 定義をはっきりしましょう。必要なのはFWと云うより「ストライカー」です。FWだけだと、名の如く前線に張っているプレーヤーでしかありませんが、ポストやアシストしか出来ない選手では話になりません。一人でも決定機をつくれる選手、それがストライカーです。ぱっと見て若手で使えそうな素材はカレンか平山ぐらいでしょうが、とても及第点はあげられません。Jリーグで例えれば、彼等にはワシントン、エメルソン、ジュニーニョ、アラウージョなどのストライカーの代役はまず務まりません。この層を分厚くすることが今もっとも求められております。 FWに求められるものは、テクニックと判断力、スピード、フィジカルだと思いますが、ストライカーはそれだけでは駄目で、相手DF2〜3人に囲まれてもボールキープし、たった一人で突破して決定機をつくっていける、強靱なメンタリティが必要とされます。とかくチームプレーにこだわる日本は、下部組織や学生の頃から、こういった強い個人を育成することは苦手です。でも海外チームと渡り合うためには、何よりも「強いFW」が必須です。上手い中盤、強いDFという構成では、いつまで経っても参加するだけのW杯に終わってしまうでしょう。 |
| ■2006年6月17日 (土) ウキゴリ雑感 |
ハゼ科のなかでは、格好がいいので、いくつかを過去飼育しましたが、愛想はあまり良くない魚です。昼は陰に隠れているくせに、夜間の活動は活発のようで、朝起きると小魚がずいぶん減ったりして、どうも観賞魚としてはよろしくないようです。 ところが、ガサ入れでのウキゴリは別。この魚が川の状態のバロメーターのような役割を果たしているのではないかと思っています。そして、今年このところのガサガサでウキゴリ幼魚が幾匹も取れたことは、とても喜ばしいことだと感じています。 ハゼ科の遡上魚(ヨシノボリ、ボウズハゼなど)は腹ビレが吸盤状になって、段差や急流でも、すごい登坂力、遡上力を見せるのですが、名の如く中層をよく泳層としているウキゴリは、ハゼ科のなかでも遡上力が弱いとされています。 そんな魚でも遡っているのですから、今年の多摩川はまあ良い状態だと思っています。雨も比較的多いので、川底の様子は悪くありません。そして、バロメーターであるこの魚に準じて、他の魚種も今年の遡上はかなり上出来ではないかと推察しています。願わくば、今年こそ、竿で一本多摩川ウナギをゲットしたいと思っていますが、普段の年よりも可能性は高そうです。 |
| ■2006年6月16日 (金) 淡水資源Ⅲ |
関西から配信です。昨日の雨とは一転、ドピーカンです。 さて、人は水がなければ生きられませんが、水の惑星と呼ばれている地球でも98%は海水、残りの淡水の殆んどは両極地方の氷になっているので、そういったのを差し引くと、人が自由に使える表層水は0.01%。仮に風呂桶一杯の水が地球上の水だとすると、人が自由に使える水は1滴くらいの存在になっています。淡水資源は上手に使わねばなりません。 そうなると日本にとって見直すべき水資源の一つが、海の水になるでしょう。一時のブームは終わった感じがしますが「海洋深層水」が良質な水資源です。 太陽光線が届かない、水深200~300mより深い海水(いわゆる海洋深層水)には、多くの栄養分やミネラルが含まれております。これは植物プランクトンがいないためです。同時に安定した低水温(2~3度)のため、雑菌が少ないという点も飲料水、あるいは酵母発酵用として高い特性を保持しています。塩分除去は確立されており、イオン交換電気透析装置で3日ほどかけて分離します。出来たミネラル水は硬度250程度で、欧州のエビアンやヴィッテル並みの硬水です。ときどき海洋深層水のミネラルウォーターを飲むことがありますが、美味しさはともかく、意外にもくせがありません。これは地下水などに比べるまでもなく無尽蔵の資源ですから、もっと活用してもいいのかも知れません。
|
| ■2006年6月15日 (木) 淡水資源Ⅱ |
日本の食糧自給率は四割とも云われており、世界中から食材をかき集めている訳ですが、じつは目に見えない水消費大国でもあるのです。 世界中の食材は、それぞれの地域で水の消費の結果として生産され、そしてそれらが日本に輸出されていることになりますので、間接的には「ニッポンは世界中で水を消費している国」という見方も出来ます。 食材に使われる水は「間接水」と呼ばれ、日本は間接水の輸入超大国ということになります。例えば、輸入穀物の代表である小麦。これを1トン作るために約2トンの淡水が必要です。1トンの小麦を輸入するということは、バーチャルですが間接水2トンを輸入するということになります。同じように大豆1トンには2.5トンの水。ちなみに小麦も大豆も、それぞれ一年間で約500万トンが輸入されます。裏に隠れた間接水の量はとてつもない規模です。 さらに怖いのは畜産物です。穀物を大量に消費する畜産物は水の消費はうなぎのぼり、鶏肉で4.5トン、豚肉で6トン、効率の悪い牛肉は20トンもの水を使います。 地球全体で水が余っているならまだしも、昨日ご紹介したように淡水資源は非常に貴重です。エコロジーを少しでも考えるのならば、こういった水大量消費型の食材は減らしていくことが、本当は大切なことなのです。 |
| ■2006年6月14日 (水) 淡水資源Ⅰ |
これから暑くなってくるとペットボトルは手放せなくなる人が増えるでしょう。小生はやや水デブ(漢方的に云うと水毒症)の傾向があるので、必要以上の水分摂取は避けるようにしていますが、それでもサウナなどに入っときには相応の水分補充をしています。 手に取るのはほとんど欧米のミネラルウォーターですが、はたしてそれが良いことなのかどうかです。淡水というのも天然素材ですから、グリーンマイレージで云うと、ずいぶんと無駄なことをしているような気がします。 世界の中では、日本は淡水資源に恵まれている方なので、どうしても水の有難味というものを軽視してしまいがちですが、いま地球上で安全な飲料水を得られない人は、少なめにみても10~20億人もいるそうです。 飽食国家ニッポンの話は都度とり上げておりますが、暴飲国家ニッポンという視点で、私達の生活習慣を俯瞰してみると面白いのかも知れません。 |
| ■2006年6月13日 (火) サッカーW杯開幕 |
先週末から、いよいよサッカーW杯が始まりましたが、予想通りというか、さっそく睡眠不足に悩まされています。世界中のトップレベルサッカーをまとめて見ることができる絶好の機会ですので、見逃すわけにはまいりませんが、夜更かしが苦手な小生なので、録画して後から見るパターンになっています。本当はリアルタイムがいいのですがね。ただでさえボケた頭がますますボケてしまいますので、ちょっと無理です。 さて、今回の開催国であるドイツは、小生にとっては馴染み深い国なので、その感慨もひとしおなのですが、ことサッカーに関しては狡猾な欧州サッカーよりも、個人技を極限まで高めた南米のサッカーに魅せられてしまいますね。よって全ての中南米チームを応援しています。 肝心の日本代表ですが、鍵となる初戦は、あと少しの集中力の差で残念ながら落としてしまいました。これでグループリーグ突破は限りなく難しくなりましたが、クロアチア・ブラジルの強豪との戦いも残っているので、最後まで全力で頑張って、日本サッカーの力を示して頂きたいものです。 |
| ■2006年6月12日 (月) アユ百万匹がかえってきた |
以前、NHKで放映されたのを見た方はご存知でしょうが、それの書籍版が小学館から出版されました。著者の田辺さんは、中本さんに一度紹介されたことがあるのですが、そのときは、まさかこれほど多摩川にのめりこんで、本まで出してしまうとは思いもよりませんでした。 この本は表題の如く、アユという魚をモチーフにしていますが、田辺さんの視点はアユだけでなく雑っ魚たちにも向けられています。 とかく水質汚染ばかりが取り上げられますが、稚魚を育む東京湾の砂州の保全など、川の再生には多くの要素が必要で、多摩川の場合はそれらが複合的に改善されてきたので、いまこうやって多くの魚が戻ってきているのでしょう。そのなかでも魚道整備が河川の活性化に非常に効果が大きいのではないか、という筆者の説には100%アグリーです。とくに宿河原堰の改修は非常に効果絶大でした。下流域でいえば、やはり調布堰魚道が最大のガンでしょう。簡易魚道とかでしのいでおりますが、最下流の魚道がプアなのは大きな問題です。これが解決されれば多摩川の生態系はもっと豊かになるはずです。 |
| ■2006年6月10日 (土) 梅雨 |
5月から雨空ばかりだったので「なにをいまさら」という感じですが、気象庁の発表では関東も昨日から梅雨入りだそうです。一般的には、この時期はあまり好かれないのですが、小生的に云うとまんざら嫌いではありません。降雨によって魚の活性が上がる要素が増えるからです。溶存酸素の増加、濁り、増水による川床の洗浄など、水温低下を打ち消して余りある効果があると思っています。釣り人も少ないのでプレッシャーが減るという副次的要素も、都市近郊では小さくない要素です。そんなわけで雨空はあまり気にせずに出かけるようにしています(残念ながら成果は付いてきていませんが…)。 また魚釣り以外でも、雨音は不思議と心を和ませてくれるので、普段以上に喫茶店に入って休むことが多いようです。必ず窓際などに席をとって読書やシグマリをするのですが、けっこう気持ちのいい時間を過せます。家ではNyチェアを窓際にもっていき、そこで酒を飲んだり、本を読んだりしています。涼やかな風が舞っていると、いつの間にか寝入ってしまったりしています。そんなわけで梅雨はそれなりに愉しんでいます。
|
| ■2006年6月 8日 (木) 銀塩⇒デジカメ |
天候不順のため三度目の正直で、延期となった子供の運動会は無事終了。中学生になる来年からは、こう云った父兄参加の運動会はなくなりますので、場所取りや写真撮影でドタバタするのも今回で終了となり、やれやれでした。 運動会につきものと云えばビデオカメラですが、どうも我が家は後日あらためてじっくりビデオを見るような行動様式はもっていないので、幼稚園以来、ずーっと小生は銀塩一眼レフカメラで通してきました。考えてみれば、こういったイベントも終わりますので、一眼レフカメラも使うことはなくなるでしょう。これからは、入学卒業や旅行のときのスナップが中心になると思いますので、おそらく手軽なコンパクトカメラのほうが重宝されるはずです。 そんなわけで、十年ばかり使い込んできた一眼レフ(PENTAX-MZ5)を手放そうと考えています。代わりといっては何ですが、先日、カメラ屋に高性能コンパクトデジカメを探しにいきました。小型軽量高画素化が日進月歩で進んでいるので目移りしてしまいますが、そのぶん陳腐化が激しいです。小生的には出来るだけ長く使いたいので、コンセプトがしっかりしている機種はないかと探したところ、リコーのGRデジタルがなかなか面白いですね。もう少し検討が必要ですが、銀塩のGR1といい、この会社のモノづくりのスタンスは素晴らしいです。 |
| ■2006年6月 7日 (水) 手ごわいシグマリⅠ |
昨日はブログ更新は出来ませんでした。なぜかというとフラッシュメモリーカードのデータが全て死んでしまったためです(T_T)。 4月にも似た症状が出て、そのときは何とか復旧したのですが、今回は相当重症でした。当然ブログネタもカードに入っていましたので、夜遅くまで復旧に尽力したのですが叶わずでした。どうもシグマリⅠのCFスロット内で発生しているようで、メモリーカード自体がへばったのか、シグマリのシステムバグかはよく分かりませんが、いずれにしても何らかの条件下で相性が良くなくなるのでしょう。 前回の事故直後にバックアップを取っていましたので、おおきな障害にはなりませんでしたが、日々更新している日和見ノートネタは少なからぬ打撃です。 常識的にはカード寿命としては全然問題ない期間ですが、何かの故障が起きているのかも知れません。値段もかなり安くなってきているので、そろそろメモリーカードも更新することも考えましょう。 |
| ■2006年6月 5日 (月) しぶといシグマリⅠ |
既報の通り、もはや小生の五感の一部とさえなっている感のあるシグマリを、遅ればせながらⅠ→Ⅱにグレードアップしたのですが、このシグマリⅡがどうも冴えません。ブラウザが進歩して、セキュリティ面でアクセスできなかったサイトにもアクセスできるようになったのですが、困ったのは今まで出来たことが出来なくなってしまった点です。 代表的なのが拙サイトのブログに何故かアクセスできなくなってしまった点です。プロバイダの仕様で、言語コードがUTF-8になっていることがネックなのかも知れませんが、どうも解析出来ていません。 それだけならまだしも、どうした案配かダイヤルアップパスワードが勝手に書き換えられてしまうので、それもまた面倒な話です。そんなわけで、今回もそうですがまたシグマリⅠを棚から引き出して使っているような状況です。 バッテリーもヘタり初めているので、いつまでリバイバルモードでやるのか分かりませんが、当面の間は手慣れたシグマリⅠでやって行こうと考えています。 |
| ■2006年6月 3日 (土) フィールド行脚 |
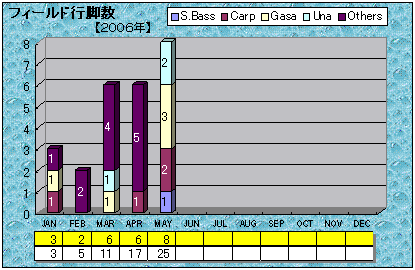 先月の不順な天候にも拘らず、フィールド行脚は順調に回数を伸ばし、5月迄の累計で25回を数えました。GWと休暇を活用したことがうまくいったようです。年間50回というのが目標ですので、一月早く折返し点をターンしたことは励みになります。この25回というデータを調べてみると、01年と並ぶタイ記録で、そしてこの年には何と72回という記録を残しております。さすがにそこまでは出来そうにないですが、50をいくら上回れるかを狙って頑張りたいと思うのも悪くはありません。年頭所感にも言及したと思われますが、型狙いや新顔をゲットするためには回数を重ねないと、自ずと可能性は減ってしまうのでしょう。50プラスαでどこまで行けるのかも楽しみにしたいと思っております。 今月6月は梅雨入りで、更に天気はモヤモヤするでしょうが、魚釣りという視点では、曇天や小雨ならば、ピーカンよりも、むしろ好条件とも云えるはずです。 さらには今月はW杯サッカーのTV観戦で時間を取られそうですが、ちなみに前回のW杯イヤー(02年)には、それでも8回も出掛けておりますので、それは言い訳になりそうにありませんね(笑)。 |
| ■2006年6月 2日 (金) 館山湾=河口 |
館山の話題が出てきたので、もう一話いたしましょう。大昔の海岸線は、氷河期の影響でいまよりずっと後退していて、東京湾は今の半分以下の面積しかなく、むしろ利根川の河口干潟の様相を示していたと考えられます。 河口部左岸に位置していた安房国の国府は館山にあり、日本書紀によると館山の湊は「淡水門(アワノミナト)」と呼ばれていたようです。つまり川の入口という意味です。安房国を拓いたのが忌部族。彼等は四国の阿波国から来ていますので、海部一族つまりアヅミ一族です。アヅミ族はなぜか遡行が大好きで、川をひたすら上るサケのようなDNAで、山深い信州の安曇野あたりまで進出しています。種を明かすと、遡行の理由は二つあって、一つは植生。日本列島の太平洋岸は温帯照葉樹林帯で、低山ながらもものすごく深い薮で、川沿いでも無ければ奥地に入り込めなかったと推察されています。もう一点は塩の確保。前のブログにも書きましたが、日本列島では岩塩が取れないために、海からの輸送路(河川)が不可欠だったのです。山奥でも塩尻などという地名が残っているのも、そんな歴史からです。 つまり河口は人間社会の玄関のような場所だったと思われます。館山湾は黒潮に乗ってやってきた彼等を自然に受け入れるような地形になっているのが、いまでも地図を見るとよく分かります。 |
| ■2006年6月 1日 (木) 南房総 |
最近は市町村合併流行りで、あちらこちらで妙な市名が聞こえてきます。地図やナビソフトの会社はさぞかし儲かっていることでしょう。 小生の地元千葉県ではいすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市などが去年から雨後の筍のごとく市制発足しています。中高の教科書で習ったときには、市ではなくても××郡○○町などと云う地名で、概ね馴染みはあります。 ところが「南房総」というと、旧行政区的な区分はなく概念的な「地方」を指しています。当然、対象とするエリアが広大で、いったいどこからどこまでが市の一角なのかまるで分かりません。館山市は当然入っていると思っていましたが、まだ残っているとは知りませんでした。 調べてみると、富浦町、富山町、三芳村、白浜町、千倉町、丸山町、和田町の7町村が合併して出来たのが南房総市ということになっていました。この市には鴨川市や館山市が当初の合併構想の中には入っていたようですが、例によって財政問題や地縁絡みの問題で調整がうまくいかず、最終的には上記の町村合併という形になったようです。 市役所は富浦になったようですが、実態はここが市の中心という感じでもありません。人口が一番多いのは外房千倉地区ですが、内房側の地区からは経済的にも疎遠です。そして和田地区は内房や館山でなく、鴨川市とのつながりが強いエリアです。 そもそも漁村がベースになっていますので、それぞれが独立性が強いのも事実。学生時代から、この辺りのエリアは踏破していましたが、それぞれ雰囲気が異なっていることは感じていました。 何でもくっつければ良いと言う話しではないと思いますが、結果として出来てしまったのは、まあへそのない、云うなればノッペラボーの市になっていますので、上手くいくとは思えません。そう遠くないうちに再編されるのではないかと見ています。 |
[Back]