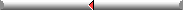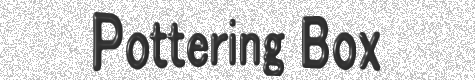 (((((Pottering Report))))) |
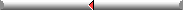
さてさて相棒たち(コーダ君&トランちゃん)とポタリングを意識して始めるようになりましたが、じつに色々なことを感じるようになりました。まず第一に感じるのは直接的な痛みです。
①足腰が弱い。 ②尻がやわい。 ③首が弱い。 日和見ノートにもアップしたように、70キロ弱のポタリングで両足痙攣の大トラブル。まともに歩けるまで3日もかかってしまいました。今回、再開するずっと以前にもチャリは相当に走っていたのですが、そのときはこれほど足腰が弱いとは思っていませんでした。よくよく考えてみたら、それは20年近く前の出来事でしたので、ベースとなる体力、筋力も、今とは比較にならないのでしょう。足腰が弱くなっていることは十二分に認識しましたので、これからは名実ともポタリングでチンタラ休みながら走ろうと思います。 足に来るのを防止することは何とか出来そうですが、どうにも鍛えようがないのが尻の皮です。足の痙攣も、尻が痛くなったために、左右のバランスを崩しながら漕ぐようになったことが一因のような気がいたします。パッド入りレーサーパンツ(レーパン)を履くようにしておりますが、それでもかなりの痛さです。いつの間にか、齢とともに尻の皮もふやけてしまったのでしょう。走っている人からは「走っているうちに慣れるよ」とか言ってくれますが、これには個人差があるでしょうね。いまのサドルはセラ・サンマルコ(Elba)、そこそこ肉厚で硬くもないのですが…。もしも3ヶ月たっても尻の痛さが変わらないようだったら、サドルを多少重くても柔いのに交換しようと考えています。  三つ目の痛みは首の痛みです。たしかに一般的なスポーツサイクルの場合、首はのけぞって前方を見る形(普段でいうとずっと空や天井を見上げているような位置関係)なので、これを長時間続けていれば痛くなるのも道理です。しかも首回りに余計な贅肉が付いているオヤヂとしては、そのポジションの不自然さはひときわ感じることでしょう。(そう云えば、その昔に走っていたときには首の痛みなどは殆ど感じませんでした) おそらくこれも「慣れれば大丈夫」という範疇のものなのかも知れません。さすがに反射神経も衰えてきたし、事故が怖いので、最近はチャリヘルを装着するようにしておりますが、それの重みがが多少災いしていることもあるでしょう(でも反射神経が衰えている今は、決してノーヘルでのポタリングはやりたくないです)。首の筋力がついてくれば、もしかすると肩こり、首の凝りなども改善していくのかも知れません。しばらくは頑張ってみます。。 基本的には痛いのはキライなので、これらの痛みからは早く解放されたいな~と願っている今日この頃です。
昔とは道路事情が違うのかどうかは分かりませんが、最近のチャリンコはあまりバックミラーを付けていませんね(小生が中高生のころは車道も狭く、バックミラーは必須でした)。チャリンコは原則としては軽車両なので、歩道ではなく車道を走るようにされていますが、車道のなかでもっとも低速の乗り物なので、やはり背後には注意が必要です。しかも、他の交通機関(オートバイや自動車)などと接触などがあれば、そのダメージはかなり大きいです。その意味では、背後の様子を視認できるバックミラーは必需品だとも云えるでしょう。それにも拘らずバックミラーをつけない理由はどんなことなのでしょう?
一つには見栄えが良くなくなること。軽快性をもとめる場合、バックミラーはたしかにうざいです。でも本当は標準装備でも良いほどの装備だとも思えます。車道にはたくさんの障害物(とくに多いのは路上駐車の自動車)があり、それを避けて進むためには、一旦車道の中寄りを走らねばなりません。このときにバックミラーがあれば早めに後続車を視認することが出来るのです。内側にふくらむときは首を回して背後を確認することは必須ですが、事前のミラー視認あるなしでは安全性は大きく違います。 また、小生が危ないと感じるのは、サイクリング道路でのロードバイクの追い越し時のぶつかりです(もちろん小生がオカマを掘られるケース)。相手もそれなりに注意はしているでしょうが、なにぶん音が聞こえないので気がついたときには手遅れです。のんびり走る身としては、ビュンと抜き去っていく(気のせいか、追い抜くときに彼らはわざとスピードを上げているようなフシもあります)ロードバイク連中との追突を避けるためにも、バックミラーは必要なのかもしれません。実は、小生も見栄えが悪いのでバックミラーを取り付けてはおりませんが、調べてみるとバーエンドやフロントフォークに取り付けるタイプもあるようです。これらの見た目がしょぼくなければ取り付けようと考えています。
既報のとおり、盗難や埃汚れが嫌なので、室内、それも寝室に置いていましたが、カミさんから「ゴム臭い」というクレームが早々と出たので、玄関(内側)に移動。どうやら交換したタイヤが新しいので、その臭いがかなり強いようです。これはしばらく外を走っていれば消えるものだと思いますが、寝室とチャリは相性がよくないようで、一週間で玄関に移動と相成りました。
とはいえ、拙宅玄関は内装がそれなりに凝っていて、漆喰塗壁やチベット和紙の棚など、チャリが触れると一発で傷つきそうな空間なのでヒヤヒヤものでした。結局一ヶ月あまりで、駐輪場に置くことになってしまいました。不幸中の幸い、拙コーポラの駐輪場は屋内にあって、雨風はまったくOKなので、マンションベランダよりははるかにマシです。ところが、吹き溜まりになるのか出入り口からの埃がすごい。SpecializedやDAHONなど、それなりに高級(だった)バイクも置いてあるのですが、いまや埃だらけで見る影もありません。一週間でも乗っていないと見事に埃まみれになるので、少なくともシートカバーを被せる必要はあります。 駐輪場にいくのが遅れた、もう一つのネックは盗難対策です。駐輪場には扉が無く、道路からそのまま入れてしまうので、しっかりとしたワイヤー錠で止める必要があります。警備会社の人に聞いたところでは、先ず二本は必要。且つダイヤル錠は駄目で、ワイヤーキーもディンプルキーで無いと、付けてないのと一緒だということでした。一本目はちゃちいので、二本目を探したのですが、なかなかよさげなタイプが無く、それで時間が掛ってしまったわけです。二本目の方は持ち歩かないので、太くて重いやつを入手いたしました。駐輪ラック場所は、敢えて取り出しにくい上段に確保しているのですが、コーダ君に使用感が出てくるまで、チャリ自身からフェロモンを出しているので、しばらくは不安な日々が続きそうな感じです。 拙コーポラは自由設計だったので、なかには数台のロードバイク置き場をちゃんと室内に設けている家もあります。残念ながら、小生の場合、設計を詰めていた時にはポタリングなどは殆ど忘却していたので、拙宅にはかかるスペースは作りませんでした。部屋数を絞って、各部屋は大きめに作ってあるので、見栄えは別として物理的には、どこでもチャリスペースは作れそうでした。例えばサイクルショップで見かけるような、吊り下げ式のバイクスペースぐらいは作っておけばよかったのですが、あとの祭りです。
障害物:
川を見ていると癒される小生にとって、土手沿いのサイクリングロードを走るのはとても好きなのですが、困ったことにオートバイの侵入を防ぐための鉄柵が至るところに設置されています。チャリですら非常に通過しにくい構造になっているので、いったいこれを作った人間はどういった「サイクリング」を想定しているのか理解に苦しみます。 車道の作りもそうですが、日頃自転車に乗ってもいない、ましてやスポーツバイクなどに跨ったこともないような人間が設計したとしか思えない、本当に走りにくい自転車レーンや道路によく遭遇します。これも血税で作っているのでしょうから、上から目線で設計するのではなく、当事者に喜ばれるようなものを作るにはどうしたらよいか、サイクリストの意見を取り入れたりするとか、もう少し知恵を働かせてもらいたいものです。  チャリンコ: その語源はよく分かりませんが、自転車の総称として最近は一般化しています。日本人の一般的なイメージとしては、日本の自転車八千万台の9割を占めるであろう、籠付きの買物用の自転車(いわゆるママチャリ)を想定しているのだと思いますが、小生的にはスポーツバイクを含めて、別段この呼び名でも構わないと感じております。軽快で愛着が湧くような感じがするからです。 ところが、本格的なMTBやロードレーサー車に乗っている愛好家によっては、十把一絡げで、この軽々しい響きで自転車を呼ばれてしまっては、自身の高級車や趣味を貶めるような風にも聞こえるらしく「チャリという言葉が大嫌い」という人が多いとも聞きます。まあ、そこまで肩肘張るのはどうかとも思いますが、自転車の良さは、使う個人個人で全て自由というところにありますので、まあ呼び名にもいろいろな見方があっても良いかと思います。そんなわけで、小生は「チャリ」というフレーズを全ての自転車に使っていくつもりです。 太タイヤ: 前使っていたロードレーサーでも、タイヤは700×25Cとやや太めに換装してましたが、それでも多摩川土手では二度ほどパンクしています。ぬかるんだ未舗装道路では車輪がもぐってこけてしまうし、車道脇の排水溝蓋(グレーチング)には幾度かタイヤを取られて肝を冷やしています。 そんなことから、出来るだけ太いタイヤにすることが、今回のチャリ買換えのメインテーマでした。これから走りたい道は舗装路よりも、農道や離島のコンクリ段差ロードですので、やはり太タイヤなくしては気楽に走れないと思ったからです。そんなわけで使い始めた700×35C(Panaracer Pasela)、オリジナルの28Cより車輪全体がそれなりに重くなっている(320→470g/本)ので、やはり舗装路ではかったるいですが、段差や砂利道、未舗装路、農道、さらには土手下り(MTBでもないので、これはお勧めできません)などを想定すると、やっぱり安心感が高いです。(とはいえブロックパターンでないので、未舗装路カーブでのグリップはほとんど期待出来ません。) 当り前のことかも知れませんが、走行環境が千差万別のなかで、オールラウンダーバイクというのは所詮は無理な話で、舗装路、未舗装路どちらに比重を置くかでパーツやスペックを決めていくしかないのでしょうね。小生は速さよりも悪路の安定感を求めましたが、いまのところ、これは間違っていなかったと思っています。  This page is edited by Zaurus。 |