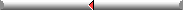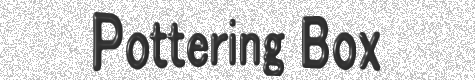 (((((Riverside Pottering))))) |
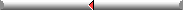
ホームリバー:
以前、川崎市多摩区に住んでいた時は、多摩川をホームリバーと呼ぶことに、ある種の誇りのようなものも感じておりましたが、鶴見川が最寄りの河川となってしまった今、同じようなトーンで『鶴見川はホームリバー』と言い切れるキアイはありません。 ホームと言い切れない理由には、越してきて間もないので、川へ思いが中途半端なことと、鶴見川が本来もっている魅力を、まだまだ小生自身がよく理解していないこと等があるのだろうと思います。多摩川に比べると地味ですし、なにより川としてのスケールが小さいのでインパクトが薄いためでしょう。これから、チャリという媒体を活用することで、より細やかな、普段は気がつかないような魅力を見つけることが出来れば、そのうちに鶴見川はホームリバーだと、威張って騒ぎだすかも知れません。早速、拙宅のちょい上流に「これがあの鶴見川?」と思えるような一角がありました。チャリが無いと、おそらくずっと気がつかなかったでしょう。  これもあの鶴見川の風景 汚濁河川: 鶴見川という河川をマイナーにしている大きな理由の一つに、この水質汚濁があります。国交省が発表している、全国一級河川の水質調査で、いつも下の方(ワースト3)に名を連ねているのが鶴見川です。行政ならびに近隣の努力の結果、今回の発表では定位置のから脱却する(3→4位)ことが出来ました。できればこのままワースト5から消え去って欲しいものです。 鶴見川は多摩川中下流域と同じく、その水源のほとんどを下水に頼っております(6割程度)。流域の下水道整備率は年々高まっているので、BOD負荷は楽になる方向というのが行政側の説明ですが、現実に土手道をポタリングしてみると、鼻を塞ぎたくなるほど臭気が強烈なのは下水処理センターの処理水排水口付近です。塩素臭やアンモニア臭が物凄いです。下水処理場は必要ですし、処理のプロセスは間違ってはいないのでしょうが、その前を走る時に、小生の五感からは「拒絶反応」しか湧いてきません。ほんとうに処理プロセスが今のままで良いのかどうか、この臭気のなかでは疑問を感じてしまいます。 鶴見川流域には7ヶ所の下水処理場(町田2、川崎2、横浜3)があって、それぞれがブワーッと臭気まみれる処理水を鶴見川に流していますので、これらの前では止まらずに一気に駆け抜けます(笑)。あくまで感覚的なものですが、走りながら川相を見ていると、汚水処理場のやや上流付近の水質が比較的綺麗な気がします。(とは云え、処理水口で釣りをしている、奇特なオジサンもよく見かけます。釣れるのでしょうか?) 源流行脚: けなしてばかりでは可哀相なので弁護します。同じ鶴見川でも上流域は、その水源を湧水に頼っているため、とても水は綺麗です。谷戸に毛が生えたようなもので、水量はしれておりますが、アブラハヤやスナヤツメ、ホトケドジョウなどが静かに棲息しているようです。(ガサ入れは遠慮しておきます)水源地は、いまは小山田の水田地帯の一角に源流の泉を整備してありますので、それがオフィシャルには水源となっています。(出掛けた九月は、まだまだ水温が高いようで水藻が繁茂していました) 唐木田あたりからバスでも行けますが、急がねばチャリンコでもさほど苦労なく行けます。ただし途中の野津田〜小山田付近では河畔の道がなくなってしまいますので、クルマも結構多く、排気ガスも多い幹線道路を走らねばなりませんので、このあたりがネックです。チャリンコでのツーリングは好きですが、幹線道路をクルマやトラックの排気ガスにまみれて走るのだけは勘弁して欲しいものです。そういった意味では野津田あたりからJR東海道線鉄橋まで延々と続いているサイクリングロードは大変な価値があるものだと思えます。さて、源流付近まで行けば、交通量もだいぶ減って、里山に挟まれた田園が広がります。なかなかのんびりしていて、チャリでゆったり走っていて気持ちがいいです。  鶴見川源流の泉 堰と魚道: どの河川の河畔を走る場合も、小生が必ず止まってチェックを入れるのが、河川のところどころにある「堰」です。勾配のある河川では、利水や治水を考えて堰を設けるケースが多いのですが、その昔は生態系のことなどは真面目に配慮されず。いい加減な堰が作られてしまったりしています。不真面目な堰というのは、川を棲み家とする生き物たちが、行き来できなくなってしまうような堰を指します。魚道の位置がいい加減だったり、あるいは全く魚道などは設けずに作られた堰がどれだけあるかで、河川全体の生態系が豊かになったり貧相になったりします。川というのは陸封された生態系ではなく、里山や森と海とをつなぐゆりかごのような存在でもあるのです。 多摩川は流域住民(特に都民)の環境意識が高く、最近の政治家の言葉でいえば「やかましかった」ので、取水堰と魚道の改修が積極的に行われてまいりましたが、鶴見川では行政が分断されているので、河川環境の改善「魚が上りやすい川づくり」などには、着手が遅れていました。ところが昨今の鶴見川流域の整備事業をみていると、この点での配慮が次第にされてきているのを実感しています。更にはポタリングで網羅的に河川を眺めていると、新たに改修整備された一角では、堰を崩してなだらかにしたり、堰を改修する場合もまともな魚道作りを志向しているようです。河川の生態系を豊かにしようという意識が感じられ、まあ合格点があげられると思います。  遡上魚の第一関門、小机の堰 親水護岸: この夏の兵庫県の川で起きた、上流域集中豪雨にともなう水の事故などが、悪い方向に向かうと、行政側はまた川と人とを分断するような愚行をしないかと危惧しております。 たしかに、ここ二十年ほどの都市化の弊害は、河川にずいぶんツケが回っています。かっての水田のような遊水部分もなくなり、里山が削られ樹木が切られた結果、雨は一気に河川に流れ込んでしまいます。とくに鶴見川のような流域の殆どが都市化しているような河川では、数多くの支流から一気に水が入ってきて、瞬く間に大増水です。鶴見川流域の都市開発では、遊水地や集合住宅の雨水貯水槽などの設置が義務付けられておりますが、近年のゲリラ豪雨にはとても追いついていません。拙宅近辺の支流では、上流部にいくつかの遊水地があるにも拘らず、1mぐらいの水位アップは茶飯事です。 このような中で「親水護岸」というのは論議が分かれるかとも思いますが、日頃、どれだけその河川に親しめるかで、河川環境の改善進捗は大きく変わってくることは間違いないと小生は思っています。下流域の、いわば巨大な排水路としての鶴見川しか見ていなかった身としては、流域でこれほど親水護岸整備が進んでいたとは、正直言って町田に越してきて、更にチャリで河畔を走ってみて初めて認識をあらたにした次第です。スペース的な制約のなかで、よく整備してきたなーという印象です。それとも東京都の行政力でしょうか?(遅ればせながら川崎・横浜エリアも整備されつつあります) いずれにしても、この親水護岸整備がさらに進んでいくことで、鶴見川は流域にもっと親しまれる存在となるはずです。それとともに川の水が綺麗になり、多様な魚たちが戻ってきてくれる日を心待ちにしております。  少しずつ増えている親水護岸 This page is edited by Zaurus。 |