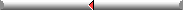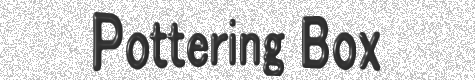 (((((Coda Sports 2))))) |
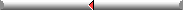
シートポスト:
基本的には前回のレポートでもお伝えしたように、Codasportsの完成度は高く、通常の街乗りではコンポの交換などは考えなくとも良いと思われます。ところが小生のように丘陵の尾根や林道、あるいは島ロードなどを徘徊していくうちに、いくつか手を加えたくなるようなパーツが出てきます。真っ先に感じたものはシートポストです。 クッションストロークのあるシートポストサスペンションは、サスペンションフォークの無いチャリでダートや段差が多い道などを走る場合、衝撃を緩和するので重宝するというのが能書きになっておりますが、もともと尻には厚い肉が付いているので、これはさほど恩恵としては感じません。 むしろデメリットとして、巡航中のペダリング干渉があります。共振するのか、平らな道でもケイデンスを多めに漕いでいると、ボヨンボヨンとはねるような状態になってしまうことが時々あります。これは気持ちが良くないです。あとは構造上の問題で、シンプルなシートピラーに比べると重くなってしまう欠点もあります。 350mmという長さも、小生には少しばかり足りなかったので、軽めのSyncrosの400mmに交換することにしました。重量は450gから290gになりました。これで走りが劇的に軽くなるとは思えませんが、ボヨンボヨンが減ったのは嬉しいことです。  シートピラーひとつでシルエットが締る クランクセット:
伊豆大島の長い坂道には閉口しました。このような場合は、スローペースでもいいので、長時間ひたすら漕ぎ続けられることが必要です。多摩丘陵には激坂はあるのですが、10キロちかく続くような坂道はありませんでしたので、伊豆大島ではコーダ君も途中で挫折してしまいました。そんなわけで、坂道対応をもう少し強化することに致しました。 基本的には、ローギア側を広げて、もっぱらトルクを求めて行くことになりますが、複数のギアが並べられる幅には制約がありますので、ハイギア側を減らすことになります。つまり、今まで程のスピードは出せなくなるということです。これについては割切るしかありません。小生のスタイルはスピードではなく、ゆっくりとどんな道でも走っていく、ということですので、スピードには執着はありません。 コーダ君のリアスプロケット(リアギア)はSRAM製の9速。ロー側で、MTB並みに32枚あるので、これはいじる必要はありません。よって、クランク(ペダル側)をいじることにしました。チェンリングをオリジナルの52/42/30Tから、MTB並みの44/32/22Tに変更したいとショップに行って相談したら、こういう場合はクランクセット丸ごと交換したほうがベターです、ということで、丸ごと交換することにしました。パワーアップのために、クランク長も長くしたい(170mm→175mm)と考えていたので、その点からもクランクセット交換しか手段はなさそうです。 オリジナルでも、FSA(Vero)のクランクセットなので、クランク交換でグレードは落としたくはありません。MTB系ならばシマノのDeoreあたりならどうかと、在庫を調べてもらいましたが、時期的にはモデルイヤーの切替え時期で、問屋にも在庫がまったく無いというタイミング。値段を勉強してもらうことで、もう一つ上のDeore-LXにすることにしました。ホローテックIIとか云う、いま流行りの軽量高剛性の中空シャフトのクランクです。クランク軸を覗くと反対側が見えます(笑)。クランク長は175mmとしました。 マッシブなデザインは好き嫌いが別れるところですが、個人的には細いフレームと対象的で、意外と面白いかなと思っています。シマノの陰謀でしょうか、BBも専用のものに替えねばならず、結局クランク回りはペダルを残して、すべて様変わりです。  シャフトが中空のLXクランク。FDはこの時はオリジナル。 ディレィラー:
ところが、クランクセットをいざ取付けてみると、意外な問題が生じました。シートチューブ(フレーム)にFディレイラーが取り付けてあるのですが、クランク径がコンパクトになったために、その台座を下にずらす必要が出てきました。ところが、微妙な位置にボトルゲージ用のビスが入っていて、台座を下まで降ろせません。このままですと、ディレイラーの位置が離れているので、シフト時にチェーンが流れて外れてしまいます。 それでは困るので、応急措置としてアウター側に遊びをなくして、インナー側にチェーン外れ防止爪を取り付けて、内側にチェーンが外れても戻るようにしてもらいました。チェーン外れはないものの、シフト完了タイミングが1段階ずれること、リアをアウト側の振ったときに、Fディレイラーにチェーンが擦る現象も生じてしまったので、どうにも按配が良くありません。そんなわけで、ディレイラーもDeore専用のディレイラーにすることにしました。台座取付け位置の制約もなくなりますので、クランクに対してキチンとしたアライメントでディレイラーを取り付けられます。 ところが、部品在庫については、ディレイラーについても同じような話があって、LXのディレイラーが問屋に欠品ということが分かりました。これに対して、値段を勉強してもらいつつ、フロントは新型のSLXに、この際なのでリアも旧モデルのXTでディレイラーを組んでもらうことにしました。あれやこれやで、変速系は一気にレベルアップした感じです。  FDは新型SLX  RDはなんとXT シフター:
オリジナルのシフターは、フラットバーロード系シフターですので、交換したFディレイラーとは互換性がありません。よって、シフターについてもDeore系に交換することになりました。(リア用は変更する必要ありませんが、左右のシフターが違うのは見た目もよくないので、リア用もシフターも交換することに) シフターについても、在庫状態は一緒です。Deore-LXが欠品しているので、これもXTになりました。云わば継ぎはぎ仕様になってしまいましたが、すべてのパーツがグレードアップしたので、操作感はありえないぐらい良くなりました。シフターの流れが逆(外すと軽いギアになる)になったので、とっさの時に間違えてしまいます。多少の慣れは必要です。  シフターもXT。オリジナルと流れが逆ですが。 ブレーキ:
伊豆大島でも気になったのですが、チャリの場合、ブレーキへの依存度はクルマ以上に高いです。エンジンブレーキなるものは有り得ませんし、もともと慣性走行性能を、極限まで円滑になるようにセットアップしている訳ですので、下り坂のスピードたるや凄いものがあります。そしてこれを制御するのは、唯一ちっこいブレーキシューです。 伊豆大島と沖縄やんばるでのチャリ遠征を過ぎたブレーキシューは、かなりの摩耗状態。それ以上にヤバかったのは、フロントのシューが捩れてしまっていたことです。なにしろ10キロ近いダウンヒルを、ブレーキかけ続けていたことになりますので、その力と摩擦熱はかなりのものだったはずです。 テクトロ製ダイレクトプルVブレーキは、前後にアームの遊びを設けることで、リムへのリニアーな圧着を図る仕様になっているらしいのですが、長時間のダウンヒルで、ブレーキを掛け放しするような使い方は、やや苦手のような感じも致します。ポンピングを意識すれば、たぶんOKのはずですが…。 そんなわけで、ブレーキもDeoreに交換することにしました。多摩丘陵程度の下り坂では、ほとんど違いは分かりません。操作感よりも、構造的なポテンシャルだけの問題だと思いますが、命綱であるブレーキには、少しでも精度とか余力を残しておいた方が良いでしょう。  ついでに前後ブレーキもDeoreに。
以下に纏めてみましたが、変速系を中心にkかなりのパーツ交換になっています。とは云うものの、やはり自分の好みに合わせてチューンナップすると、今まで以上に愛着が湧いてきます。
オリジナルでも完成度が高かったコーダ君。クランク、ディレイラー、シフター、ブレーキの変更で、クロスと云いながらも、かなりマウンテン系に様相が変わってしまいました。走りの方も変わりました。当り前のことですが、最高速度はそれなりに抑えられた一方、坂道や尾根の走破力という点では、ずいぶんとワイドになりました。
当然のごとく、シフトレスポンスもかなり改善しました(というか、びっくりするほど)。ここは以前から不満がありましたので、大幅改善で大満足です。
次なるTune-up:
これで、芋づる式に続いたチューンナップは一段落という感じです。そして次なる対応は、もう決めております。タイヤとチューブの交換です。自転車用タイヤというのは、本来、耐久性から云えば3000kmぐらいは行けるものなのですが、今のタイヤのグリップ性に不満(不安)をもっているので、これは1000km超えたあたり(年明け頃)にでも行おうと思っています。 今まで走った道で云うと、舗装路が8割、ダート2割という感じではないでしょうか?コーダ君を買った時のイメージと比べると、ダートが意外と少ないです。そうなると、必ずしも700x35Cにする必要はなさそうです。林道や尾根筋を走る際の、個人的な感触では、ショルダーさえしっかりしていれば、段差対応も含めて、32Cでもいけそうな感じです。 いまの35C(Pasela)は、存外にグリップが弱く、簡単に滑るので、カーブやウェット面では、かなりヒヤヒヤものです。グリップ性は、太さよりもパターンに依存しているようです。太くてもグリップ性を担保するものではないと言うことが、幾度か危ない目にあって分かりました。 次は出来るだけ高グリップの32Cに交換したいと思っているのですが、困ったことがあります。それはタイヤ重量です。35C(Pasela)は470g。32Cにすれば、軽くなるのが道理ですが、高グリップで、耐パンク性能も高いような頑丈なタイヤでは、重さがぐんと違ってきます。 軽い⇒薄い⇒パンクに弱い、ということと、パンクに強い⇒分厚い⇒重い、というトレードオフの関係を、理解したうえでタイヤを選ぶことになります。そのためには小生の走り方を、もう一度確認する必要があります。 ①悪路でも高グリップ力を求めたい ②パンクは極力避けたい ③スピードは出なくとも良い こういう事になります。やはり、タフな仕様を求めることになりそうです。頑丈一徹ならばドイツSchwalbeのマラソン(550g/32C)がベストバイですが、kendaのKwick-Trax(500g/32C)もトレッドが美しく強靭そうです。IRCのURBANMASTER TOURIST(550g/32C)もパワフルそうです。いずれを選んでも、今より重量アップになってしまうので、そこらが心配ではありますが。 This page is edited by Zaurus。 |