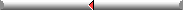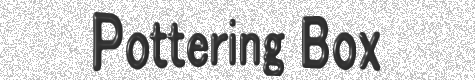 (((((Okinawa Town in Tsurumi))))) |
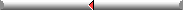
鶴見のウチナーたち:
さて、今回のテーマのトリガーですが、先日読んでいた本に、鶴見の一角にある沖縄タウンのことが取り上げられていたことから始まります。それによると、鶴見川を挟んで、鶴見駅の反対側にある、潮田(うしおだ)銀座、仲通商店街あたりに、どことなく広がっているエリアが、鶴見の沖縄タウンと呼ばれているそうです。とは云っても、中華街やセメント通りコリアタウンのような集中したものではなく、なんとなく沖縄物産店や沖縄料理の店が点在している一帯とのこと。 さて、かくなる沖縄タウン。いったいどんなところなのか、本を読むうちに興味が湧いてまいりました。しかも、小生のポタリングルートのひとつでもある鶴見川から近いエリアにあるとも聞いたので、ならばとコーダ君と一緒に出掛けてみることに致しました。  鶴見沖縄県人会のある「おきつる会館」 町田→鶴見ポタ行雑感:
コーダ君は変速系と前後ブレーキを換えたあとなので、テストランもそれなりのアップダウンのあるルートを走るべきですが、今回は日和って平坦ルートになりました。寒くなってきたので、年内のポタリングはそろそろお仕舞、と考えていたのですが、たまたま南寄り風の入ってくる、暖かな日が週末に重なったので、昼過ぎからのんびり出掛けることにしました。 とは云え、この陽気がくせ者でした。往路の大半が向かい風だったのです。鶴見川のような小さな川でも、風の通り道になっており、河畔をずっと下るあいだ、ずぅーっとアゲインストでした。拙宅から鶴見までの30キロは、休憩を入れて一時間半もかかってしまいました。まさに日和を間違えてしまいました(笑)。 綱島や新羽あたりからショートカットしても良かったのですが、クルマの多い道は危ないし空気もキタナイので、基本的には土手沿いのサイクリング道路をひたすら走りました。アゲインストも下流に行くにつれて強くなってきて、どんどんへこたれてきたところで、ようやく森永橋に着きました。 とは云え、このサイクリング道路は、人ごみの多摩川サイクリングロードよりも空いていて、ずっと快適です。通常、小生のポタリングスピード(20〜25km/h)では、ロードバイクにどんどん追い抜かれるのですが、今回、往路では一度も抜かれませんでした。つまり下り方面のロードの人がおりませんでした。それだけ空いています。(ただし、「青少年サイクリング道路」というのには、オヤヂとしては若干の違和感を覚えるのですがね…) 森永橋から一旦、鶴見市街に入ってから国道沿いに走り、JRと京急の鉄橋をくぐり、再度鶴見川にぶつかり潮鶴橋を渡ります。この付近は、以前シーバス釣りで幾度も通ったところです。橋を渡ると、道路は太くなり潮風大通りという名になります。そのまましばらく行くと、これでようやく沖縄タウンに近づきます。 仲通商店街:
沖縄タウンというのは、沖縄出身者や沖縄にルーツをもつウチナーたちが、比較的多く住んでいる一帯ということで、中華街のようなところをイメージすると、とんだ肩透かしを食らうことになります。 潮風大通りを少しばかり行くと、やがて「仲通り商店街」と交差します。ここを左に曲がってしばし直進すると、鶴見沖縄県人会の建物「おきつる会館」が見えて来ます。この建物を中心に、いくつかの沖縄食材店、そば屋、居酒屋などが点在しています。ここ以外にも居酒屋、あるいは沖縄と縁の深い南米料理系列の店など、広範に点在していますが、比較的固まっているエリアは、このあたりになります。 沖縄料理を食べたり、食材や土産物を探すだけならば、おきつる会館周辺で十分に堪能できるはずです。ちなみに、このエリアは鶴見駅からは歩くと、けっこうありますので、バス(27系統で往路は潮田神社下車、復路は仲通り三丁目乗車。15系統で向井町三丁目でも可。)が、便利だと思います。  うちなー日常品なんでもあり おきつる会館の一階にある沖縄物産店では、沖縄でしか売ってない食材がところ狭しと並べられております。チャリ行なので、買い物はせずに、大好きな沖縄バヤリースだけ購入して、近所の沖縄そば屋に移動しました。行こうと思っていた食堂「コージ小(グヮー)」はあいにく休憩時間(15〜16時)だったので、「かなやあー」とかいう小さな食堂に入りました。 狭い店内には、おばちゃんと、昼間から酒をのんでいるおじいさん。壁にはいろいろな芸能人(よく読めないし、芸能人はあまり知らないので誰だか不明)のサインなどが貼ってあります。たぶん沖縄出身の芸能人なのでしょう。ソーキそば(\850)を注文しました。コーレーグースをババッと振りかけて食べてみました。意外とか云うと失礼ですが、けっこう美味しかったのでビックリしました。何はともあれ、沖縄の本格的な味を、いつでも鶴見の片隅で味わえることは非常に嬉しい気がします。  そばは美味しかった。次回はご飯ものを。 潮田神社:
もう少しのんびり周囲を散策してみたかったのですが、季節は冬、日も早々傾きかけていたので、そそくさと帰還することに致しました。帰りがけに潮田銀座を回ってみると、こちらには殆ど沖縄風の店はありません。暗くなれば居酒屋などがオープンするのかもしれませんが、そこまでは待てません。泡盛と三線とで盛り上がるのでしょうかね。 ふと見ると、潮田銀座のどん詰まりに、立派な鳥居が見えます。寄ってみると、これが潮田神社です。寺社巡りが好きな小生、例によって立ち寄り、道中の安全を祈念しておきました。この神社は、いままで沢山の沖縄からの人たちの安寧を見守ってきたのでしょう。  立派な鳥居の潮田神社。
南米移民と琉球文化:
そもそも鶴見と沖縄のつながりは、南米航路の表玄関「横浜港」を媒体として発生したものです。100年前に大勢の沖縄人が、ここを起点として、海外に農業移民として旅立っていきました。初めはハワイ、やがてペルー、ブラジル、アルゼンチンを中心とした南米諸国が中心となりました。 何かの事情で、この地に残ったウチナーが、いまの沖縄タウンの開拓者のようなものだったと思われます。やっとここまで来て、南米にも行けず、かと云って沖縄にまた戻るお金も無く「ここでやるっきゃない」という覚悟で頑張ったのでしょう。いまなお、この街が沖縄タウンと呼ばれ続けているのは、こういった頑張り屋さんのおかげです。 やがて、終戦ともに移民者の一部は引き揚げてきました。横浜港から近くて、同郷の親類縁者が多い鶴見界隈に、彼らが集まってきたのも、こういった結びつきを大切にするウチナーたちにとっては、特段不思議なことではありません。いっぽう沖縄からの移民も米軍統治下で再開されて、ボリビア、ペルーなど南米諸国に向かったウチナーたちも多かったようです。 今回のテーマは、鶴見と沖縄とのつながりです。鶴見区というのは横浜市の一行政区ですが、今まで小生的には鶴見が横浜の一部と呼ぶのには、かなり抵抗がありました。歴史的にも文化的にも、横浜市より、むしろ川崎市に近い地域だと思っていたからですが、今回のテーマを通して感じたことは、横浜港抜きには鶴見沖縄タウンは語れないということでした。このようなことから、鶴見の帰属は川崎だと言い切るのは、必ずしも正しくはないな、という気になりました。 京浜工業地帯への出稼ぎ: 鶴見は京浜工業地帯のど真ん中、戦後の復興期から高度成長期にかけて、工業地帯では大勢の労働者を必要としておりました。そこで頼りにされたのが、農村地帯からの出稼ぎ労働者、そして沖縄からの労働者でした。鶴見沖縄タウンは、上に取り上げた南米移民絡みの在住者に加えて、その生活の場を沖縄からこちらに移した工場労働者によっても、成り立ってきたと言えます。 さらには、彼らをウチナーと呼んでいいのかどうか分からないのですが、1990年の入国管理法改正以降、日系人の2世、3世が、ツテを頼って日本に戻ってきて就労、定住するケースが増えました。多くは沖縄にルーツをもった人たちのようです。鶴見に南米系料理の店が多いのは、こういったウチナー系日系人たちの移住によるものでしょう。沖縄料理店と南米エスニックレストランが、軒先を並べているのは、ちゃんとした理由があるわけです。 本土の沖縄タウン: このような沖縄タウンのようなものは、大阪や尼崎などにもあるようです。いずれも鶴見エリア同様に、親類縁者のつながりで、一定の地域に集まってきたものだと思われます。通常は、長い年月が経てば、地域性というのは、次第に薄れていくものなのですが、どちらの地域でも、いまなおウチナー色が色濃く残っているということは、本当に大したものです。 いま沖縄タウンに住んでいる人たちの多くが、沖縄では暮していなかったにも拘わらず、こうして沖縄文化を維持できていることは驚きです。その理由を突き詰めていくと、おそらくは、郷土とその文化への愛情ということになるのでしょう。あまり根っこのない小生にとっては、こういった世界がとても素晴らしく、貴重なものに思えるのです。  休日だったらしくサーターアンダギーは買えず。残念。 This page is edited by Zaurus。 |