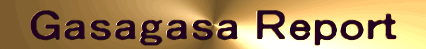 |

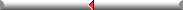
| 2001-11-04(日) | 多摩川 [PHOTO] | |
| 09:00-11:00 | 晴れ |
スジエビ、ヨシノボリ、 小ブナ、 モツゴ、モロコ類 |
| タモ網、 | ||
|
子供にせかされたのとヌマチチブのエサ確保ということで、親子ともども11月というのに短パンで川に出かけることになった。空は雲一つない好天。風はすこし寒いがいい季節である。 最初に行こうとしていた場所には「人影」が見えたのでパス。次なるポイントへ。水位は昨日降った雨にも拘わらず、あまりない。濁りが多少入っている程度。 ここぞという場所を探し、ガサ入れをしてみるが全然だめ。たまに採れるのはヌマチチブのベイトサイズのタモロコのみ。やはり深場に落ち始めているのだろう。 あまり採れないので子供は砂遊びにシフト。砂のソファやベッド作りにいそしんでいる。何でも遊びにしてしまう子供の感性はさすが。こういう時代だから、大人も固定観念に縛られないで、もっと自由な発想が必要なんだな、などとふと考えてしまう。 水位がやや減っているので中州に移動してみる(渡河は深みもあり危険なのでお勧めしない)。人が入ってないので開放感がある。なんとタヌキの足跡を発見した。人や猟犬が入ってきてないので生きながらえているのだろう。大事にしたいものである。 あとは河床改修のためか、国交省が中州にブルトーザーを入れた跡があった。この時期に改修が必要なのかどうか、ちょっと疑問をかんじた。これは京浜工事事務所に問い合わせてみようと思っている。 ガサ入れのほうは、ヨシノボリや小ブナが若干採れるものの、どうやらもう時期的には本流筋のガサ入れは厳しくなってきたようだ。これからは細流や河原の野池での採集が中心となろう。 | ||
| 2001-10-28(日) | 多摩川  |
|
| 06:00-09:00 | 曇り・雨 |
スジエビ、ヌマエビ、 小ブナ、コオイムシ、 モツゴ、モロコ類 |
| タモ網、 | ||
|
木曜〜金曜と北茨城へ出かけてたので、土日はグッタリ。川に出る元気は全然無かったのだが、水槽の魚たちにエサをやっているうちにムラムラその気になって、多摩川にタモ網をもって出かけることになった。殆ど衝動的な行動パターン。小生もこの辺は子供返りをしているのかも知れない。 天気の方はあまり良くなく、空には一面雲がかかっているが、どうせ水にはいるのだから関係は余りないが、川に行ってみると水位は先週よりさらに下がっている。十センチ強という感じか。先週遊んだ河原の野池も干上がっている。一杯泳いでいた小魚達はどうなってしまったのだろう。 水位が下がると、水は透明になって濁りが消えるので、水辺の採集はなかなか大変になる。そんなわけで、今日は本流筋というよりも、河原の野池群の干上がりそうな奴を探ることと、時間があれば中州にでも渡って新しいポイントを見つけてみることにした。 今日の狙いはズバリ「ムギツク」、サブとして「カマツカ」「ニゴイ」で、それにヌマチチブのエサ(タモロコ稚魚)が入る。特に、この付近の多摩川でムギツクは厳しいが、まあこれも下手な鉄砲数打ちゃ当たるというセンスでやっていくしかない。 さて、河原にいくつかある野池。どこも伏流水位が下がっているために、一様に小さくなっている。水質も悪くなっているところが多いが、それでも幾つかには伏流水が湧き出して、まだまだ小魚がいる。とくに目立ったのはスジエビ。産卵パターンが不勉強で分からないが、それこそ「湧くように」いる場所があった。いつまで保つ場所か分からないので、採集したエビは本流筋に再放流。 中州に渡ったが、いつもの小魚ばかりで、とくにめぼしい成果は無いまま、雨が本格的に降り始めたので撤収することにした。降下とか魚の動きが出てくるのは、もう少し秋が深まったあたりのような気がする。 またブルトーザーが中州で河道改修をやっていた痕跡があったが理由は不明。何か目算はあるのだろうか?そういえば右岸の魚道口付近の地形がシンプルになっていた。感覚的にはこれで岸寄りを遡上してきた遡上魚がもっと堰上に上がれることが出来そうだ。 |
||
| 2001-10-20(土) | 多摩川 | |
| 10:30-13:30 | 晴れ |
小ブナ、スジエビ、 シマドジョウ、オイカワ、 アブラハヤ、モロコ類 |
| タモ網、お魚キラー、 | ||
|
今日は、小生のHPを見てガサガサをしてみたくなったという友人「Oさん」に、ガサガサの紹介を兼ねて娘と多摩川へ行く。まあ言うなれば「ガサガサ接待」である。早朝からシーバス釣り、コイ釣りと重ねてきて、ダブルヘッダーならぬトリプル行脚に目が回るが、そうも言ってられない。思い起こせば四年前、仕事も体調も閉塞状態だった小生に、他ならぬ「Oさん」の奥方から勧められ、十数年のブランクをもっていた魚釣りを再開したわけで(リバーサイドカフェ参照)、いまもって大きな恩義を感じている。何気ない一言だったのかも知れないが、それがあるからこそ、今こうして魚釣りをし、かなりいい加減だが元気に生きている自分があるのだと思っている。そんなわけで、それこそガサガサ接待を成功させねばメンツがすたる。という訳である。 そして、もうひとつ。思うに小生もガサガサをする前に幾度も多摩川に来ていながら、今になって思うに川との距離はそれなりにあったような気がする。というのは、釣りというのはやはり陸からの視点で成り立つもの。水に入って逆に陸地に向かってバシャバシャと騒ぐことで、小生のココロのなかで川との距離がぐっと縮まったような気がする。多摩川に深い愛着や共感を覚えたのも、ガサガサを始めてからだ。そんな意味でガサガサを通じて多摩川を知ってもらう人を一人でも増やすことは、いまの小生がこの川に対して出来ることの一つでは、という気持ちもある。 とはいえガサガサをするには、いまの多摩川のコンディションはそんなに良くない。台風でガサガサが根こそぎはぎ取られてしまったからだ。おそらくは中流にいた魚たちもかなり流下してしまったのだろう。アユのようにこれから産卵をする魚にとってはかなりの打撃だったかも知れない。 とはいえ出水でよくなった面もまたある。河床が削られたり、底石が磨かれたりして、悪臭や水質悪化の要因ともなる水垢やゴミが洗われ流されてしまったという点である。多摩川マスターの中本賢さんの実地調査でも、アユの産卵床になる水苔の付いてないきれいな底石が今年は多いという話を聞いた。一部のアユは流されてしまったのだろうが、そのあとには立派な産卵床が残る。産卵の恩恵にあずかれるのは、濁流を生き延びた優勢なアユたちだけである。彼等が次世代に命をつなげていく。自然のメカニズムはいろいろな事象を起こすけれど、一般的に我々人間が把握しているのは、ほんの一部だけのような気がする。 さて、少なくなったガサガサの場所で、子供や初めての人でも遊べるような場所は、殆ど無く、今日アレンジしたところもおそらくは攻められているところ。朝にでもガサ入れされていればアウト=BOZとなるので、接待役としては大いに不安。 結果的にはオイカワ、シマドジョウなども入って、そこそこ賑やかな成果となって一安心。雨後で心配した水もきれいで、「Oさん」も久々に童心に帰って満足できた様子。ウキゴリなどハゼ類が入らなかったのは、ちょっと残念だったが、都心からほど近い多摩川でも沢山の魚が生きていることを知ってもらったので、多摩川や川に対しての精神的な距離もかなり近くなってくれたのではと思う。 日和見ノートにも書いたが、川の底力というのは放流されたアユやコイではなく、これらの雑っ魚がどれだけ豊富に再生産しているのかということ。そういう意味で、多摩川は確実に再生しつつある都市河川だとあらためて感じた。 |
||
| 2001-10-13(土) | 多摩川  |
|
| 10:00-12:00 | 晴れ |
小ゴイ、小ブナ、 モツゴ&モロコ類 |
| タモ網、お魚キラー、ビンドウ | ||
|
今日は多摩川に行く予定は全くなかったのだが、娘にせがまれてガサガサ道具一式をもって昼前のひとときを河原遊びのために出かけた。天気は秋晴れでまさに川遊びには最適である。 ただし既報のとおり、子供が遊べるガサガサ域が、台風後ほとんど無くなってしまったのでポイント探しに頭が痛い。結局のところ先週魚キラーでモツゴが大量に入った水溜まりに行くことにした。水溜まりといっても伏流水の湧水が流れ込んでいて、水はかなり澄んでいる。ここでは底棲魚がほとんど採れないが、今日は娘主体なので仕方がない。 浅場オープンウォーターには雑っ魚が一杯見えるが、これをタモで掬うのはかなり厳しい。娘に網を待ち伏せさせて追い込んでいくと、ようやく小さなモロコが入った。子供は欲がないのでこれで大満足(一安心)。一方、先日のケースでは魚キラーはどうも「大物」ばかりなってしまったので、もう少し可愛いモツゴ&モロコをゲットするために、今回はビンドウも投入。スイミー団子を入れて、早速試してみたらどっちもウジャッとモツゴが入る。 採れるサイズはビンドウも魚キラーも有意差は認められない。4〜5センチから8〜9センチぐらいという感じに偏ってしまう。ヌマチチブのエサとして個人的に欲しいのは2〜3センチ級なのだが、どうもこれらは網でシコシコ採らないと駄目なようだ。 設置場所を変えて3〜4クールぐらい魚キラーとビンドウを仕掛けたが、ウジャッと採れる場所と、反対に一匹も入らないポイントがあるのには驚いた。いずれにも雑っ魚の大群がいっぱい見えているのにも拘わらずである。 動きがないので、小生としては魚キラーもビンドウも、タモ網のガサガサほど好きではないが、これはこれで結構奥が深そうな漁法である。次回は試しにエサを変えてみようと思っている。 |
||
| 2001-10-07(日) | 多摩川  |
|
| 14:00-17:00 | 曇 |
ヨシノボリ、シマドジョウ、 小ブナ、スジエビ、 モツゴ&モロコ類 |
| タモ網、お魚キラー | ||
|
鶴見川汽水域でのコイ釣りが大ハズレで終わったので、多摩川コイ釣り場探索という名目で、タモを担いで歩き回る。小生のテリトリーは、宿河原堰をはさんで、上は中野島の堰堤(上河原堰)から下は東名多摩川橋まで3キロあまり。台風の爪痕は甚大で、宿河原堰の上も下も大きく河床が変わってしまった。小生のお気に入りだったコイ釣りのポイントも、ガサガサのポイントも全てやられてしまい、また一から出直しという感じである。 とくに宿河原堰からの下の地形は大きく変わり、東京側にも流心が出来てしまい、化石マニアがいつも集まっていた新生代の土丹層河床もすべからく水面下。泥が固まっている岩盤ですので、台風の濁流で壊されたのでしょう。堰下流の河原には1立米級の塊がゴロゴロと転がっていて、なかなか壮観。水中の土丹層はヌルが付いていてかなり歩行には注意を要するが、土丹層の溝の中には小魚がたくさん走っている。安定したポジションがとれないのでガサ入れはしなかったが、おそらくは小バヤだろう。 その下、中州をはさんで東京側と川崎側に分かれていた河道は全て川崎側に寄ってしまい、川崎側は流れが強すぎ、東京側は水溜まりになってしまっている。どちらも釣りというにはいまいちであるが、東京側はもともと在ったテトラの足元が格好の小物釣り場になっているようで、週末ということもあり大勢の人が糸を垂らしていた。まさかここをガサガサで荒らすわけにはいかないのでパス。やはり堰下流はポイントが少ない。幾つかここだというところでパンを流してみるが無反応。どうも駄目である。 そんなわけで上流側に目を転じることにしたが、こちらもまた厳しい。当然ガサガサは消失し、しかも流心が東京側、川崎側それぞれに寄っているので、岸辺から急深になっていてガサガサするには危険きわまりない。かといって流れが強すぎてパン餌を流せるようなスタンスがなかなか採れない。試しにパンくずを撒いてみても反応がない。 どうも今回の台風は今の時点では「凶」と出ている感じだ。取り残された水溜まり(洗掘されているので結構深い)が幾つか出来ているので、ガサガサではなく「お魚キラー」をセッティングしてみたところ、モツゴがウジャッと採れたが、7〜8cmの大物ばかりなのでヨッシー軍団やヌマチチブ君のライブベイトとしては全く不適合。ビンドウに比べると魚キラーは小魚よりも大物が選択的に入るのだろうか?なかなか上手い具合にはいかない。 ところどころに洪水で堆積した砂山もあり、どこまでも続く石河原の放浪となったわけだが、まるで賽の河原を歩く罪人となったような気さえした。いや〜それにしても疲れた〜。 |
||
| 2001-09-24(月) | 多摩川 | |
| 17:30-18:00 | 晴れ |
ヨシノボリ多数、 スミウキゴリ、シマドジョウ、 スジエビ、モツゴ&モロコ類 |
| タモ網 | ||
|
土曜日に採ったカマツカがウキゴリにやられてしまい、頭にきたので多摩川に再放流に行く。そのついでにちょっとガサガサを行なった。 実家に帰っていたので時間もなく、日没前の30分ばかりだった。水位の方はかなり下がっていて、先日巨ベラをゲットしたクリークもほとんど干上がっていた。やはり金曜〜土曜のタイミングがベストだったのだろう。カマツカゲットに仏心をだして攻めなかったのが悔やまれる。釣りもそうだが、自然相手はタイミングが命。ガサガサは採れるときに採っておく、という心構えが肝心だと云うことを感じた次第。 カマツカを採ったポイントに行くと、水位は下がっているので、土曜日攻めたポイントは陸地になっている。ただ濁りはかなり引いてきた感じだ。取り急ぎウキゴリを放すと、一宿一飯の恩義のかけらも見せずに、流れの中にそそくさと消えてしまった。プンプン。 低い位置にあった水草は殆どが根こそぎ流されていて、低くなった水位に合ったガサガサは殆どないという有様。しかも流心が川岸に迫っているのでドン深となっており危ない。水位が安定して、水辺に土砂が堆積し、そして新たな水草が繁茂するまでには、まだまだ時間が要るので、当分はガサガサは楽しめないのかも知れない。 ところどころにあるガサガサを探してやってみると、彼等も住居不足に陥っているのだろう、今日もヨシノボリがコンスタントに網に入った。しかもまた大きなスミウキゴリが二匹入る。さすがにリリース。 取り敢えず、幾匹かウキゴリに食べられて減ってしまったシマドジョウとスジエビを、補充用として持ち帰ることにした。ちなみにカマツカの方は今日はまったく採れず(T_T) いずれにしても台風によって川相は一変しているので、ガサガサのポイントはかなり変化している。子供と一緒にいけるような安全な場所も含めて、新ポイント開拓をしなければいけない。 |
||
| 2001-09-22(土) | 多摩川  |
|
| 06:00-07:00 | 曇り |
ヨシノボリ多数、 スミウキゴリ、シマドジョウ、 スジエビ、カマツカ、 ハヤ、モツゴ&モロコ類 |
| タモ網 | ||
|
次の台風が寄ってきたので、増水前にということで今週半ばの平日にガサガサ行を予定していたのだが、運良く台風もずれたので平日のガサ入れは中止。そして満を持して土曜日に臨む予定だったが、なんと金曜日に雨が降ってしまった。またまた増水だとガックリ。 土曜朝になって雨もあがったので、水槽に飼っていた魚の再放流も兼ねて多摩川へ行く。雨が上がったとはいえ鬼のような寒さ。つい数日前まで暑い暑いと言っていたのがウソのよう。秋が唐突にやってきた感じだ。 川に着くとやはり濁り切っている。水位の方は昨日の雨の影響もあるのか、一週前と比べても10センチほどしか下がっていない。やはり上流のダムで放水を続けているのだろう。水色もWAXMAN氏が云っていたように石灰を溶かしたような感じ。 先ずは再放流の魚を放つ。水槽に二匹いるスミウキゴリの大きいやつ一匹と、成長して我が家の水槽では大きくなってしまったタモロコ、ホンモロコ4匹。浅瀬に放したら、わき目もふらずに一目散に流れの中に帰っていった。増水して濁ってはいるが、やっぱり故郷の川の方がいいのだろう。 先週ガサ入れした場所は水が引き干上がり、陸地になっているので、今日時点の水辺のガサガサを探っていく。やはり一杯いる。タモロコは云うに及ばずスジエビ、シマドジョウ、ハヤ、ウキゴリ、ヨシノボリがビシバシ入る。とくにすごいのがヨシノボリで、ガサガサを始めてから今までに捕った以上のヨシノボリが採れた。あとで数えたが15匹以上。 ウキゴリも13センチもある巨大なやつを混ぜて3匹。そして今日のメイントピックスとなったのは新顔「カマツカ」である。多摩川中流で採れる小魚としてはムギツク、ギバチと並んで密かに狙っていたターゲットである。つい先日にも大学の後輩とカマツカの話をしていたのだが、「多摩川にカマツカなんているんですか?ニゴイの稚魚じゃないですか?」とバカにされていたが、何とそのあとすぐに採れるとは思わなかった。それも4センチほどのやつと2センチぐらいの稚魚の二匹。 先日攻めたクリークにも出かける予定だったが、運良くカマツカをゲットできたので、これ以上欲を出さずに、ヨシノボリなどをリリースして帰ることにした。というより、風が極めて冷たく、このまま居ると間違いなく風邪を引きそうだったので退散したというのが、もう一つの理由。 川にはアユ師は例によってパラパラと居たようだが、この寒さでは釣りの方はなかなか厳しいだろう。いずれにしても濁りが消えて、平水位にまで戻るのはまだしばらくかかりそうである。 |
||
| 2001-09-16(日) | 多摩川  |
|
| 14:00-15:00 | 曇り |
ヘラブナ、ウキゴリ、スミウキゴリ シマドジョウ、スジエビ、 モツゴ&モロコ類 |
| タモ網 | ||
|
避難騒ぎまででた大型台風も過ぎ、水もだいぶ引いてきたところで多摩川ガサガサに行く。ところが川に着いてみるとビックリ、まだまだ水が引いていないうえ、かなりの濁流である。上流のダムが開放されているのだろう。 いつも攻めている細流のポイントに行くと、光景はいつもとは様変わり。まるで普段の本流の如き流れになっている。流心が迫っており、濁流で底が見えないので、タモの柄でちょいと探ってみるとアーラ大変、底につかない。どうやら濁流によって洗掘が進んでいるようで、かなり急深になってしまっているようだ。これは危ない。 水辺が一部ワンドになっていて、浅くなっているところがあったので、そこぐらいしかガサガサが出来そうにない。水深にして10cm足らずのところをガサ入れしたところ、何と一回目から大きめのウキゴリが入った!しかもいつものスミウキゴリではなく、ウキゴリである。嬉しくなってガサガサと続けたら、いつものスミウキゴリをゲット。おまけに爪楊枝大のシマドジョウも入った。これはデパートでもけっこう人気が高いということが分かったので、育ててみることにする。 これで十分なのだが、色気を出して上流へ行くことにする。ママチャリで走ること五分でめぼしいポイントを発見。ここは普段は陸地になっているところで、ブッシュのジャングルだったのが、水が引いてきているために、広大なマングローブの池のようなクリークを形成し始めている。水深は一部ドン深な場所があるが、だいたい10cmから30cm。 目を凝らしてみると、やはり想像のとおり魚がかなり迷いこんでいるようだ。あちこちで波紋が立っている。じりじりと追い詰めていくと何やらデカイのがいる。狭くなっているところに更に追い詰めていくと、巨大なヘラブナが浅場に何匹もスタックしている。ヒエ〜ッ! 二つのタモを振り回して追いつめるが、相手はさすがに野生魚、いく匹かは逃げられてしまった。格闘の末、なんとか三匹をゲットできた。サイズは尺上ばかり。大きいのは40cmくらいある。巨ベラのすごい暴れ方に、小生自身びしょぬれ。今までヘラブナというものにはまるで関心がなかったが、こんなのを細仕掛けで釣れば、さぞかし楽しいことだろう。人気があるのもうかがえる。 クリークの中には、もっと怪しい魚がいるのだろうが、今の水位でスタックしているのはヘラブナのような体高のある魚だけ。ナマズやウナギなどは、もう少し水位が減ってみないと駄目だろう。もし、今週半ばに時間が出来たら、もう一回チャレンジをしてみたいところである。 |
||
| 2001-09-08(土) | 多摩川  |
|
| 14:00-15:00 | 曇り | 小ブナ、モツゴ&モロコ類 |
| タモ網、魚キラー | ||
|
早朝の鶴見川コイ釣行が急用で中断してしまったので、まったくの欲求不満状態。用件が一段落した午後のひととき、人の目を盗んでコソコソと多摩川へ。コイ釣り再開も頭にあったが、手にしたのはタモ網と魚キラー。特に鶴見川で魚キラーが、短時間とはいえ惨敗したのは大きな痛手。何とか獲物ゲットを心中期すものがあった。 先日の台風で河道が大きく変わってしまったことはレポートしたとおりだが、どうも伏流水の流れも一変したようで、いつも行く細流の水量、水温とも様変わり。ピカピカきれいだった底石にも早くもコケが一杯付き始めている。そうなると魚類相も変わっているようで、ウナギはおろか今迄コンスタントに採れていたヨシノボリやヌマチチブも全くゲット出来ない。たまに網に入るのはモツゴと小ブナだけ。 そんなわけで先日カムルチーをゲットした新たなポイントに早速移動。ところが水位が前より下がっているうえ、水温も何となくぬくく、雰囲気が一変してしまっていた。案の定、ここではオタマジャクシ以外は何もゲット出来ず、万策つきて対岸へ移動。 対岸のガサガサは結構よさげで、期待がもてたが流心が近いために意外と岸辺からドン深である。この手はスジエビがワンサカいる?はずであったが、意に反してモロコと小ブナだけしか入らない。いい場所があったので魚キラーを仕掛けてみるも、水流が強すぎてどんどん転がってしまう。結局のところ期待の魚キラーは、またもや空振りに終わってしまった。(T_T) やはり行いが悪いと川の神様のご加護もないようで、今回はガサガサ始まって以来の貧果となってしまった。ノリが悪いときは川に行っても徒労に終わることが多いようだ。 PS:台風11号の余波で川相はつまらなくなったが、週明けに15号がやってきて、また全てをひっくり返してしまった。今日はまだ河原は濁流の下だが、水が引いた後いったいどう変わるのかとても楽しみである。 |
||
| 2001-09-02(日) | 多摩川 | |
| 14:00-16:30 | 晴れ |
ヌマチチブ、スジエビ、コイ稚魚、 小ブナ、モツゴ&モロコ類諸々 |
| タモ網 | ||
|
昨日、一人で行ったのが娘に見とがめられ、夏休み最終日ということで、またまた多摩川に連日行くことに。とはいっても小生自身も全然イヤイヤではない。 日曜の昼過ぎということもあって、いつもとは違う場所を開拓するという目論見と、宿河原堰下のコイ釣り場が、台風でどう変わったのかを調べるということもあって、7月に娘と行ったことのある中州の池に行くことにした。 行ってみてビックリ仰天。あたり一面ブッシュが茂っていたはずの中州が、広大な石河原に一変している。おそらく台風の増水で堰の閘門を開けたのだろう、小生の首ぐらいまで一面に繁茂していた雑草は根こそぎ流されてしまったようだ。 中州にあった秘密の野池は残されてはいたが、伏流水の経路が絶たれてしまったようで、死んだ水の水溜まりになっていた。中には小魚が一杯いたが足を入れるような水質ではない。 もう少し下の東京に面したところまで歩くと、台風で溜まったであろう綺麗な砂に囲まれたワンドがあった。ここは水質も本川からまわっているのでまあまあ。ワンドの中は砂の底地で、小ブナやコイの稚魚がワンサカ採れる。すばしっこいコイの稚魚は多分初めて。いずれにしても今年の春に孵ったやつだろう。再生産が順調にいっていることが確認できたのは嬉しいことである。川崎側も東京側も結構な人が土手に出ているが、サッカーグランドよりデカイ広大な中州には馬鹿な親子が一組だけ。さすがに人の居ない中州は魚が濃いし気分もいい!娘も広大な砂場&水溜まりに大喜び。あっというまに全身ビシャビシャになっている。 東京側を流れる本川も見てみたが、急流且つ急深でとてもガサガサをやれる雰囲気ではない。それでも水辺の草をタモでしゃくるとスジエビが結構入った。家の水槽には一杯いるのでリリース予定だったが、帰り際に探った瀬尻のガサガサで手頃な大きさのヌマチチブが入ったので「ベイト」としてキープすることにした。ヌマチチブは新たに買う小型水槽に入れよう。 こんな感じで中州ガサガサ行はそれなりの成果をみたが、もう一つの目的のコイの生態調査は今ひとつ。パンを幾つかのポイントで流してみたが反応無し。どうやら台風でコイの居場所も大きく変わってしまったようである。これはじつに頭が痛いことである。そろそろ本業のポイントサーベイを始めようかな。 |
||
| 2001-09-01(土) | 多摩川  |
|
| 05:30-07:30 | 晴れ |
ウキゴリ、ウナギ、ライギョ、 ヨシノボリ、小ブナ、モロコ類諸々 |
| タモ網 | ||
|
ようやく9月、そろそろ秋の釣りシーズンインとなるのだが、小生の方は相も変わらずタモを担いでの多摩川通い。今日は朝早く目が覚めたのだが、それでもロッドを持たずにタモを持って出かける。 早朝のガサガサは初めてだったが、朝の空気はやはり気持ちがいい。ポイントはいつものところ。水位も落ち着いてきておりガサガサしやすい環境になってきた。ガサガサの楽しいところは毎回何かしらの驚きがあること。タモのなかで何かがビタビタ跳ねて「オッ」という声がでてしまう。これは、対象魚を絞り込んでしまう釣りというアプローチではそう味わえないものだ。 今回の「オッ」は何とウナギ君であった。河道が変わったことで行き先を間違えたウナギが細流に紛れ込んできたようだ。長さは測ってないが60ぐらいある立派なサイズ。クネクネ行き場を失っていたようで、ちょっと慌てたが今日は二刀流だったので、こねくり回して何とかタモ網にいれることが出来た。 その後はウキゴリをまたゲット。今度はサイズも小さく可愛いのでこれも持ち帰り。ウナギもそうだったが、けっこう細い流れの中にも魚は居る。これもおそらくは台風の余波なのだろう。単なる流水ではなく、ポイントは水温の低い伏流水を見つけることのようだ。 時間もあったので他のポイントも開拓しようと移動。最近までは砂州だったところが水没していて、いい案配にガサガサを形成している。泥が意外と深く往生したが、そのうちナマズが居着きそうな場所であるのでチェックを入れた。今日は何とここで二回目の「オッ」。カムルチーの幼魚(とはいっても15センチほど)をゲットした。噛まれたくないので写真をとってリリース。今日は実にめでたい日だ。まさに早起きは三文の得。 多摩川ガサガサの神様のような存在、中本賢さんの本に「ウナギ、ナマズ、ライギョを捕まえると、ガサガサからもう抜け出せなくなる」と書いてあったが、小生もこの先どうなることなのだろう。 |
||
| 2001-08-26(日) | 多摩川 | |
| 17:00-18:00 | 晴れ |
ウキゴリ、小バヤ、バラタナゴ、 ヨシノボリ、モロコ、モツゴ類諸々 |
| タモ網 | ||
|
前週の台風の増水が残っているかと気になったが、週末に出かけた芦ノ湖で大量のヨシノボリを見つけたためにガサガサ虫が騒ぎ出し、夕方の小一時間、多摩川に子供と一緒に出かけた。 いつものポイントに着くと、増水どころか水がない!なんと台風によって河道が変わってしまい、辺り一面が石河原に変わっていた! 肝心な河道ははるか彼方の東京寄りに、距離にして50〜60メートル移動している。河原に立って土手を見上げると、小生の頭ぐらいの草までがなぎ倒されている。あらためて川は生き物だと云うことを感じた次第。 ナマズやモクズガニの好ポイントは哀れ石河原の下に埋まってしまったが、細流の方は辛うじて生き残っていて、しかも伏流水位が上がっているのか水が多い。増水時に洗掘されたためか深みがあちこちに出来ている。子供にとっては膝下が腰ぐらいまで深くなっていたが、ワイルドな娘は勝手にずんずん進む。 本流筋はまだ水量も多そうだったので、今回は細流だけをガサガサしてみたが、なんと10センチを超えるバラタナゴをゲット。持ち帰ろうか迷ったが、近くでガサガサしていた親子がコツが分からないらしく、全然採れていないのであげることにした。 どうやら増水によって、上流からいろいろ新たな魚種が流れ落ちてきている様子。いままで採れたことのない模様のヨシノボリや、きれいな測線のホンモロコ、そしてとうとう念願のウキゴリをゲットする事が出来た。(詳細はアクアBOXに追ってUP) 氾濫は好ポイントを潰してしまうが、上からまた新たな魚を運んでくる。川の生態系を豊かにするという視点で見ると、これもまた必要なプロセスなのだろう。 |
||
| 2001-08-19(日) | 多摩川(沢井〜御獄)  |
|
| 14:00-16:00 | 晴れ |
アブラハヤ、サワガニ、 ハヤ稚魚類 |
| タモ網 | ||
|
今日も性懲りもなく多摩川へ、とはいってもはるか上流の奥多摩渓谷へ家族と一緒に川遊びに行く。出発が遅れてしまったので、途中の羽村堰あたりでお茶を濁そうとも思ったが、風景が目新しくないので、当初の目論見どおり、場所は酒蔵のある沢井駅から御獄駅までのエリア。 この辺りの多摩川は巨岩があちこちに点在している景勝地。水量も豊富でカヌーイストたちがたくさん遊んでいた。でもかなりの混雑で、なにもこんな山奥でカヌーの雑踏に揉まれなくても、とも思ったが、まあ集まるのが好きな日本人ということなのかも知れない。 こんな渓谷でも岸辺にはところどころに草がはえ、例のガサガサを形成している。とはいってもそれほど密度は高くなく、ポイントは少ない。そのうえ足元でも1m以上もある深みがあるので、子供のケアもあってけっこう大変。 岩の隙間など(ゴリゴリ漁法)がいいと思ったが、意外と深いうえ苦労しても採れない。やっぱりガサガサ周りがいいようだ。ほんとうの目論見は底棲魚だったが、採れるのはアブラハヤやハヤの稚魚ばかり。すこし目の前にはマスやアユが泳いでいるが、2〜3mもの深さがあって、これらはさすがにタモでは採れない。多摩川中流で怪しい魚ばかり見慣れている娘は「なんだまたアブラハヤか〜」と馬鹿にしてしまっている。 このままでは父親の威厳が…さらに落ちてしまうので、あちらこちら探ってみたものの、結局目新しいのは沢筋で採れた大きなサワガニだけだった。しかもこいつがやたらに食い意地がはっていて、バケツの中にキープして置いたアブラハヤを瞬く間に平らげる。やはりカニは悪食である。 そんなわけで、水はきれいな奥多摩ガサガサ行だったが、魚種も少なく成果と云うにはいまいちだった。上流部のガサガサは水量の少ない沢や小河川のほうが良いのだろう。でも川の水で冷やした生酒はうまかったな〜。 |
||
| 2001-08-18(土) | 多摩川  |
|
| 15:30-18:30 | 小雨・曇り |
ナマズ、オイカワ、 スジエビ、ヌマチチブ、 ギンブナ、シマドジョウ、 モツゴ&モロコ類諸々 |
| タモ網 | ||
|
今日は朝から久々の雨。午後になって止んだり小ぶりになったりしてきたので、いつものように多摩川へ。今回は一人なので別の場所を探そうと中野島堰堤に近いところを中心にガサガサを行うことにした。 いっぽう家にいた小ブナとドジョウは再放流。小ブナは可愛いのだが、動きがやや緩慢なため、ヨシノボリに狙われるらしく、尾鰭などが傷つけられてしまったので可哀想になり放免。また、ドジョウはいつも底の小石の中に潜っていて、どうも水槽用としてはエンターテイメント性が乏しいので、これも再放流。なかなか一長一短があって水槽の魚種選びは難しい。 川に着いてみるとビックリ。初めて他のガサガサ人に出会った。ウェーダーを履いた本格的なスタイルで「池の掃除になるのでエビを狙っている」という話だった。こんな小雨の時に来ているので見るからに採りまくりそう。ガサガサは先行者がいると全く駄目なので、いそいそと場所替えをした。 ただオジサンからいいことを聞いた。スジエビの居るガサガサは「葉っぱ系」ではなく、アシなどの「茎系」や「ササ系」だそうだ。「エビ狙いならもっと上だよ」という言葉も貰ったので、チャリに戻り上に移動していくと、オジサンがもの凄い勢いでガサガサをしながら遡行している。こりゃもっと上に行かないとと、一生懸命遡るとかっての河川だったと思われる池に到着。ここは意外とドン深でガサガサ出きるポイントは少なく難しいが、かっての水制テトラ穴をゴリゴリするとウワッというほどスジエビが入った。スジエビは本流よりこのような池の方が多いのかも知れない。 たんまり採ったあと、期待の中野島堰堤直下に移動、ところがここは水勢が強いうえ水質も意外と良くなく、たまにあるガサガサでも空振りばかり。もしかしたら先行者がいたのかも知れない そんなわけで、いつものポイントまで今度は下っていって、ガサガサを始めたらいつものように小ナマズをゲット。ナマズは居る場所が決まっているようだ。 しばらくガサガサしていたら「今日は駄目だな〜」と、くだんのオジサンが唐突に下ってきてビックリ仰天。この人はいったい何キロガサガサしてきたのだろう。とりあえずスジエビの御礼を言って、そそくさと別のポイントに逃げたが、まるで渓流で先行者に会うときのあの気持ちがちょっと出てきて、自分の小市民性を感じてしまった(やや自己嫌悪)。 その後、薄暗くなってから細流を攻め、初めてオイカワ成魚(15cmぐらい)と、本流筋で最近よく採れるヌマチチブをゲット。オイカワは初めてなので嬉しかったが、写真を撮ろうとしたら跳ねて逃げられてしまった、残念。 またヌマチチブはルリヨシノボリと勝手に思っていたが、バッチオさんの検分でヌマチチブと判明したので、過去の記述は全て訂正した。⇒自宅に調査のために持って帰ったが被害甚大となる。 |
||
| 2001-08-14(火) | 多摩川  |
|
| 10:30-12:00、17:00-18:30 | 晴れ |
ナマズ、ヨシノボリ、 ヌマチチブ、シマドジョウ、ハヤ、 ギンブナ、タナゴ、モクズガニ、 モツゴ&モロコ類諸々 |
| タモ網 | ||
|
風邪気味のせいもあるのだが、やはり朝は動けず釣りはパス。そして性懲りもなく多摩川へ行く、もはや日課の様相である。 今日は午前の部と、夕方に分けて行った。午前は水槽の魚の間引きのための再放流がメイン。とくに一昨日ゲットしたヨシノボリが性悪(?)で、タモロコ稚魚はイートしてしまうわ、小ブナを傷つけてしまうわで、放逐と相成った。あとは傷ついた小ブナと、動きがせわしすぎるやや大きめのドジョウなど5〜6匹が再放流の対象。 川に着いてみると、一昨日にあんなあった水位が下がっており、もとの平水位になっていた。水色も澄んでおり、再放流を無事済ますと、ちょいと試し打ちとばかりにガサガサをやる。水が澄んでいる上、好天なのでガサガサと云うよりも護岸石の隙間の影を中心に探ることにする。 石の隙間の出口にタモを置いて、奥を棒のようなもので刺してゴリゴリやるので、ガサガサと云うよりもゴリゴリと命名した方が良いかもしれない。さっそくヌマチチブが入った。これは一昨日のやつと同サイズ。 更にべつのポイントを攻めると今度はでかいウグイの群れが溜まっていたらしく、棒を突っ込むといきなり数匹がジャンプアウトして来た。運良くタモの中に一匹入ったがサイズは20センチ強ある。写真を撮ってリリース。こんなウグイを細糸で釣ったら凄い。 さらには泥底の浅場でモクズガニをゲット!美味そうであったが「お盆」でもあり、一尾だけ鍋に入れても冴えないので、これもリリース。 炎天のした、あまりに汗だくになって頭もふらふらしてきたので、一旦帰って夕方に日が傾いてから子供を連れて再度出陣。夕方になると川面をすべる風は一段とさわやか。やっぱり晴天の日中は自殺行為である。 子供はあいかわらず小モロコやアメンボをチェイスして大騒ぎであるが、小生は本流筋の石の間を探って、ヨシノボリやシマドジョウ、小バヤや、そしてまたいつもの小ナマズなどをゲット。今日はガサガサよりゴリゴリが良いようだ。 そんなこんなで賑やかな一日となった。毎回あらたな発見があって、ガサガサ&ゴリゴリはしばらく足抜け出来そうにない。(笑) |
||
| 2001-08-12(日) | 多摩川  |
|
| 16:00-18:00 | 曇り |
ナマズ、ヨシノボリ各種、 ヌマチチブ、シマドジョウ、ハヤ、 ギンブナ、ゲンゴロウブナ、ザリガニ、 モツゴ&モロコ類諸々 |
| タモ網 | ||
|
今日は早朝フィッシング(コイフライ)を目論んでいたが、このところの激務で朝は動けずにパスになった。ゴロ寝もいいのだが子供にせがまれて(?)、例によって一緒に多摩川へ行く。天候も曇りがちなので、ガサガサには好都合。 川に着いてみると、前回より水位が10センチほど増水気味である。平野部では雨はさっぱりだが、上流部でまとまった雨が降ったらしい。そう云えば人工降雨に成功したとかしないとかいうニュースが耳に残っていたので、それのことかもしれない。 河原には大勢のアユ釣り師がでているが、それにしても河原に散乱しているのはアユ仕掛けのゴミ屑。市販仕掛けを使っているあたり俄鮎師と思うが、いい大人が情けないものである。映画「千と千尋の神隠し」ではないが、河の神様を汚し「オクサリサマ」にさせないように、川で遊ばせてもらっている人間はもっと謙虚に川のことを考えなくてはいけない。 今日は前回探ったところから始めたが、不思議なことに同じところで同じ魚が入ってくる。やはり同じように見えるガサガサも、魚によって微妙に棲み分けがされているらしい。今回はスジエビは駄目だったが、10センチを越えるヌマチチブをゲット!そのほかトウヨシノボリやナマズ、ドジョウなどの底生魚がやたらに入った。やはり増水の濁りでこれらの魚が活性化しているのかも知れない。 ヌマチチブと小ナマズについては、水槽の住人をいじめそうなので、惜しいがリリース。またヨシノボリも種類が異なるのが採れ(トウヨシノボリ他詳細不明)大満足。ドジョウも大小いろいろな種類が混ざり、ヨシノボリとともに小柄な奴を選んで家に持ち帰った。いれてみたら、ちょっと底部が過密状態になってしまったので、しばらく様子を見てから一部再放流して減らすことにする。 |
||
| 2001-08-05(日) | 多摩川  |
|
| 16:00-18:00 | 曇り |
ナマズ、ヨシノボリ、スジエビ、 アブラハヤ、小ブナ、ザリガニ、モツゴ&モロコ類諸々 |
| タモ網 | ||
|
ここ数日、冷房病のためかひどい頭痛に悩まされていたが、一日エアコンを止めて汗みどろになったら不思議と治ってしまった。文明の利器は功罪なかばということか。 だからという訳ではないが、今週も原始的な漁法「ガサガサ」をやりに、子供と多摩川に行く。 今日は珍しく終日曇りがちで、釣りには絶好の日和ではあったのだが、朝は前日の休日出勤の疲れで寝過ごしてしまい、昼は昼で子供と生田緑地にザリガニ釣りに行ったりで動けずに過ごす。ようやく夕方になって時間が出来たのだが、面白しさにハマってしまったのか、一般的な魚釣りではなく、やっぱりガサガサにいくことにした。 先日は流れの強い場所を中心に探ってみたが、底生魚が採れなかったのと、今日は子供も一緒なので、水の緩い浅場を中心に探ってみる。 川につくと、元気な小学生達が今日も瀬尻で泳いでいる。渇水期ではあるのだが、水質は結構良い。やっぱり多摩川は年々キレイになっている。 今日攻めたのは、中州の末端や瀬脇に出きる「溜まり」。水が死んでいるところもあるが、なかには砂底から冷たく澄んだ伏流水があふれ出ているポイントが幾つかある。これは実際に川に入ってみないと分からない。 そのような、砂底、泥底を中心として探ってみると、なんとナマズ君が続けざまに網に入った(15センチぐらい)。水槽で飼うには手頃な大きさではあったが、メンテ(エサ)の問題も面倒だし、今また水槽を追加すると家庭内争議が避けられないので、諦めて写真だけ撮ってリリースすることにした(T_T)。大きくなってからの再会を約す。このサイズのナマズが採れると云うことは、多摩川で順調に再生産していることをあらわしており、実に嬉しいことである。 そのほかにはギンブナ、アブラハヤ、スジエビ、ザリガニや、いつものモロコ&モツゴ類。そしてとうとう淡水ハゼをゲットできた! ポイントは護岸石にへばり付いていたアシの中。サイズは3〜4センチぐらいしかないが、スジエビと一緒に持ち帰る。 家に帰って調べてみたら「カワヨシノボリ」のメスらしい。ハゼ類は個体差が結構あって識別はなかなか難しい。ヨシノボリの特徴(?)らしい目〜口への赤線もないので妙だが、それに近いゴクラクハゼとも斑紋が違う感じ。面倒なのでカワヨシノボリだと思うことにした。どうもあんまり凶暴でもなさそうなので、とりあえず他の小魚やエビと一緒に飼うことにする。 しばらく様子をみて、もしもエビや小魚がどんどん食べられてしまった場合は、また川に返そう。 増水時に出来た河原内の池や、ホソもガサガサをしてみたものの、このところ増水がないので場荒れ気味、伏流水のために水質は良好だったがほとんど採れなかった。やはり一雨欲しい。 |
||
| 2001-07-29(日) | 多摩川  |
|
| 14:00-16:00 | 晴れ | スジエビ、ドジョウ、小ブナ、その他諸々 |
| タモ網 | ||
|
先日のガサガサが楽しかったので、再び多摩川へ。ただし今日は単独行なので気恥ずかしい。 ときどき日は射すものの雲が多く、絶好のガサガサ日和。先日は中州に渡ったが、モツゴ、タモロコの類ばかりだったので、今日は本流筋のガサガサを探っていくことにする。 日曜とあって川にはアユ釣りの人や、川遊びの人がけっこう出ている。前に来たときは猛暑だったので人は少なかったが、今日は過ごしやすいということもあったようだ。なかにはフリチンで泳いでいるマッチョな子供たちも居た!人が集まってくる川はいい川である。 水温を測ってみると27度。やはりかなり高い。そんなわけで水通しが良いようなガサガサを中心に探る。狙いはスジエビとヌマチチブ・ヨシノボリなどハゼ類。面白いことに上から見ると深くないようなガサガサも、意外と奥行きがあってびっくりするようなことも。このようなところでは何かしら小魚が入る。 とはいえガサガサ二回目のビギナーであるので、いわゆる「読み」が甘く、ねらったガサガサでは何もゲットできず、意外なところで珍しい魚が入ったりする。やはり、これも「経験」を積まないと駄目なようだ。 今日もまたウェーダーではなくアクアソックを履いていったので、水を肌で感じることができ、いくつか湧水(水温がぐっと低くなる)が湧いているところも発見できた。これらは水温が下がったときのポイントとして記録しておく。 ガサガサで網を仕掛けるポイントは、中本さんの云うようにやはりヘチ(水際)のところ。ここが開いていると、魚も必死なのでスルリと逃げられてしまう(逃亡が見えないのでわからないが、隙があると先ず魚が入らない)。 ゲットできたのはモロコ、モツゴ類に加えて、ザリガニ、ドジョウ、ギンブナ稚魚、キンブナ稚魚、そしてお目当てのスジエビも♪ 水槽に入れるスジエビと小ブナを少し残して後は逃がす。 やはり本流筋の方が、魚の種類は豊富なようだ。ハゼ類を探して瀬尻の石まわりや、河原の中にある溜め池なども探ってはみたが、すべてスカ。 淡水ハゼ類のガサガサポイントをもう一度勉強しなくてはいけない。 あっと言う間に時間が過ぎて、気がつくとハラペコで目が回りそう。ガサガサは思いのほか腹がへる遊びらしい。まだまだ探るべきポイントは残っていたが、そんなわけで40数歳のガキはバケツを抱えて家路を急いだ。 |
||
| 2001-07-22(日) | 多摩川  |
|
| 17:30-19:00 | 晴れ | 小バヤ、タモロコ稚魚無数 |
| ビンドウ・タモ網 | ||
|
先月下旬以降ほとんど雨が降っておらず、ドピーカンの連打。まさに「日照り」状態である。もともと暑さにめっぽう弱い小生、そのうえ暴飲?がたたってダウンしてしまい。とても魚釣りなどと云う状況ではなかった。 そうはいうものの、今月に入ってから釣行がわずか二回というていたらくに、これではイカンと、日曜日の夕方になってごそごそ釣り支度を始めた。 ところが運悪くキャンプから帰ってきた娘に見つかり。「たまがわにいっしょにいきたいよ〜」という羽目に。 仕方がないので、つい先日に多摩川フォーラムで聞いた中本賢さんの話がまだ耳に焼き付いているので「よし今日はガサガサだ〜」と釣りを諦めて、川遊びに行くことにした(ということでこれは釣行記とは呼べないのかも知れない‥)。 今日のポイントは一つ。中州の原っぱの中にある池だ。ここは先日コイ釣りに来たときに見つけた秘密の場所。土手からは見えないところにあって、水は伏流水が流れており子供の遊び場としては適当なところと目星をつけておいたところ。 途中の釣具屋で多摩川用の半円型のガサガサ玉網を購入(900円也)、ジュースやお菓子を買い込みポイントへ。 この場所は中州にあるので普段は子供などは容易に行ける場所ではないが、いまは減水状態。二人でバシャバシャと瀬を渡っていく。 今まではウェーダーの世話になってはいたものの、こう暑くなって減水してくるとウェーダーは邪魔もの以外の何者でもない。半ズボンにお揃いのアクアソック(知っている人は知っているが、サーファーなどに使われている海辺用の即乾メッシュ地のスニーカー、暑い時期のガサガサやウェーディングには実に勝手が良い。ナイキ製)で全身ビショビショになりながら川に入って遊ぶ。 炎天猛暑だったためか、夕方なので皆帰ってしまったのか分からないが、河原には釣り人はあまり居ない。犬の散歩で泳がせている人は結構いたが‥ お目当ての池は二つあって、湧水が湧いている小さい方はブッシュでなかなか近寄れず(水温も低くいけそうであったが、やや不気味で今回はガサガサはやめた)、もう一つの大きい方は足場は良いものの減水で水が回っていなくて、やや水温も高くなって水質も前よりやや悪化していたが、それでもかなり綺麗なのでここでガサガサをやることにする。 案の定、掬う度に小魚が入り娘は大はしゃぎ、小生は大物を目指して深みのガサガサを中本さんお教えのようにやってはみたが上手くいかず、子供の前で父親の威厳を高めることは失敗。とはいえ子供にとっては多摩川の自然の豊かさを満喫できたので成功。(^o^)v 魚掬いも飽きたので、持ち帰り分だけ残しリリースし、中州の秘密基地でお菓子を食べてから日が落ちる頃にまた早瀬を渡行して帰ったが、夕マヅメで小魚が瀬に一杯でている。早速瀬の中程に簡易式のヤナを作ってバチャバチャバチャ、またもや小バヤを大量ゲット! そんなわけで、子供をダシにして結構たのしいガサガサでした。 |
||

 |