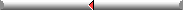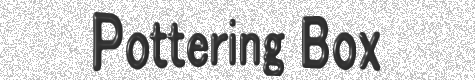 (((((Riverside Pottering))))) |
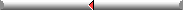
遡河行再開: だいぶ前の話になりますが、渋谷川(古川)の遡河行ルポを取り上げたことがあります。ともすると暗渠にされたり、ドブ川扱いされたりと、都市化の中で弄ばれていうる小河川の様子を紹介したいと思い始めたのですが、あれからずいぶんと日が経ってしまいました。 そのときは、渋谷川以外についても調べてみたいと思ったのですが、小河川といえども、いずれもそこそこに長さがあるので、もう少し纏まった時間ができたらと、延ばし延ばしにしてきました。歩いて遡るとなると、どうしても構えてしまいます。 チャリで遡るという発想は、当時はまるで浮かばず、一昨年にとらくろを買った時にも、彼の活用などは考えもしませんでした。その時は釣りだけをイメージして、このフォールディングバイクを買ったからです。歳とともに、知らぬ間にアタマが固くなってきているようです(笑)。 さて、とらくろは持運びと組立も簡単なので、週末を利用して、この冬は都市小河川の徘徊を再開することに致しました。とはいえ、小生はチャリも川も好きなので、双方の視点から、遡河行レポートをしていきたいと思います。ただし、メインはポタリングによるものなので、従来の「ガイア」ではなく「ポタリングBOX」にUPすることにしたいと思います。  小河川巡りの相棒「とらくろ」 二子玉川: サブテーマが「遡河行」ということなので、原則的には下流から、みなもと(源流)を目指すアプローチをしていきたいと思います。小生が再開後にまず選んだ「野川」ですが、町田市にある拙宅からもさほど遠くない位置にあるので、二つ目の都市小河川としてはふさわしいと思ってとります。ちなみに「野川」という名前の由来で有力なのは、野水をあつめた川、というものです。この川の源流部にあたる、国分寺や三鷹の崖線から湧き出る水を指して、野水と呼んだのでしょうか。 多摩川の支流ですので、二子玉川の合流部が吐出し口にあたり、ここが遡河行のスタート地点ということになります。蛇足ですが、このエリアの野川は、人工的に開削し作られたもので、昔の野川という川は、もっと上流の狛江市宇奈根付近で多摩川に注いでいたという話です。今では、入間川も仙川も野川に合流して、さも野川の支流のような扱いになっておりますが、これらも元々はそれぞれ独立して多摩川に注いでいました。ところが、17世紀初めころ、有名な六郷用水(次大夫堀)の開削にあわせて、それぞれの流路が束ねられてしました。(現在の野川吐出し部は、次第に使われなくなった六郷用水から、多摩川へ水を逃がすバイパスとして40年ほど前に開削されました) 多摩川への合流部。ここには兵庫島公園という、ちょっとした散策スポットがあって、綺麗に整備されております。兵庫島の由来は、以前に拙HPでも紹介したような気がします。さらに、ここには「礫間浄化施設」という、河川水質の浄化システムが埋設されており(これもまた過去に解説したような記憶が…)、この効果?もあるのか、このエリアの水質は、都市河川としてはかなり良いと思われます。20年前には2桁楽勝であったBODも、いまでは4mg/L程度にまで良くなっています。河畔にいても、まるで臭いは感じません。流れをみるとキラッキラッと小魚が反転しています。この時期ならば越年オイカワ幼魚でしょうか?  兵庫島(左側)と野川河口域 多摩川の感潮域は、合流点からずっと下流にある調布取水堰(丸子橋)までですので、野川には汽水域にはなっておりません。つまり野川は純淡水河川ということになります。野川に棲む生き物たちにとっては、多摩川が「海」のような存在ではなかろうかと思いました。懐の深い多摩川ではぐくまれた稚魚たちが、しだいに野川に遡っていく様が、小生の脳裏にイメージされたからです。生態調査では、兵庫島付近の野川では、たくさんの魚が確認されております。
野川の河畔にはサイクリング道路が整備されていて、快適に遡ることができます。しばらく行くと大きな流れ込みがあります。これが仙川との合流部です。仙川も住宅地のど真ん中を流れておりますが、三面護岸なので水質は野川より落ちる感じです。落差がかなりあるので、やはり野川の河川床が作られたものであることが分かりますし、野川から遡上するような魚は殆どいないと思われます。  仙川合流部 次大夫堀: 野川の水はけっこうキレイです。一昔前はドブ川で大変だったそうですが、やはり下水道整備の効果でしょう。しばらく走ると、左手にきれいな公園が見えてきます。これが次大夫堀公園です。ここは六郷用水を開削した代官、小泉次太夫を記念して作られた公園です。なかには六郷用水の流路をのこした水路が走っています。 公園内には、世田谷の古民家を残した民家園などがあって、とても静かでひなびた空気が漂っています。俳句の会かなにかがあるようで、同好の人たちが集まってきていました。この一角だけみると、とても世田谷区とは思えません。あとで調べたら、公園には河川水浄化システムなどもあるということでしたが、気がつきませんでした。  次太夫掘公園。後ろは民家園。 世田谷−狛江: 次太夫堀公園を抜けると、また野川サイクリング道路に合流します。すると、今まであまり見たことのない構造物を見かけました。落差工というにはあまりにフラットです。いずれにしても河床の養生のための構造物(護床工)でしょう。夏場は干上がるとも言われるほど流量の少ない野川で、このような構造物を作る理由を知りたいところです。  落差工もどき。働きがよく分かりません。 小田急鉄橋を渡ったところで時間もなくなったので、とらくろを仕舞って喜多見駅から帰りました。
狛江−調布: 年がかわって、正月早々にコーダ君で新春ポタリングをしました。始めは多摩川サイクリング道路をチンタラ走っていましたが、正月からけっこうな人混みで面白くもありません。 ならばと、狛江五本松公園あたりから曲がって、前回とらくろを片付けた喜多見まで走り、そこから野川を遡河することにしました。野川の河畔を走るには、コーダ君はToo-Muchの感じもしましたが、まあ、こういう気まぐれライドもいいかなと走ります。 右岸に車両基地をみながら上がると、おそらくは野川初めての堰(斜路工)がありました、粗石構造で、勾配も緩く、遡上魚にとってもやさしい斜路工です。都内の小河川では、最近、落差工から、このスタイルの斜路工への改修が進められております。とりわけ生物相が貧弱な都市小河川では、貴重な水生資源を少しでもいたわるような、こういった改修が強く望まれます。  魚にやさしい粗石付緩勾配斜路工。  しばらく上流には昔ながらの落差工。小魚にはツライ。 しばらく走ると狛江市に入ります。入間川が合流していたはずですが、気がつきませんでした。クロスバイクだと、やはり平均速度が高くなってしまうのでしょう。河畔のスローライドはミニベロに限ります。 東京都の河川行政は、多摩川を初めとして、従来型の治水一辺倒から、やすらぎや生活空間の一要素として河川環境を見直すような形に移行しつつありますが、今回のポタリングで驚いたのは、野川のような小さな川でも低水敷をしっかり残して、更には流域の人々が川に近づけるような環境をしつらえていることです。 偽善的な親水護岸には親しみを覚えませんが、低水敷を残すことで、川の生き物にも、流域の人々にもやさしい環境を与えていることには大賛成です。たしかに昨年の神戸市の小河川でのゲリラ豪雨による惨事は痛ましいものでしたが、防災管理と河川親水環境とは、必ずしも相反するものではなく、折り合いがつくものだと信じております。  低水敷の散歩道。土の部分を残すことは大切。 野川は狛江市と調布市の市境を縫いながら走りますが、しばらく行くと調布市内に入ります。すると少しずつ川の様相が変わってきました。低水敷は残しているのですが、水辺には取ってつけたような石の護岸(修景ブロック護岸)。水辺には葦などはありません。これではまた箱庭です。自然の働きによる水辺の多様性が大切なのに、まるで長い年月で、風合いの出てきた木工細工に、見た目が悪かろうとペンキを塗りたくっているようなものです。
行政区が違うだけで、どうしてこれだけ川をダメにしてしまっているのでしょう。我が鶴川村の大先輩、白洲次郎の言葉を借りると『プリンシプルがない行政』ということになるのでしょう。  「見せかけの自然護岸」。川と陸地は構造物で分断。 がっくりしたので、深大寺から野川を離れて、武蔵境通りと鶴川街道経由で、家に帰ることにしました。
三鷹−調布−小金井: とらくろがショップで入院(ディレイラー交換)していたので、次のパートもコーダ君になりました。とはいえ、野川のような小さな川を散策する場合は、やっぱりミニベロがベストです。クロスバイクだと、どうしても前に進む慣性がスムーズすぎていて、見たいところでも、あっと思うまもなくスーッと通り過ぎてしまうからです。スピードは出していなくとも、どうしても流れてしまい、本人の意識以上に前進してしまいます。次回パートは絶対にとらくろにしたいと思います。 さて、今回は武蔵境街道から上流域です。まずは三鷹市になります。それまでと似たような風景が続いて、しばらく走るとまた調布市。小金井市との境を縫うように野川が流れていますので、両市境を行ったりきたりします。河畔には水車小屋などが建てられていて、とてもいい感じです。川の水もとてもきれいです。  水車とコーダ君 また、斜めにカットした面白い落差工を見つけました。こうする事で、流路に対して直角となる、普通の落差工よりも、パートによって流れに変化が生じて、結果的に魚があがることが出来るようになるのでしょうか。
 斜めの落差工 やがて広大な野川公園に入ります。この公園はハンパではありません。公園内の野川はとても美しく、ここまでのポタリング行は、まさにこの風景をみるために走ったのだなと、つくづく感じた次第です。
南には広大な広場があります。ここはどこにもある、いわゆる広い公園ですが、北部分は必見です。鉄柵で保護されていて、自然観察のための遊歩道が整備されています。崖線(はけ)から湧出する清水で、いくつかの湿地と池があり、貴重な生態系を保全しているようです。時間があればじっくりと観察したい場所です。  野川公園。今回の流域のベストポイント。  自然観察エリア。遊歩道完備。 野川公園を過ぎて、京王の支線をくぐると小金井公園。野川公園ほどではありませんが、ここも緑が広がっております。このあたりに住んでいる人たちは本当に幸せです。都内でこれだけ整備されているエリアは限られています。東京都はやっぱり大したものだと思います。いちおう小生も都民のはしくれですので、ちょっぴり良かったと思います。 前原地区にある小学校では、なんと校庭の下を野川が流れています。暗渠にしたのは、授業や行事をやるための窮余の策でしょうが、個人的には校庭を川が横切っていたら、非常に子供たちにとっては、貴重な経験になるはずなので、暗渠にしてしまうのは勿体無いと思いました。(小生の小学校でも、普段は枯れ川でしたが、川が校庭を横切っていました。幾度も落ちましたが、なぜか今でもよく憶えています。)  校庭をくぐる野川
天気もにわかに曇ってきて、寒くなってきたためにキアイが急速に失せてきました。ちょうど小金井街道に当たったので、ここから帰路につきました。残りは次回。やはり冬のポタリングは寒いです。
小金井−国分寺: 野川行脚の最終パートは、やっぱりとらくろ登場。今回のとらくろは、さらにパワーアップしています。RディレイラーをSoraからTiagraにグレードアップし、シフターワイヤーも最新素材に交換したからです。今までどうにも緩かったシフト感触が、とてもスムーズにスパスパ入るようになりましたし、見た目もかなり立派になりました。  SoraよりTiagraにグレードアップ。
本当は、安物リールのようなラチェット音がするフリーハブを静音型に換えたかったのですが、ボスフリー型なのでスプロケットと一緒に交換する必要がありました。調べると、対応可能な歯車数が、Max26Tまでしかなく諦めました。坂道対応を考えると、現在の最ロー28Tは、どうしてもキープしたかったためです。
解説すると、MTB用スプロケットならば、最ローギアが28T(現行)以上のものもあるのですが、この場合、更にディレイラーもMTB用にしなければならず、このメカがけっこう長くなります。小径車の場合だと、長すぎるRメカは芳しくなく、状況によっては路面を擦ってしまうことにもなりかねず、残念ながらあきらめました。 とらくろの機能を活用し、途中の多摩川河畔までクルマで運び、そこから走ることにしました。当日は底冷えがして、厚い雲が垂れ籠もり、時折り雪が散らつくというバッドコンディション。とうてい楽しげにポタリングなどをする様な状況ではなかったのですが、他に日取りも立てられずに決行しました。 府中競馬場の回りにそって小金井通りをひたすら北上。ずっと平坦な道取りですが、ぐりぐり30分も漕いでいると温かくなってきます。汗をかきたくは無いので、以降は大幅にペースをダウン。時速15キロ内外の、文字通りスローライドで行きます。ほどなく野川に到着。  ここまでくると野川も細流に。でも一級河川。
源流域が郊外ですと、遡河するたびにひなびて来て、走っていても楽しくなるのですが、住宅地の中の遊水にみなもとを発する野川の場合はそうなりません。川幅が細くなってくるに従って、どんどん野川に対する扱いがぞんざいになってきます。都市河川の場合は、こういったケースが沢山あります。渋谷川はとうとう暗渠化されてしまい、その存在すら認識されていませんでした。
野川の場合は、暗渠化はなく、その点では救えますが、あるところからはとうとう三面護岸の、どこにでもある排水溝になってしまいます。  見たくは無かった三面護岸。
寒いなか、がっくりしてしまいましたが、野川の場合、救われたのは源流部付近のはけから流れ出る湧水群が見事に整備されていたからです。厳密には支流になりますが、その昔、尾張徳川家の鷹狩り場だったことにちなみ「お鷹の道」とか、名水に選ばれた「真姿の池」など、整備された一角は、とても見事なものでした。真冬に訪れたにも拘らず、オイカワが元気に泳いでいて、手を入れると、とても温かったです。湧水が豊富に湧き出ているのでしょう。
 お鷹の道。ステキな散策路になっています。  脇の清水では何人もがペットボトルを持参していました。
掬って飲んでみたいところでしたが、雪がぱらつくので、先を急ぐことにしました。野川の源流部はJR中央線を挟んだ、電機会社の研究所の敷地内にあるので、そこへは到達できませんでしたが、線路をくぐるトンネルまではたどり着きました。こちらは、誰もみむきもしないような住宅街の外れにありました。
 野川源流へのトンネル。
なにはともあれ、これで何とか野川遡河完了。4パートにも割れてしまいましたが、やはりというか、とらくろで巡った区間の情報量は、面白いことに、コーダ君と一緒だった区間よりずっと多いです。どうしても平均速度には差が出てしまい、そのぶん多くの小さな情報を見逃していたようです。
次は、どの川を巡ろうか思案しておりますが、どこにせよ、ゆっくりライドで行くことがやはり肝心。そうなると、とらくろは「川チャリ」にもピッタリです。  武蔵野崖線の澄んだ細流と、相棒とらくろ This page is edited by Zaurus。 |